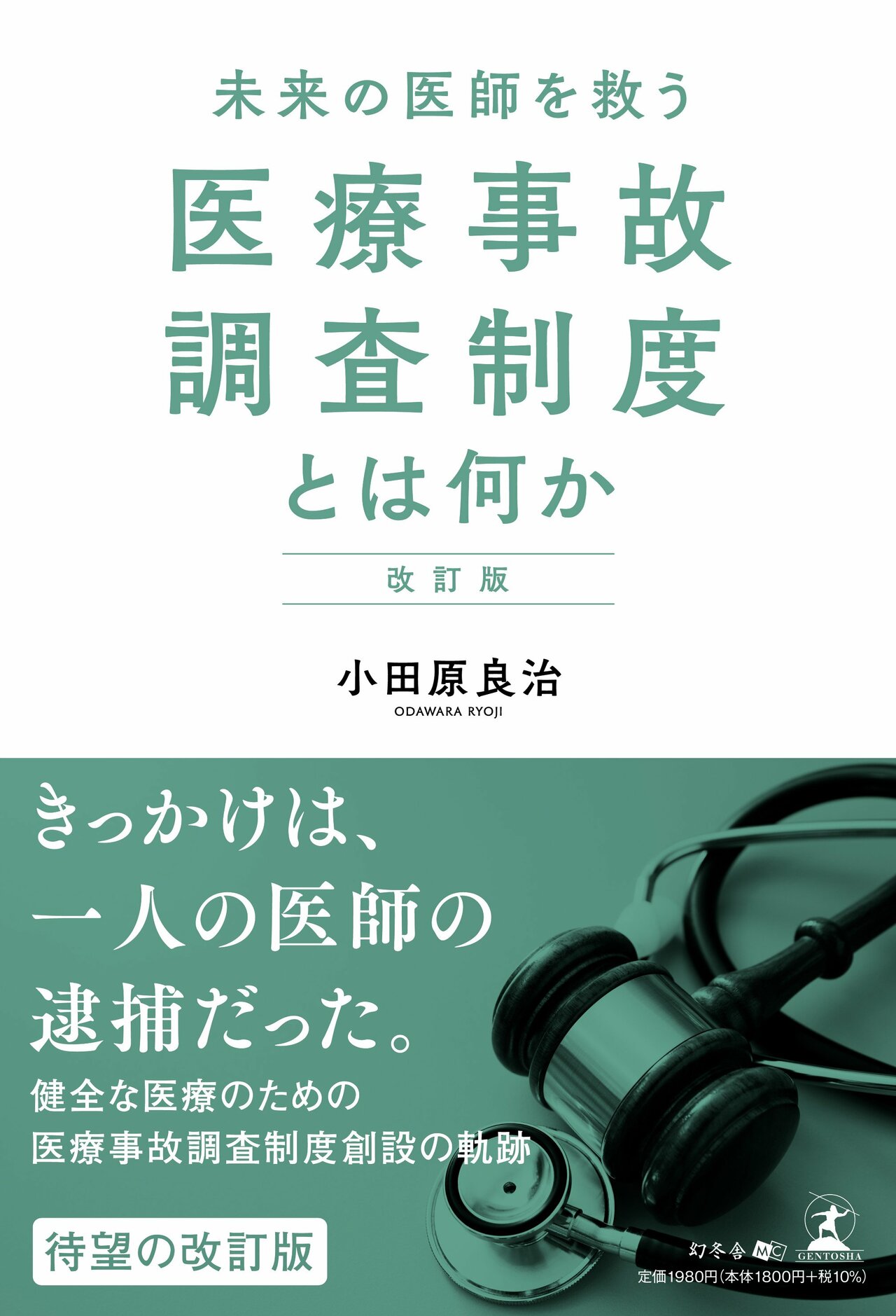東京都立広尾病院事件東京地裁判決
3)
その後、三月十日、Aの夫であるCが保険金請求のため、Aの死亡診断書、死亡証明書の作成を都立広尾病院に依頼してきて、H事務局長にその用紙を渡し、H事務局長は、翌三月十一日、これを主治医であったD医師に渡してその作成を頼んだ。
D医師は、都立広尾病院内でその作成を始めたが、死因として、不詳の死または外因死と記載するか、病死と記載するかで悩んだ。
その理由は、Aが死亡した直後の二月十二日付けで、死因の種類を「不詳の死」とした死亡診断書を作成してCに手渡していたところ、この時点では、病理解剖の所見などから病死を推認させるものは何もなく、
むしろ、Aの右腕の色素沈着、F看護師が薬物を取り違えたことを認めていることなどから、事故死としか考えられない状況下であるのに対し、他方、事故死をこれらの書面に記載して保険金請求等に用いられることにより、病院が事故死を認めたことが公になり、病院に対する社会的非難が集中すると思ったからである。
そこで、D医師は、自分個人の判断ではなく、病院全体の判断で決定して記載すべきことであると考え、院長である被告人に相談することにして、院長室に赴き、死亡診断書と死亡証明書の用紙を見せて、死因についてどのように記載するのが良いか聞いたところ、
被告人も、どうしたらいいかわからないなと悩んだ様子で、J副院長、Z副院長及びH事務局長を院長室に呼んで、どのように書けばよいかを話し合った。
その結果、未だAの血液検査の結果が出ていなかったこともあり、ヒビグルによる事故死と断定できないし、病死の可能性がゼロではないので、病死としても全くの間違いではなく、入院患者について不詳の死とするのはおかしいなどとの発言もあったので、
結局、死因として解剖の報告書に所見として急性肺血栓塞栓症といった記載があったので、死因を急性肺血栓塞栓症による病死として記載する旨その場の意見がまとまり、被告人の指示で、Dは、死因を外因死や不詳死ではなく、病死あるいは自然死であるとして、判示第二記載のとおりに、死亡診断書、死亡証明書に記載してこれら書面を作成した。
ところが、その内容をD医師がM医長に見せたところ、M医長は、死因を病死として記載しては問題となるのではないかとの意見を述べたが、D医師は、同日、2通の書面をH事務局長に渡した。
M医長は、翌三月十二日、院長室に行き、被告人に対して、死因を病死として記載して良いのですかと言ったところ、被告人は再度J副院長、Z副院長及びH事務局長を呼んで話したが、
被告人はM医長に対し、保険金請求のための診断書であり、前日の会議でそのように書くことに決まった旨述べ、H事務局長に対し、遺族からクレームが付いたら、現時点での証明であることを説明するよう指示した。