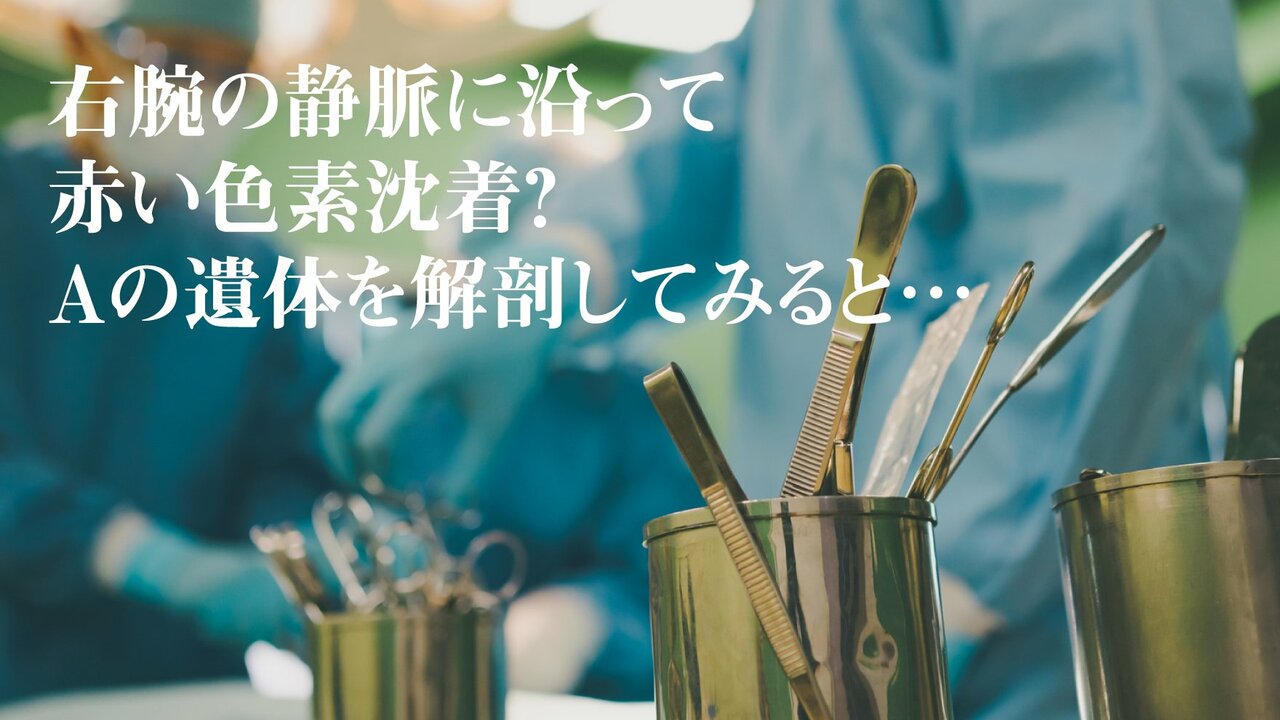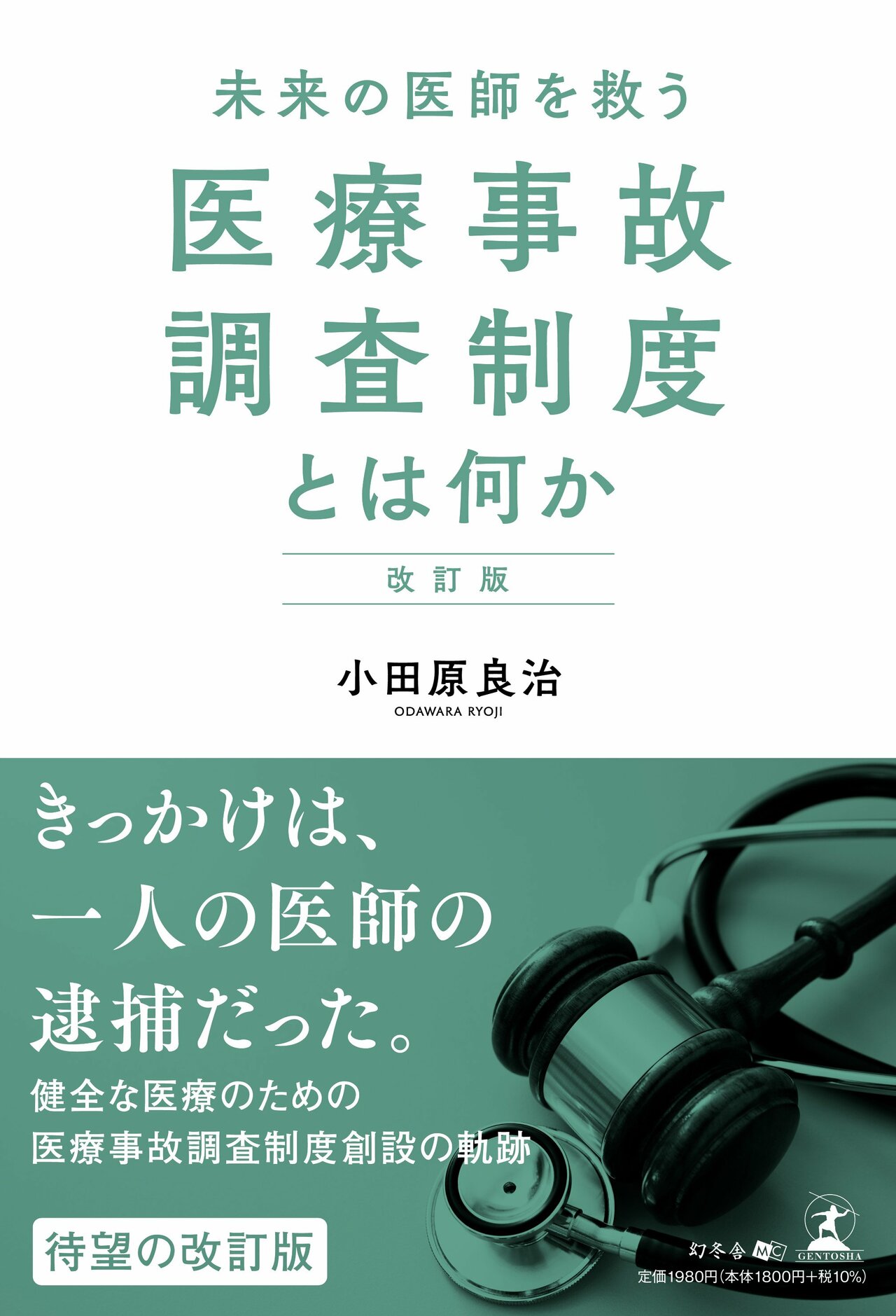東京都立広尾病院事件東京地裁判決
被告人の公判供述、検察官調書、証人D医師の証言及び検察官調書謄本、証人J副院長の証言及び検察官調書、証人H事務局長の証言及び検察官調書、証人L医師の証言などの関係各証拠によれば、次の事実が認められる。
1)
Aの病理解剖は、二月十二日午前9時半頃から、都立広尾病院で病理解剖や検査等を主に担当していたL医師が中心となって行われることとなったが、
L医師は、当日朝、都立広尾病院のO技師長から、対策会議で検討中であり、すぐには始まらないということを聞き、事件性の否定できない遺体の解剖であると認識したので、
大学の病理学の助教授であり、都立広尾病院の非常勤の医師でもあり、法医学の経験もあり、普段から頼りにしているN医師に連絡を取り、解剖への協力を頼んだ。
同日午後零時前後頃、L医師は被告人らから病理解剖を始めるようにとの指示を受け、D医師やM医長立会いのもと、N医師が来る前であったが、ぼちぼち始めたところ、Aの遺体の右腕の静脈に沿って赤い色素沈着があるのを発見し、D医師にポラロイドカメラでその写真を撮ってもらったが、
その赤い色素沈着は消毒液の静脈注射による変化で、劇物を入れたときに出てきたものであろうと思ったので、外表所見以外は手がつけられないと判断し、遺体にメスを入れずに、N医師の到着を待つことにした。
N医師が来て、遺体の右腕の状況を見て、警察に検案してもらいましょうということを提案したが、O技師長から、そんな時間はない、すぐに始めてくれと言われた。
そこで、N医師が監察医務院に連絡を取った方がよい旨言ったので、L医師が電話で連絡をとろうとしたが、解剖室の電話は外線につながらず、そのうち、O技師長は直接電話をしてもらっては困る、対策会議が発足している以上そちらを通して欲しいと言い、
自分で内線電話で院長室に電話をかけ、電話に出たI医事課長に対し、病理解剖の医師が警察に届け出た方がよいと言っていると伝えたが、
I医事課長が、被告人に今までの方針でよいか尋ねると、被告人は「それでやってください」と言い、警察に届け出ないまま病理解剖を進めるよう指示した。