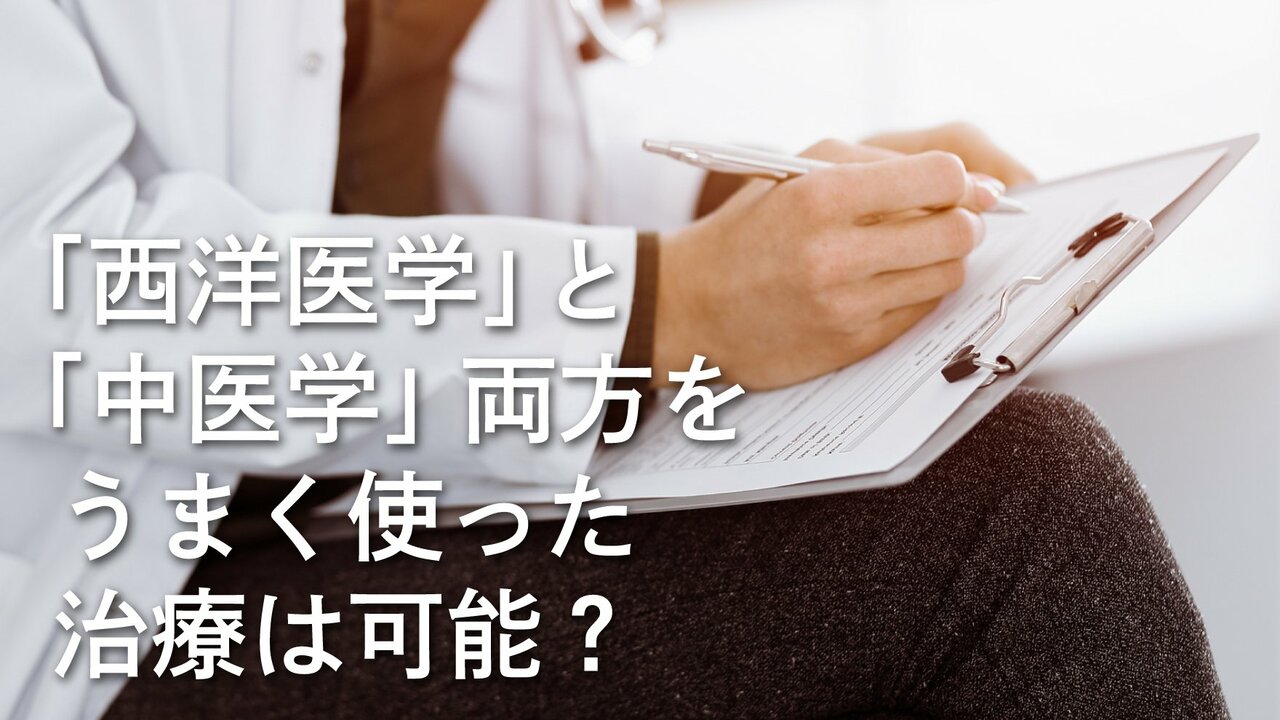翌日の一時限目。大学の大人数の授業では、階段教室になることもある。ちょっとした体育館ほどもありそうな教室の後方に僕は指定席のごとく陣取っていた。目はそれほど良くないので、あまり後ろだと見づらいけれど、前の方で熱心に授業を聞いて雰囲気を盛り上げるタイプでもない。むしろ後ろで密かに授業の邪魔をしないように、ときには居眠りの一つもできる席を好む。
僕の隣では内村がそのでかい指で熱心にチコチコとスマートフォンをいじっていた。
「沢波くん、ちょっといい?」
授業前のまったく無防備な背後から不意にかけられた声に慌てて振り返る。そこには凛とした雰囲気の春田恵美がなぜか冷ややかな目で見下ろしていた。僕は彼女に何か悪いことをしたのではないかと、自分の胸に過去の所業を問いかけてしまう。とはいえ暖かくなってきたからか、薄手のシャツに明るめのジャケットを羽織っている春田は、いつもからすると目を合わせやすい。
僕はちょいとあごを突き出して会釈した。
「昨日のお礼」
春田が唐突に紙袋を突き出した。茶色いマチ付きの手提げ袋。
(は?)
思わぬ事態に、にわかに頭が回らない。すっと息を吸い記憶を覚醒させる。
「あ、ああ……そんなんいいのに」
少し体をのけぞらせながら、両手を上げて断る。僕としてはたいしたことをしたつもりはない。自転車を引き起こすのはもちろん、逆に傷の処置なんて押し付けがましかったかもと思うくらいだ。というかそっちの気持ちのほうがはるかに強い。
そんなわざわざ僕なんかにお礼なんて、と思っていると、
「本当に助かった。ほんの気持ちだからもらっといて」