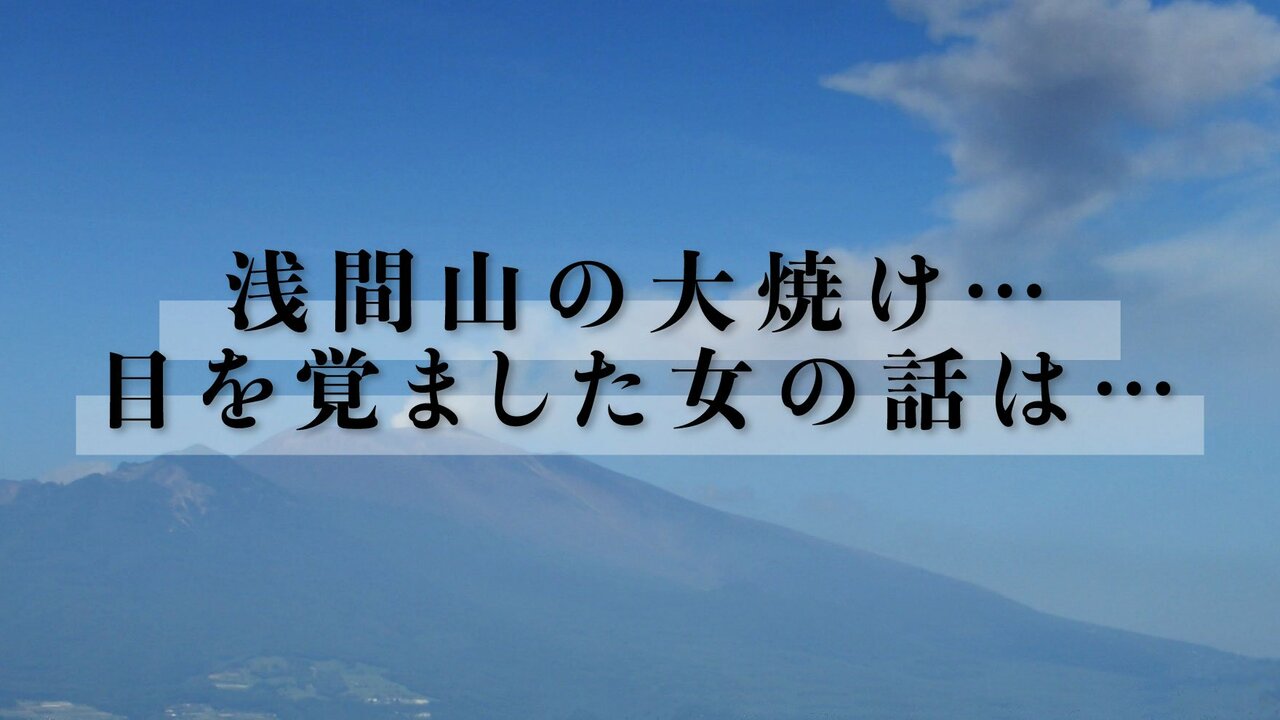奉公
伊助が十六歳になると、年季奉公が残り少なくなったことが雇い人たちの話に上るようになった。結衣は少し大人の仲間入りをはじめる年頃になっていた。
(もうすぐ伊助がいなくなる。年季奉公が明けるとここを出ていってしまう…)
そう思うと結衣はなんとなく胸が苦しくなるのを感じていた。
(伊助なんか奉公人のくせに態度は大きいし、私のことを無視するし、大嫌いよ!)
と思いつつも、なぜか日増しに伊助のことが頭から離れなくなるのだった。
(どうしよう。…そうか、伊助の借金を増やせばいいのね。そうすれば帰さなくてすむ)
と、浅はかにも考えた。
結衣は月に一度、踊りの師匠のところに稽古に通っていた。今回は近く開かれる御披露目会の衣装合わせのため、着物やら帯やらを持参せねばならず、伊助に葛籠を背負わせた。
「伊助、伊助! そこに出してある着物や帯を葛籠に入れてちょうだい。着物は振袖が三枚、帯が三本それに簪(かんざし)と櫛が二本ずつ、間違わずに入れてよ!」
おさきがそばにいるにもかかわらず、わざと伊助に手伝わせた。
師匠の家での衣装合わせや舞台稽古も終わり、おさきが着物を畳んでいると、結衣が簪の一つをそっと袖の中に隠した。おさきに見られていることに気づかなかった。
「伊助、急いで着物を葛籠に入れてちょうだい。帰るわよ。さっさとしなさい!」
結衣はそそくさと立ち上がり部屋を出て行こうとしていた。
慌てた伊助は畳まれた着物や帯を急いで葛籠に詰め込むと、両手で抱えて結衣の後を追った。屋敷に帰るやいなや、結衣が葛籠を開けさせ騒ぎだした。