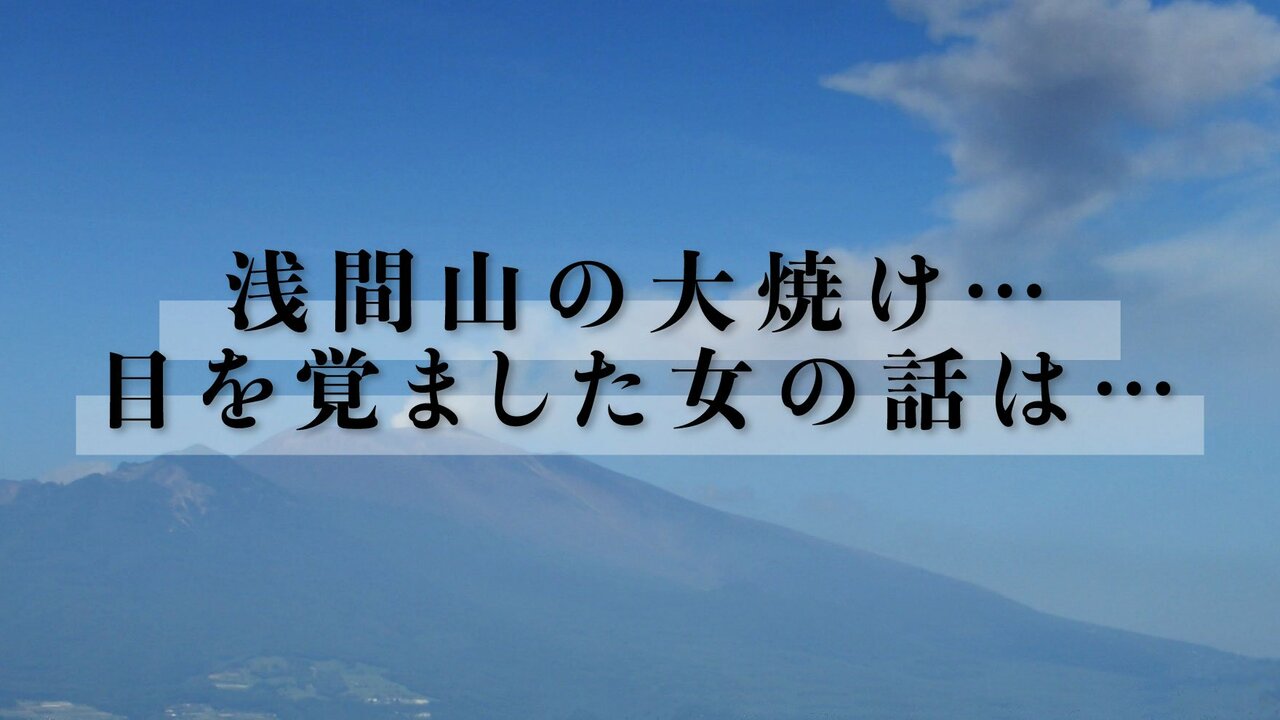奉公
伊助がこうした仕打ちにも逃げ出さず堪えたのは、逃げれば親や名主に迷惑が掛かると思ったのと、年季明けで帰ったら、親に自分が売られたことの恨みを思いっきり言いたいという一念からだった。
九右衛門が養子を迎えようと考えたのにはわけがあった。
九右衛門家は代々この地で名主を勤める名門の家柄である。ひとり娘の結衣にはいずれ然るべき家から婿を迎えて家を継がせ、名主として村の運営や年貢米の管理などの本業を行わせ、養子には山林の管理や木材の伐り出し、杣人の管理などを行わせようと考えていたのである。
しかし伊助の養子縁組がご破算になったため、この件は先送りすることし、伊助には年季奉公の間だけでも山林管理の見習いをさせることにした。
時が過ぎ、伊助は心も体も逞しくなっていった。
ある日、伊助が九右衛門に呼びつけられた。結衣を連れて山林を検分してくることを命じられたのである。山林の案内役として吾作がついていくことになった。
「お嬢様は相変わらず我儘放題、好き勝手に暮らしておいでだ。旦那様も日頃の行状が気になり出したんだろうな。先行きを心配して暮らしぶりを変えさせなければと考えるようになった。そこで、年の近いおめえさんに白羽の矢を立てたんだろう。まあ、諦めな」
と、吾作は言いながら伊助の肩をポンポンと叩いた。
不満をたらたらと並べ立てている結衣をなだめすかして山歩きさせていた。見晴らしのいい高台に立つと吾作が絵図を広げ、結衣に山林の説明をはじめた。