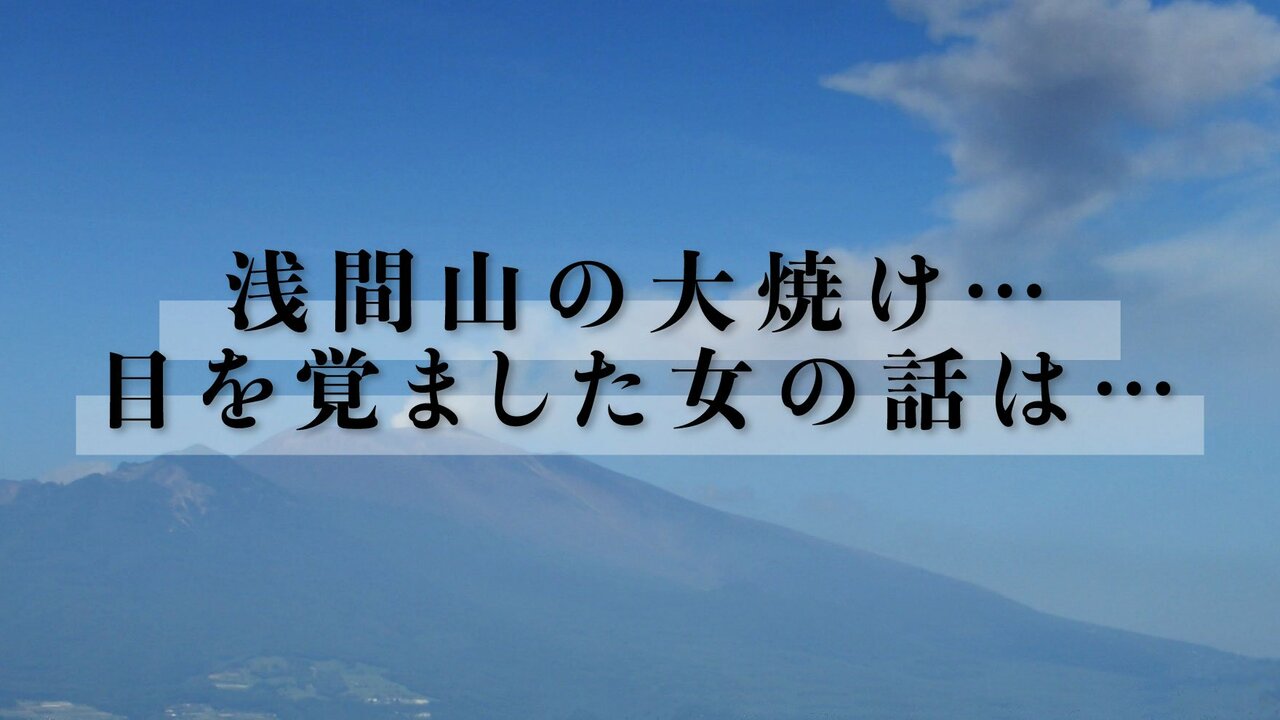「伊助、簪が一本足りないわ。なくしたのね!」
「いいや、そんなことはねえ。稽古場にあった着物、小道具類は全て葛籠に入れた。見落としがねえか、稽古場を出るとき確認したから間違いはねえ」
「だってないんだから、二本持って行ったの見てたでしょ? 弁償してもらいますからね」
「そうは言ったって、俺の給金は借金の返済に消えちまうから払えねえですよ」
「お父様に言っておまえの借金に加えてもらうわ」
「俺は簪がなくなったことは知らねえ。大事な踊りの道具なんだから自分でちゃんと確認して俺に渡すのが道理だと思うがな」
「もう、生意気ね。弁償して責任取りなさいよ!」
おさきが着替えを手伝う振りをして、結衣の袖にすっと手を入れ、隠してあった簪を取り出し、帯を解く隙に後ろから結衣の髪にそっと挿した。結衣は不満を伊助にぶつけていてそのことに気づかなかった。
「あら、お嬢様。髪に簪がついたままですよ。ほら、これ」
「えっ、そっ、そんなはずないわよ!」
髪に手をやると袖に隠したはずの簪が挿さっている。
「あれっ?」
伊助が笑いをかみ殺していた。結衣は恥ずかしさのあまり背を向けて自室の襖を閉めた。
「伊助さん、お嬢さんを許してやってね。お嬢さんは、伊助さんが年季明けでいなくなるのが寂しいのよ。だから引き留めたくてこんな意地悪するの。まだ子どもなのよ」
と、おさきの詫びる声が廊下から聞こえた。結衣は切なさに唇をかんだ。