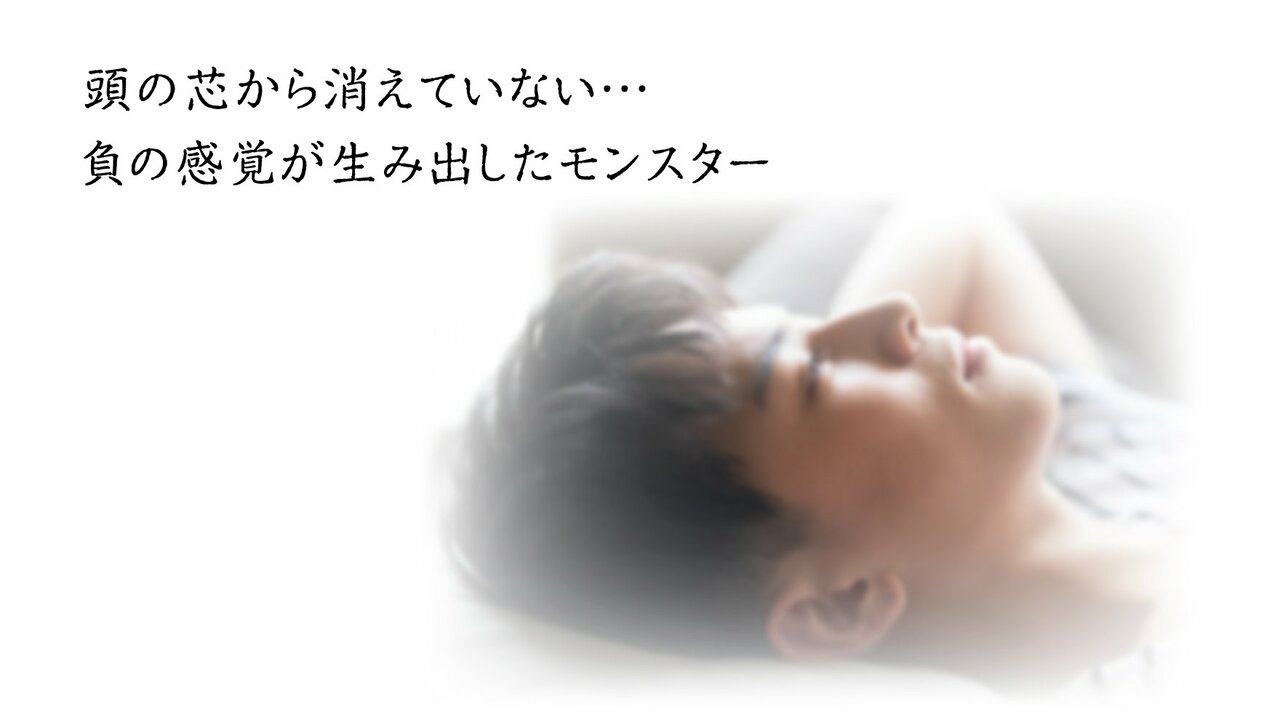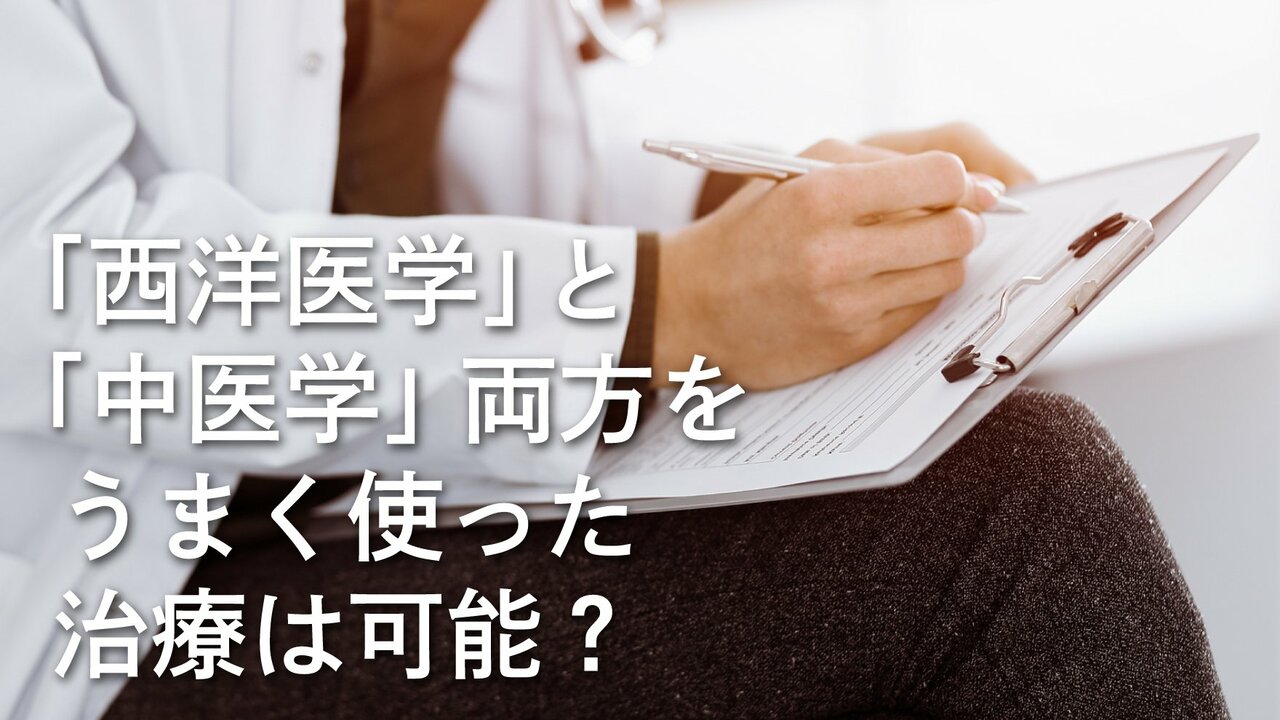プロローグ
『なぜ僕だけこんな目に合わなければならなかったんだろう……』
この二年間何かの折にふれ繰り返し頭に浮かんでくるフレーズ。それは今でも変わらない。ただ一つだけ、現在形が過去形に変わろうとしていた。
今日の夕方、彼──沢波俊樹(さわなみとしき)はようやく回復して、高知(いなか)から京都のアパートに戻ってきた。
およそ五カ月ぶりにこのドアを開く。ドアの鍵は……確かにここで間違いない。油が切れかかっているこのドアは、引き開けようとわずかに動かしたところでいつも『キィー』と小さな音を立てる。ドアノブに手を掛けたときそんなことが思い出された。そしてドアも彼を覚えていたらしく、しっかりと応えてくれた。
六畳一間片隅キッチン+ユニットバストイレの部屋に一歩足を踏み入れた。昨年十一月のあの空気が残っているようで嫌な気分だ。何よりも先に窓を全開にした。三月末の春を含む冷気がザーッと流れ込んできて、部屋の隅々にまで澱んでいた邪気を払い清めてくれる気がした。
机の横の壁に掛けた、数字だけの飾り気のないカレンダーは、しっかり『十月』を示している。十一月三日に部屋を後にしたときは、カレンダーをめくる余裕すらなかったのだろう。
ベッドの枕元には目覚まし時計が三台。そのうち付き合いが一番長かった黒い一台は破壊され、動きを止めている。青と白の二台はこの五カ月間、誰のためでもなく真面目に時を刻んできたようだ。こいつらには何度も助けられた。共に戦った戦友のような気さえする。
朝決められた時間に大声を上げ、気が付けばすかさず頭を叩かれ大人しくさせられる。逆に起きられなかったら起きられなかったで、なぜ起こさなかったと叱りつけられる。彼らはしっかり任務を遂行しているのに常にきつく当たられて、今ではとても申し訳なく思ってしまう。
小さなキッチンの横にはバーボンウイスキーの空瓶が直立している。本来彼の主な役割は、人をリラックスさせて、楽しい時間を作りだすことだろう。それが、とてつもなく不愉快な任務を負わされ、すべて飲み干されることなく無情にも捨てられてしまった。その香りすら残すことを許されず、今側面のラベルだけが、彼の存在を物語っていた。
ざっと掃除器をかけた後、血だらけの布団のシーツを換えた。シーツは数枚用意してあり、毎日のように洗濯していた。それでも洗い流しきれない血が無秩序にこびりついているそれらは、傷だらけの体を懸命に守ってくれていたはずで、やはり感謝の念を抱いてしまう。