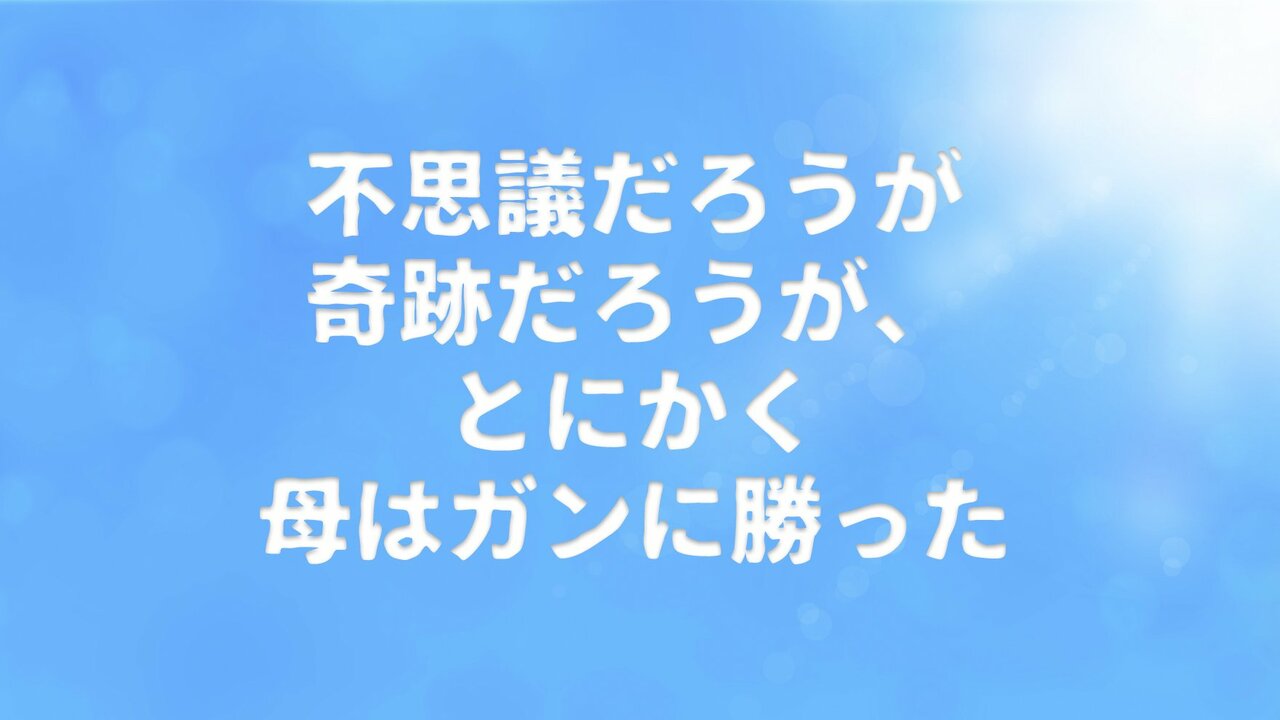第一章 青天霹靂 あと377日
二〇一六年
二月十九日(金)晴
夕食を終えた母は、ばたりと横になったきり、どことなく元気がない。
気になって薬ケースを見ると、やはり今日も飲んでいない。「二日くらいやめてみて様子を見ましょうか……」と、坂本師長の妥協案以降、一週間もさぼったままだ。
食も急に細くなり、昨日も今日も半分ほどしか食べていない。
うるさい事を言うのは可哀想だが、仕方なく小言を言うと母もようやく自覚したようで、明日からまた飲むと言ってはくれたもの、どうも心配だ。既に舵(かじ)修正のきかない方向へ向かってしまってはいないだろうか。いかなる秘薬も焼け石に水となりつつあるのではないだろうか……。
(全身に流れる血液の波と共に薬効成分も隈なく巡るはずと思っていたが、実は脳だけは関門が厳しく、ある種の成分以外は全てシャットアウトされ、簡単に辿り着けない仕組みになっているらしい。だから、身体のガンには効いても頭までは届かないという残念な事実を、この時の私は全く知らなかった。)
二月二十一日(日)晴
ちょくちょくと何か小さな土産を持ってくるように心掛けている。
今日のそれは、いつか新堀さんと一緒に作ったススキ穂のフクロウと倍賞千恵子のDVDだ。

眩しく暖かい陽にあたりながら歌を聴く時が、何よりの至福である。
「あきの……あきの……」と、母が言葉を吃る。
「オレがどうしたの?」と聞くと、「秋の砂山」と、母が言った。
母は、イントロを聴いただけで次々と曲名を当てていく。
大丈夫……、母の認知機能はまだまだ捨てたものではない。
こうして、新しいDVDやCDを持ってくれば、いつだって母は途端にご機嫌になる。母にとっての一番の薬は、やはり歌なのだ。
夢中で聴いているうちにいつの間にか斜陽刻(どき)である。
「茜色だねぇー」、ふと母が言った。
「詩人みたいな言い方をするなぁー」とからかい、母の笑顔をうながした。