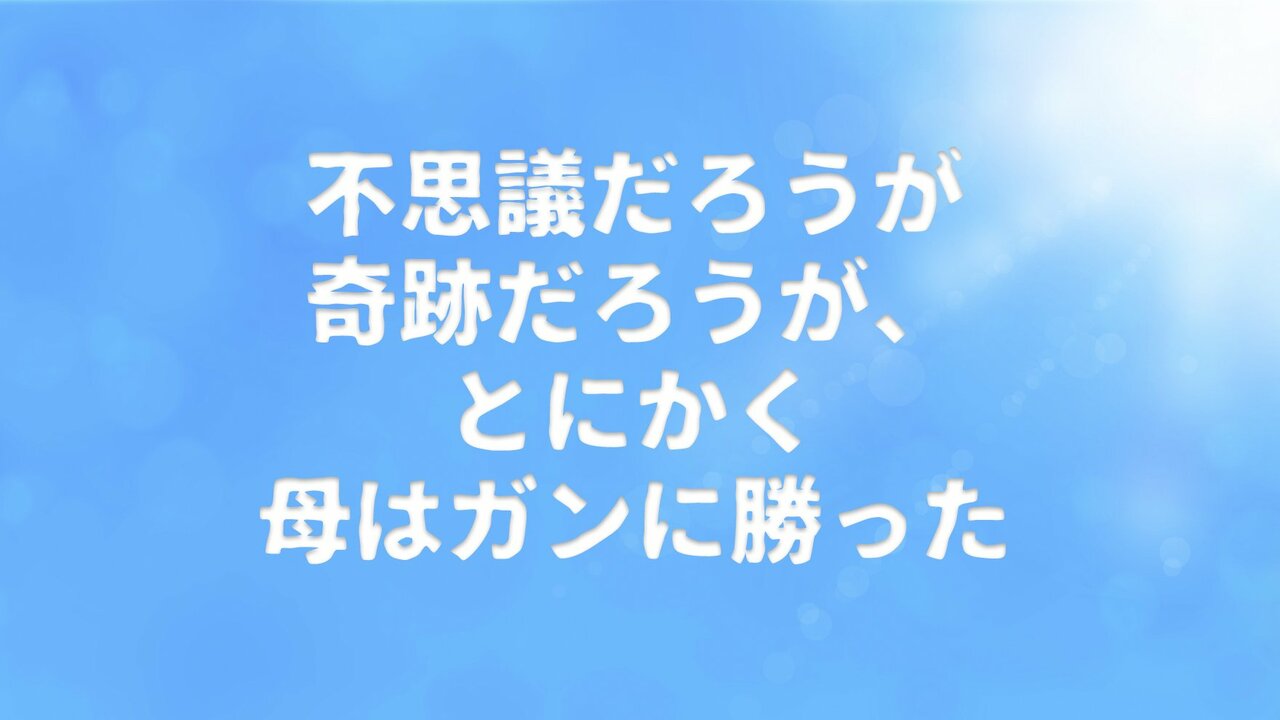第一章 青天霹靂 あと377日
二〇一六年
二月十六日(火)晴
甘酒を作り、ポットで持ってきた。
飲む点滴と言われるように、これで少しは滋養がつくだろうか。
飲みながら、“ヨッちゃんアルバム”を一緒にめくっていた……。「もう、九年も前になるんだねぇー」。祖母の実家、赤沼家のルーツを探しに秋田から東北を巡った事がある。その昔、祖母が住んでいたという秋田市・新屋(あらや)まで行き、古い菩提寺を尋ね当て、墓前の土を小ビンに持ち帰り祖母の墓へ入れてあげたのを覚えている。
「田沢湖ではスワンボートを二人でこいだねー。それから、角館、三内丸山遺跡、遠野……、そうそう、花巻の『賢治祭』では、宮沢賢治と親しかったっていうお婆ちゃんと知り合いになって、ハーモニカ吹いて聴かせてもらったけねぇ。いろんな事あったね、覚えているかい……」と、時々記憶力テストをはさむ。
回想法とかいうもので、昔の思い出を辿る事により脳が活性化するのだそうだ。
今はまだそうでもないが、いずれ母は大切な想い出を少しずつ忘れ、一つ二つと落し物を増やしていく。

二月十八日(木)晴
♪
真白に細き手をのべて
流るる血汐洗い去り
巻くや繃ほう帯たい白妙の
衣の袖は朱あけに染み
−−婦人従軍歌−−
午後の陽射しをあびながら、母と並んで古い歌を聴いていた。
明治期の軍歌であるが、きっとこれは、少女時代の母が祖父の蓄音機で聴いた懐かしいものなのだろう。
戦場へ従軍する看護婦たちが、敵味方の別なく献身的に看護を行うという、識らずと涙を誘うような歌である。

「お母さんは、どうして看護婦になろうと思ったの……」と聞くと、少し遠くを見てから「じょ、助産婦さん……」と、破裂音のような声で言った。
「子供のころから助産師になりたかったのか」と聞けば、「うん」と頷く。けれど、母は始めのころ外科の看護婦をしていたはずであり、それから引っ越しのたびに色々な科を経て、初めて産婦人科に勤めたのは確か四十歳ころになってのことだ。だから、俄(にわか)には鵜呑みに出来ずものの、何度聞いても「うん」としか答えず、髪をかきあげたりキョロキョロしたりを繰り返す……。
もしかすると別の事を言おうとしているのか、それとも曖昧な記憶を探ろうと困惑しているのだろうか……。
母は、啄木の詩の如く、じっと自分の手の甲に目を落とした。
ガラスごしの光は冬とは思えぬ暑さだ。これなら、今年の桜は少し早く咲くかもしれない。そうすれば、母に見せてあげる事が叶う。母の気力が失せる前に……。