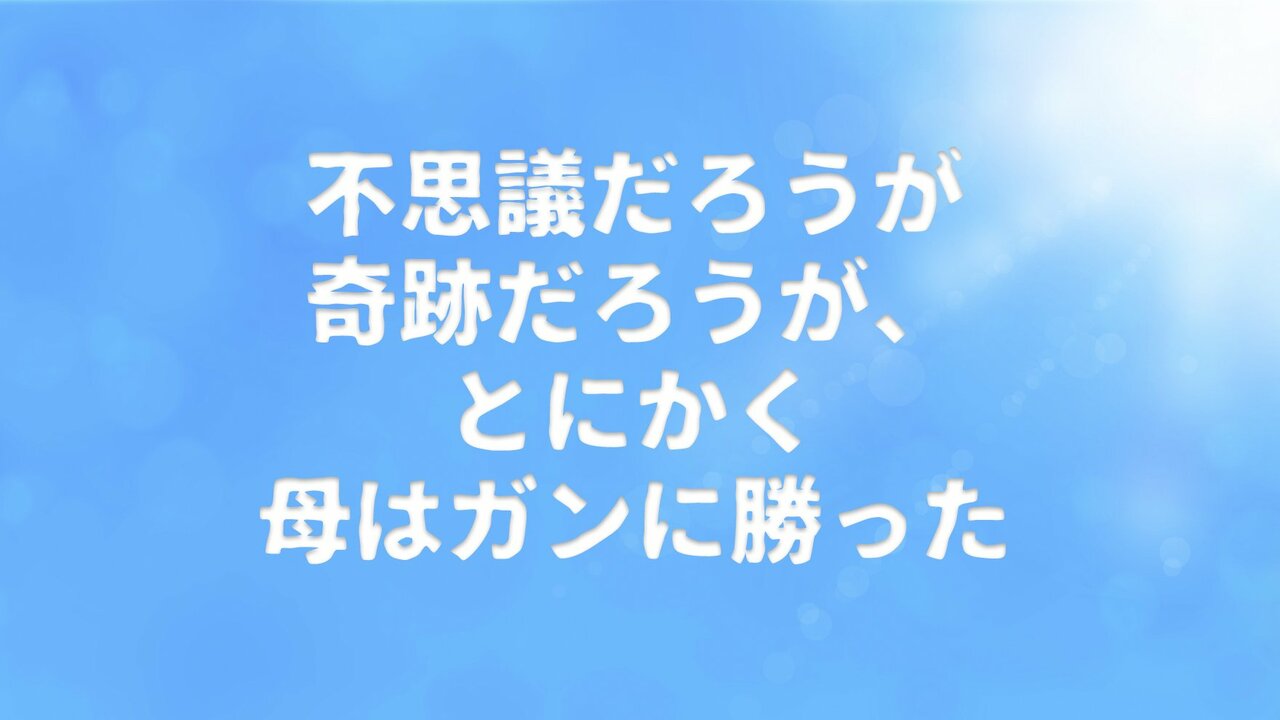第一章 青天霹靂 あと377日
二〇一六年
三月二十七日(日)
夕食時……、今日は、よほど具合が悪いようで食堂へ行くのもままならず、ベッドの背を起こしての給仕となった。
スプーンを持つ気力さえ見せないのは初めてであり、これでは給仕(きゅうじ)というより給餌(きゅうじ)であろう……と、悲しくなった。
大好きなカボチャの煮付けを二口ほど食べただけで、他の惣菜にはそっぽを向く。かろうじて、海苔の佃煮には口を開けるが、それでもやはり二口三口でいっぱいの様子……。けれど、デザートのフルーツとアイスクリームはちゃんと平らげ、コンデンスミルクをかけたイチゴは七つも食べた。
とうに満腹顔の母が「イチゴちゃん、イチゴちゃん……」と、言うものだから、「もっと食べるか」と、聞けば「いらない」と言ってそっぽを向く。でもまた「イチゴちゃん、イチゴちゃん……」と、繰り返す。何とも可愛い母である。
*
夜……
帰ろうとする私に母が言った。
「お願いがあるの……」
「なに」
「お、お、お願いがあるのよ……、あの、あのね……」
けれど、やはり母はその続きを伝えてはくれなかった。
言おうとする思いはあるのに、それを発することが出来ない。と言うより、言葉そのものを忘れてしまい、意思を言語に置き換えられないのだ……。
“喚語(かんご)困難”と呼ばれるこの現症は、母に混乱と苦痛の極みを与え、以後、見る見る言葉を失くしていった。
三月二十八日(月)
急に元気のなくなってしまった母のために、今日から、車椅子がリクライニング付きの大型のものに変わり、食事の介助もつくようになった。
「楽ちんか?」と聞いても「うーん」と小さくうなずくだけで、喜んでいるのか、それとも症状の進行を嘆いているのか……。
リハビリも既にリハビリではなく、理学療法士に抱えられながら立ち座りを何度かするのがやっとで、向後は、体力の現状維持……、と言うより、これ以上の減退を極力おさえる事が目標になった。だから、手すり棒につかまっての歩行訓練も既に無用だ。
日当たりのいい窓辺で、景色を見ながらするリハビリが好きだった母。けれど、今日は「もう帰りたい」と、蚊のなくような声を震わせるだけだ。