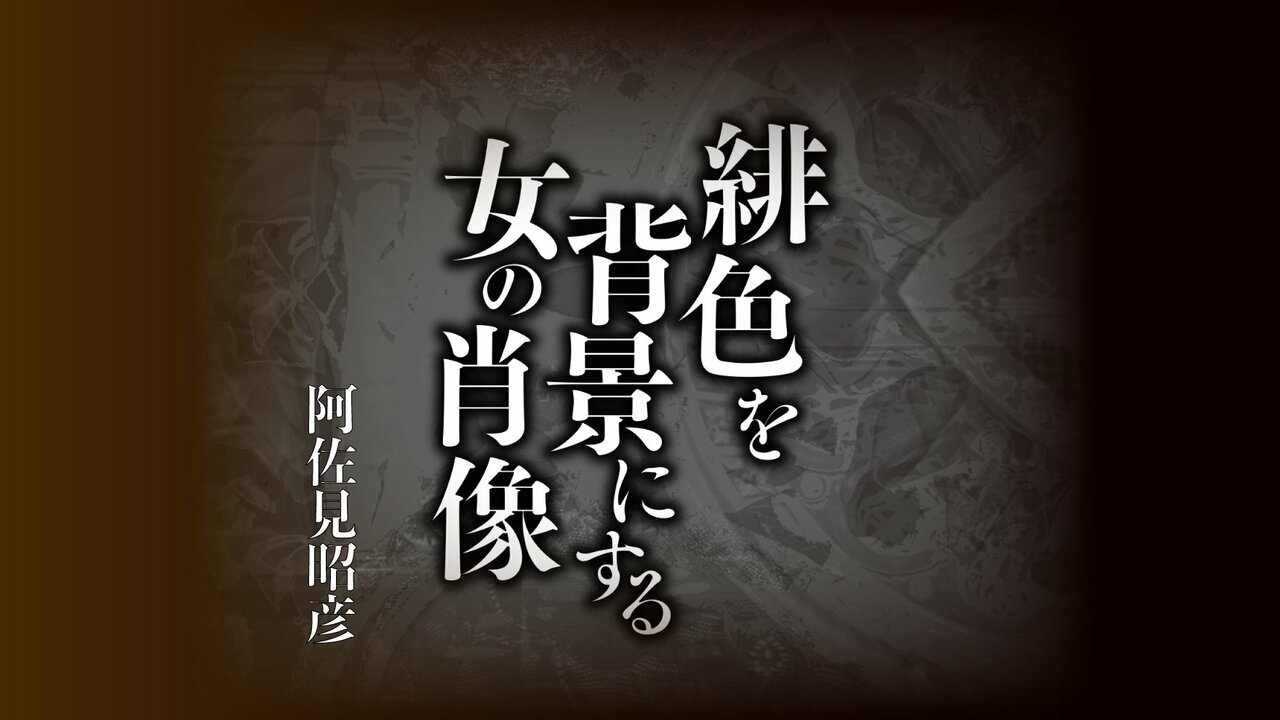3
「いやなに、たいしたものではございません。フェラーラの絵葉書でございます。ホテルにでもお帰りになったら開けて下さいな。何かのお役に立つかもね。ところで宗像さん。あなた、よほどフェラーラに惚れ込まれたようですな。その慧眼には敬意を表しますよ。四十年前の私と全く同じだ。いやいや、それはこちらのこと。
何かあればご連絡ください。先ほどの名刺のところにおりますから。毎月、本店に二週間、ロンドンとヴェネツィアに一週間ずつのローテーションです。今日はたまたまスタッフが外に出ておりますが、もうすぐ戻るはずです。フィリップを通してコンタクトしてくださいな。ええ、ここに書いておきましょう」
このような場合、いつもの宗像ならばその場で封筒を開けて中身を確認するはずだった。しかし、このときはまるで催眠術にかかったかのように、言われるがままに黄色い封筒を受け取り、そのままショルダー・バッグの中袋を開け、その奥深くへ仕舞い込んだのである。
コジモ・エステ氏とは話の通じてなさそうな部分がいくつかあったと思いながら、宗像は筒型のポスター・ケースを小脇に抱えて店を出た。時計を見ると十一時半である。いったんホテルに戻り、着替えてテート・モダンに向かえば、約束した時間にちょうど間に合う計算だった。
4
ホテルからセント・ジョンズ・ウッド駅まで歩き、地下鉄ジュビリー・ラインでサザークへは直通である。新しい駅のエスカレーターを乗り継いで外に出ると、間もなくその特徴溢れる雄姿をビルの谷間に現し始めた。
何しろ昔は巨大な火力発電所だった建物である。テート・モダン美術館は、その外観をほとんど昔のままに保存して内部を改装し、一九〇〇年以降に作られた現代美術を展示する、壮大な美術館として生まれ変わっていた。
おまけに、歴史、人物、静物、風景と、四つの展示部門からなる独自の展示コンセプトで、建築と同様に世界中の美術関係者から注目される存在になっていた。
心地とは、テート・モダンの売りの一つであるターバイン・ホールで待ち合わせることにしていた。
それは巨大な豪華客船がスッポリと収まってしまうような大空間だった。彼とは二年ぶりの再会である。左側のブック・ショップに沿いながら下りて行くと、残響感の強い大空間の中で、無数の反射音が入り混じりながら、定かではないが誰かを呼ぶ声が聞こえていた。
「おーい。む・な・か・た。宗像。ここだ。こ・こ・だ!」