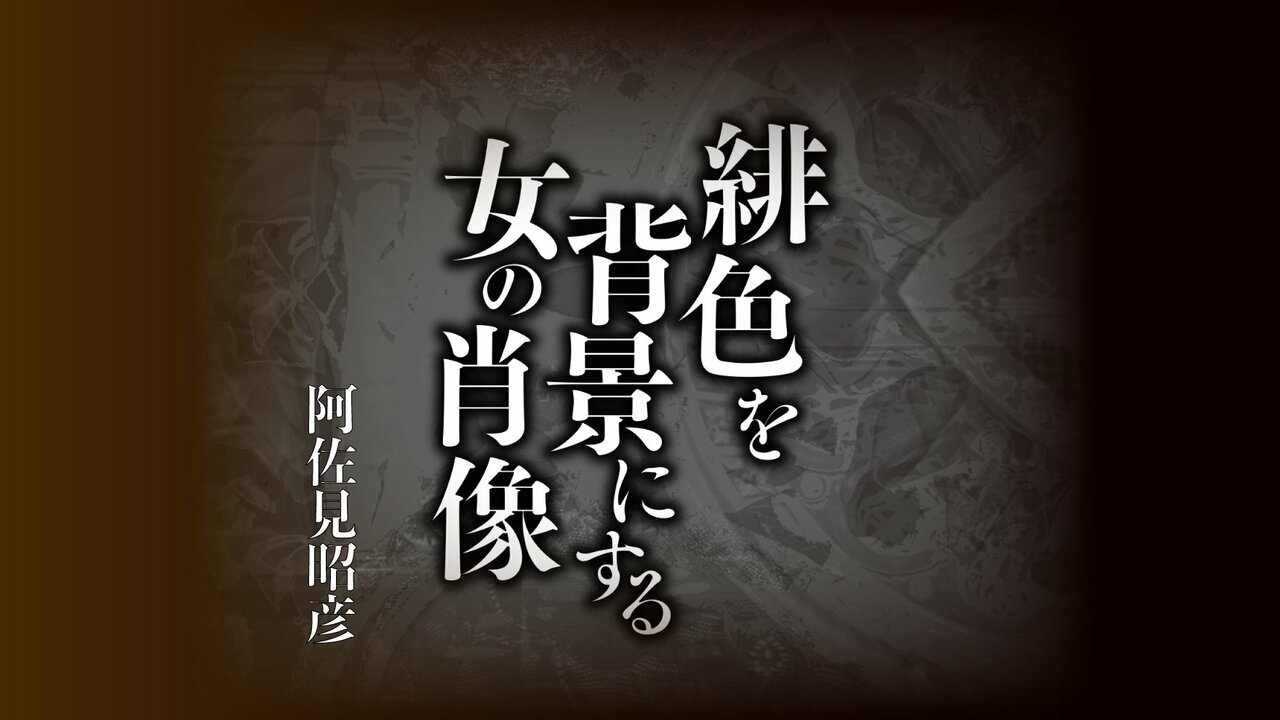邂逅─緋色を背景にする女の肖像
女史は机の右端に置かれた薄い木の箱を二人の前に差し示した。
縦三十センチメートル、横五十センチメートル、厚さ八センチメートルほどの木箱である。明るい木の表面にはニスが施され、真鍮製の小さい二枚の兆番と、二組の簡易なクレセントで施錠されていた。
「さあ開けてみろよ」
心地の急かす声に押され、クレセントを回転させて蓋を開くと、厚手の黒いベルベットで内張りされた中から、二つに折りたたんだ木の板が出てきた。
「パレットだ。フェラーラのものだそうだ」
心地は得意そうにそう言って箱からパレットを取り出した。裏返して見せると、そこにはピエトロ・フェラーラのサインと日付1969が書き込まれていた。
女史が言った。
「エジンバラ市がフェラーラの絵を買い上げたとき、彼がそのお礼として市に寄贈したものだそうです。ですから求めに応じて特別に彼のサインが入っているのです。現館長のウィックさんが若い頃、係としてその式典に立ち会っていたそうです。
授賞式の日、セレモニーの一つとしてその場でご本人に書き入れていただいたのです。三十年以上も美術館の倉庫で眠っていたこのパレットに描かれたサインと、画集にある絵に描かれたサインとを、私どもの鑑定室で照合しましたら、同一のサインであると認められました」
「このパレットに何があるのだ? 心地、もったいつけないで言ったらどうだ」
「まあ、あせるな。実はこのパレット……手に取って良く見ろ。少し変わっているとは思わないか?」
宗像がパレットを手に取り、そっと開くとかすかに古臭いテレピン油の臭いが鼻をついた。しかしあちこち見回したが何が特別のことなのか分からない。
「何だ? 分からんよ」
「ちゃんと手に持ってみろよ」
「こうか?」
「次は筆を持ってみろ。さあ、この万年筆を筆と思って……」
そう言いながら、心地は内ポケットから、やおら万年筆を取り出して宗像に差し出した。
「よし、こうか……? いや、これでは描けないぞ。左手に筆ではな。そうか、パレットを左手に持ち替えれば良いのか」
しかしパレットは宗像の左手にうまく収まらなかった。パレットに穿たれた、親指を入れる穴の位置が逆だったのだ。
「そうなんだ。このパレットは左利き用だ。だからな、フェラーラは左利きの画家ということが分かった」
「なに左利き? ちょっと待て、フェラーラは右利きだ。そら、これを見ろ」