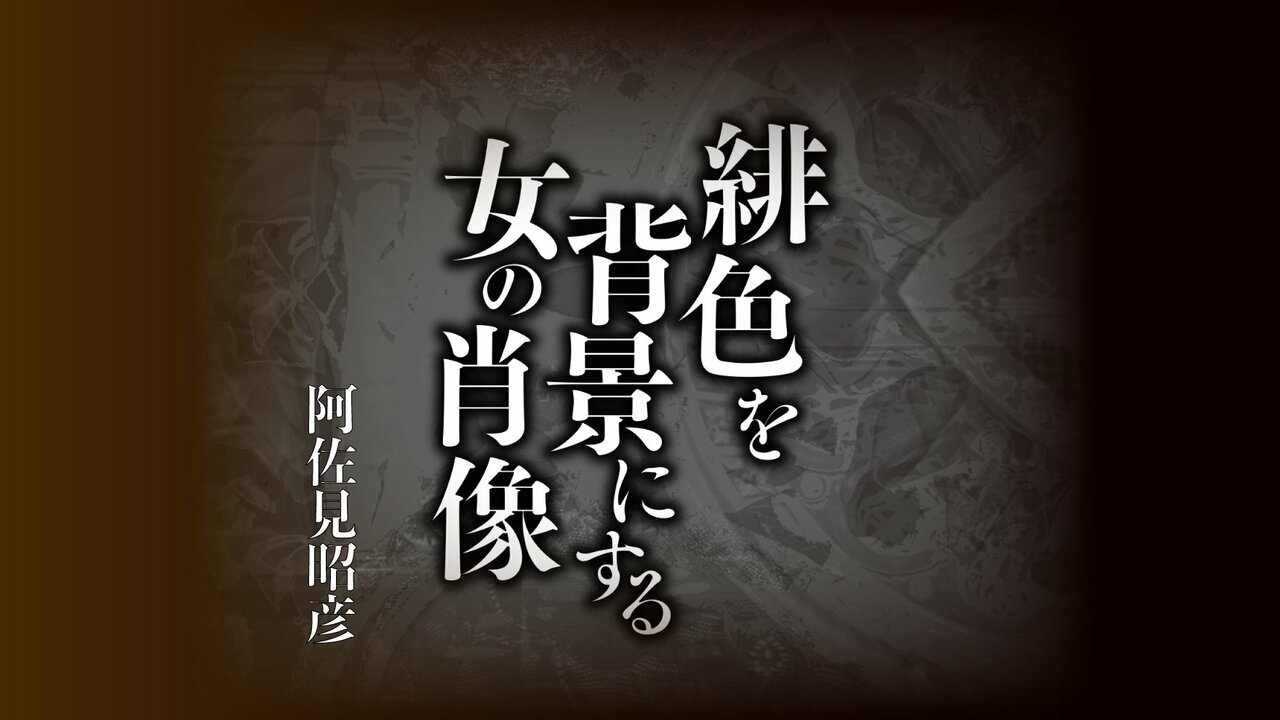邂逅─緋色を背景にする女の肖像
「美術界も大変狭い世界なのさ。ルッシュ国際現代美術館の副審査委員長に、あの超大物評論家のミッシェル・アンドレが就いていたんだ。おまけに彼、あの美術館の創設準備委員の責任者の一人として、中心になって展示コンセプトの組み立てをやってきた男だ。今回求められていることは、オーター氏の当選案に沿った大幅なコンセプトの見直しではないか。
と、いうことはアンドレがこれまで築き上げてきた考え方を否定することになるわけだ。これはロンドンのように保守的な社会の中では調和を乱す行為になる。特に美術界は現状の秩序を守ろうとする保守的な傾向が強い。無理矢理やれば、ロンドンの美術界から疎まれることになるからな」
「おいおい、心地ともあろうものがオーバーな」
宗像は呆れて言った。
「いや、これは少しもオーバーな話ではない。エリザベスさんがいるから言いにくいが、もしエドワード・ヴォーン氏が生きていればまず間違いないことだ。アンドレの後ろには常にヴォーン会長=ロイドがいたという図式は周知の事実だったからな。もっとも、うまく擦りあわせるような提案でもすれば、まあ波風は立つまいがね。でもそんなことはな」
黙って聞いていたエリザベスが心地の方を向いて毅然と言った。
「でも心地さん、あなたはアンドレさんの展示コンセプトを評価しておりますの? それに、あなたは、何も良いアイデアをお持ちではないと言うことですか?」
「えっ、エリザベスさん? ここでこんな話をして済みません」
二人の会話に突然侵入してきたエリザベスの言葉に心地は少しうろたえた。それに、日本語まで理解しているとは意外だった。宗像と心地は顔を見合わせた。
「本心ではどうなのかと聞いているのです。ロンドンで最近とみに評価の高まりつつある心地顕として……」
心地はエリザベスの顔をまじまじと見つめながら、一瞬言葉に詰まった。
「あなたがそう言う……。まあ……それは、真実、アンドレさんの展示コンセプトは少々古臭いと思いますよ。私は前からあのプロジェクトには興味を持っていて、いろいろ検討していたのは事実です。
ですから、オーター氏と言いましたかね、よくもあの斬新な案を一等に選んだものだと、実は驚いていたくらいなんです。審査委員長の磯原錬三が傑出していたと言うべきでしょうね。満場一致と聞いていますが、もし彼がいなければあの案は選ばれなかったかもしれません。それほど画期的な決定だった」
「それを聞いて安心しましたわ。心地さん、それでは思ったようにおやりになれば。父はもうおりませんし。それに恐らく、もう直ぐ私がロイドの責任者になるでしょうから、今後、アンドレさんとも距離を置くつもりです。社会はもっと多様な価値を求めているはずですわ」
堂々と主張するエリザベスに心地は少なからず驚かされた。隣に視線を移すと、宗像は目を大きく見開き、両手を左右に挙げて肩をすくめていた。