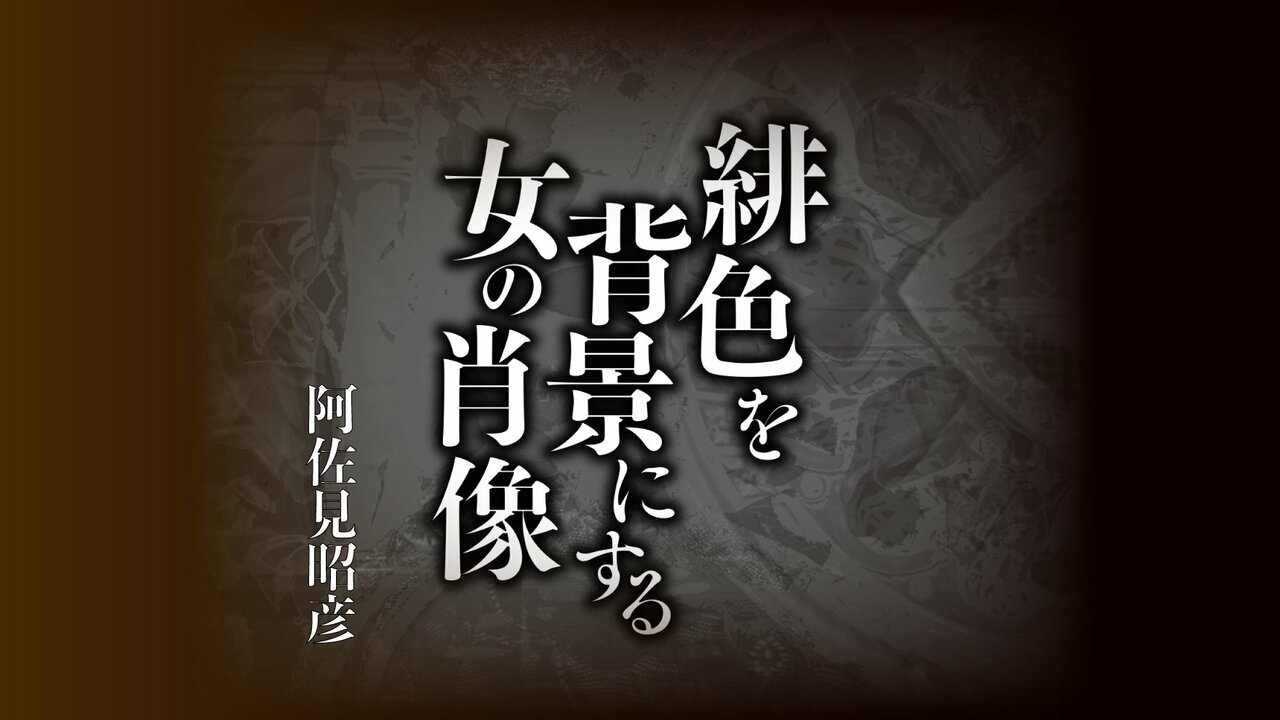3
新進気鋭と騒がれ、数々の賞を独り占めし、絶頂期にあった宗像が、突然周囲の期待を裏切って、それまでの夥しい仕事を減らして平易な気持ちで生きていく道を選んだことは、この理由と無関係ではなかった。
当時、納得できる仕事を厳選し、丁寧な仕事をする写真家という評価は、宗像に期待を寄せる周囲の人たちの温かい眼差しから出た気持ちの表れだった。
宗像はこうも考えた。テート・モダンで心地に会うのなら、この絵について尋ねてみよう。彼ならば何かが分かるだろう。たとえフェラーラが何者か分からずとも、また、彼がそれほど有名な画家ではなかったとしても、この絵はなかなか個性的だし、なによりも気に入っていた。
それに心地と批評し合うのも一興ではないか。しかしコジモ・エステと名乗るこの老人は、サインは裏側にあるというような、すぐばれる嘘をなぜついたのだろうか? 宗像はエステ氏に向き直って尋ねた。
「フェラーラの他の絵をお持ちですか?」
エステ氏は四号ほどの小さいものですがと言いながら、パステル画のプリントを持ち出してきた。やはりフェラーラの素描画だと言う。それは茶系統のコンテでサラッと描かれた、またもやあの美しい女の横顔である。
「それではこの絵をつけて五百ポンドにしてもらいたい」
宗像は新たな指し値をした。
「そ、それでは酷過ぎます。商売になりません。何とか五百五十ポンドで手を打ってはいただけませんかな?」
エステ氏は身をくねらせ、いかにも困ったという顔つきになって答えた。宗像は何が酷いものかと思いつつも、結局プリント二点がこの値段でまとまった。
「いやいや、まことに申し訳なかった。確か裏にサインがあったと記憶していたのだがね。はて、それでは別の絵だったかな? それで、というわけでもありませんが、お詫びのしるしに何か一つ……。いやなに、べつに大したものではありませんがね。ところで、あんた、確か、これからポルトガルに行くと言ってましたな?」