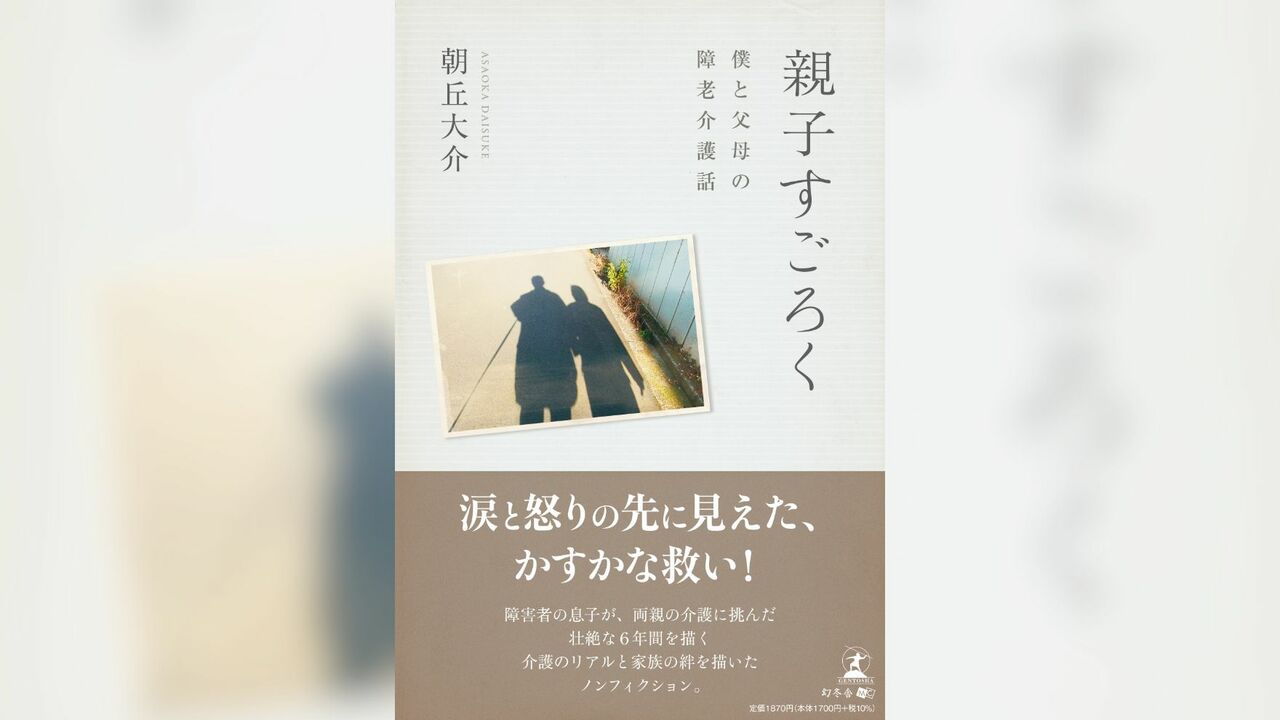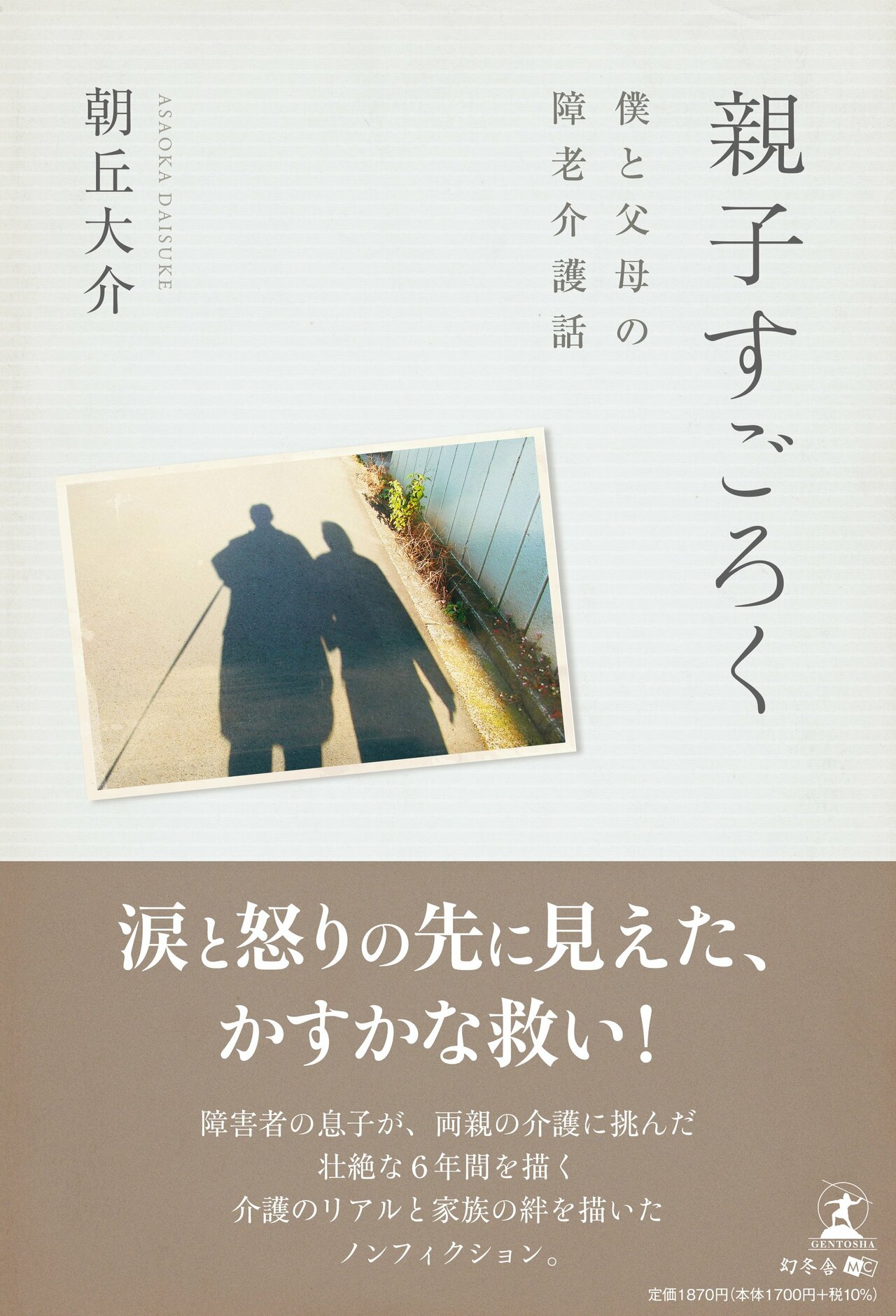【前回の記事を読む】父が肺がんを宣告された翌日、母はアルツハイマー型認知症で倒れた。交通事故による障がいを抱える私の過酷な介護生活とは…
私の神よ、どうか私を覚えて、いつくしんでください。
ネヘミヤ記十三章 三十一節より
第一部 父
肺がんの父×認知症の母×障がい者の僕
僕の愛犬クッキー(犬種はブレンハイムのキャバリア)が、三匹のトイプードルに歩みよられている。激しく詰(つ)めよられたまま、ニオイを嗅がれている。一対三ではどうにもならない。逃げ腰になるクッキー──無理もない。まだ生後五か月。散歩デビューして半月なのだ。
「いつもすみません」
「いえ。ありがとうございました」
飼い主同士、頭を下げ、その場を後にする。いま僕が進んでいる坂道の下を横切っているのは綱島(つなしま)街道だ。
うちは山の上の住宅街にある。僕はきょう、こうして介護の合間に束の間の散歩をしている。
ここから一キロ先に見える森の上にひっそりとたたずむのは、大倉山の中心的なシンボル。ギリシア神殿のような横浜市大倉山記念館だ。
障がい者である僕・池田はやとは、つねに自分に引け目を感じて生きている。
十二年前、交通事故で全身六か所の骨折と脳挫傷を負い、その後遺症で、注意の障がい、集中力の障がい、記憶の植えつけができない(これは軽度)、脳が疲れやすくて長時間の作業ができない、といった症状がでるようになった。
いわゆる高次脳機能障害である。脳が使えないということは、体が使えないということを意味する。脳が身体に指令を送るわけで、その脳が疲れてやられると体は動かなくなるのだ。
ぱっと見では、どこが障がい者なのかわからない。普通に手足が動くし、IQ、つまり理解力が保たれているせいだ。顔も普通である。
現在は、交通事故の慰謝料を取りくずしながら細々と暮らし、病気の両親の身のまわりの世話と家事をしている。食事作りとお掃除全般がわが家における僕の役割だ。掃除は単純な作業なので嫌いではない。
それに、家の中にいて親と向き合っている淡々とした毎日もなぜだか性(しょう)に合っていた。それでも集中力の障がいで、しばらくすると、脳に小石がいっぱいつめこまれたように、頭がずーんと重たくなってしまう。
元は五人家族だったが、兄のたーさんは実家から二駅離れた町で家庭を持ち、毎晩二十三時すぎまでサラリーマンとして働いていて、姉のゆっこは都内に家を持ち、先天性ミオパチーと言って、生まれつき骨格筋に障がいのある息子の介護をしている。時々実家に顔を出し、小一時間ほど話して帰る。