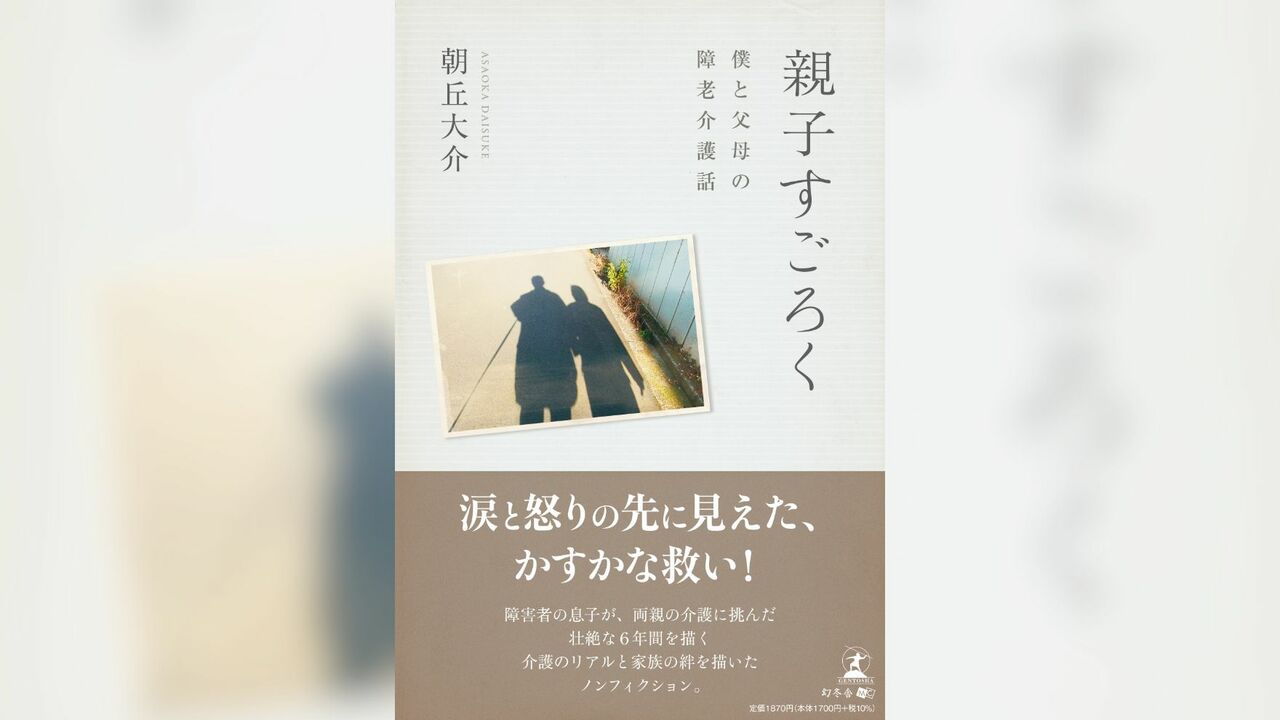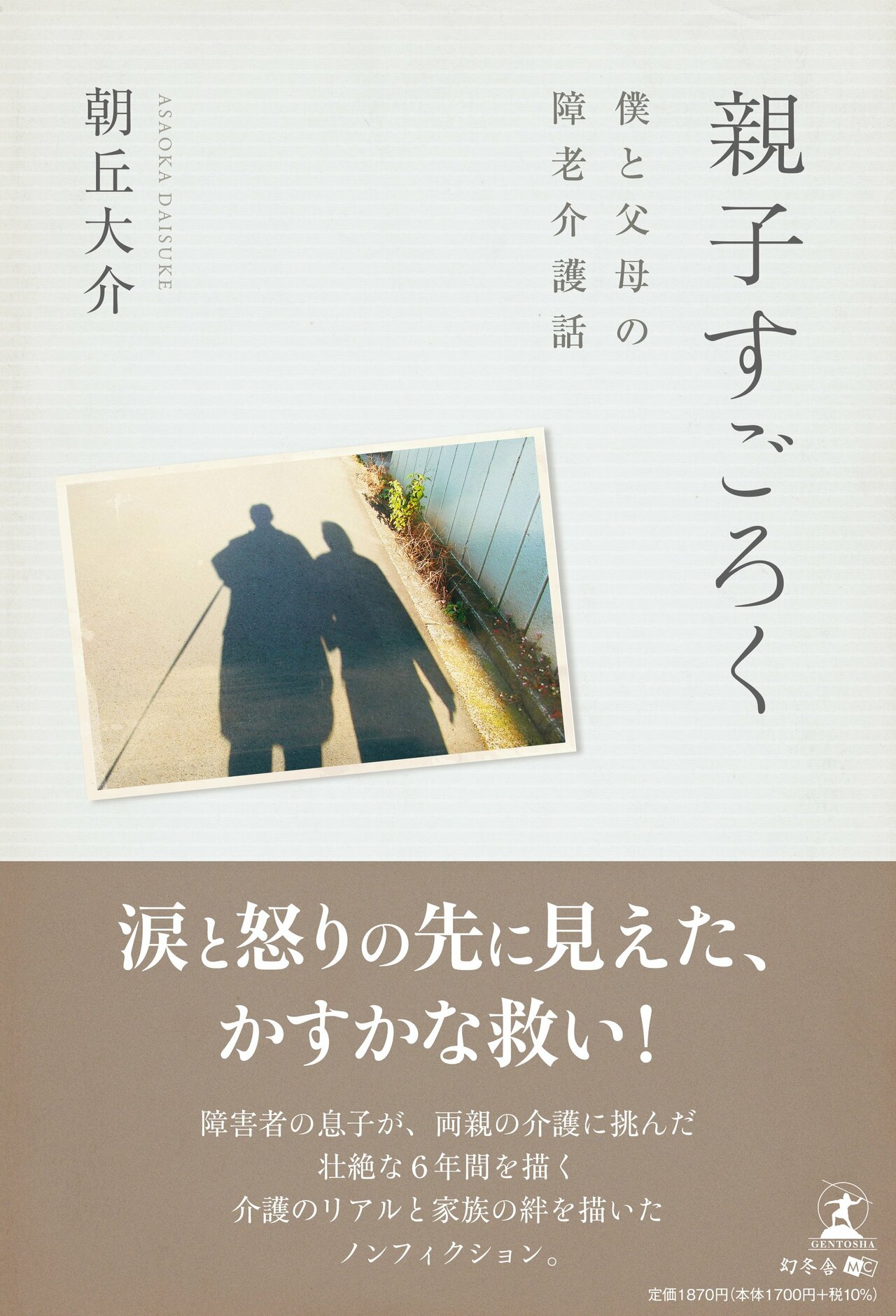はじめに
この物語はノンフィクションです。障がい者である私自身の人生と、病気を負った家族の歩み、その中で経験した「介護」の実態を、ありのままに綴(つづ)ったものです。
私は三人きょうだいの末っ子として育ちました。兄と姉はすでに家庭を持ち、実家では両親と私の三人暮らし。父は東大を出、大手企業で出世街道を驀進(ばくしん)した典型的な「昭和の家長」。母はそんな父を立てる「内助の功」の象徴のような存在でした。
そんな両親のもとで、私は幼いころから「いい子」でいなければと、親の顔色を窺(うかが)いながら育ちました。それは学校や社会に出ても、人の顔色を窺う悪癖となりました。
優秀な兄や姉とは対照的に、思春期の私は、進学校にいながらも成績はパッとしない、凡庸(ぼんよう)な少年でした。あるとき、同級生二人から駅の石柱に顔をぶつけられて鼻を骨折させられ、心にも深い傷を負いました。以来対人恐怖症になり、二十年間、人の目を見て話すことができず、気がつけば周囲から孤立し、自己肯定感まで失っていました。それでも夢だけは持ちつづけていました。いつか作家になりたい、という夢を。
二〇〇四年、旅先の旭川で交通事故に遭(あ)いました。夜、無灯火の車に撥(は)ねられ、全身六か所の骨折と脳挫傷─その結果、私は「高次脳機能障害」という後遺症を抱えることになりました。
高次脳機能障害は千人いれば千通りの症状がありますが、私の場合、脳の海馬はやられていないので、純粋な記憶障害ではないのですが、注意や集中力の障がいで記憶の植えつけが難しく、脳が疲れやすくて長時間の作業ができない、といった症状があります。
IQ(理解力)が保たれているため、障がいを受け入れるまで長い時間を要しました。長期におよぶリハビリ生活の中で、両親は以前よりも私に寄りそってくれるようになりました。一緒に映画を観て、会話をして、少年期以来なかった穏やかな時間を取りもどすことができたのです。私は、どこかで「この時間を大切にしよう」と思っていました。けれど、その時間は長く続きませんでした。