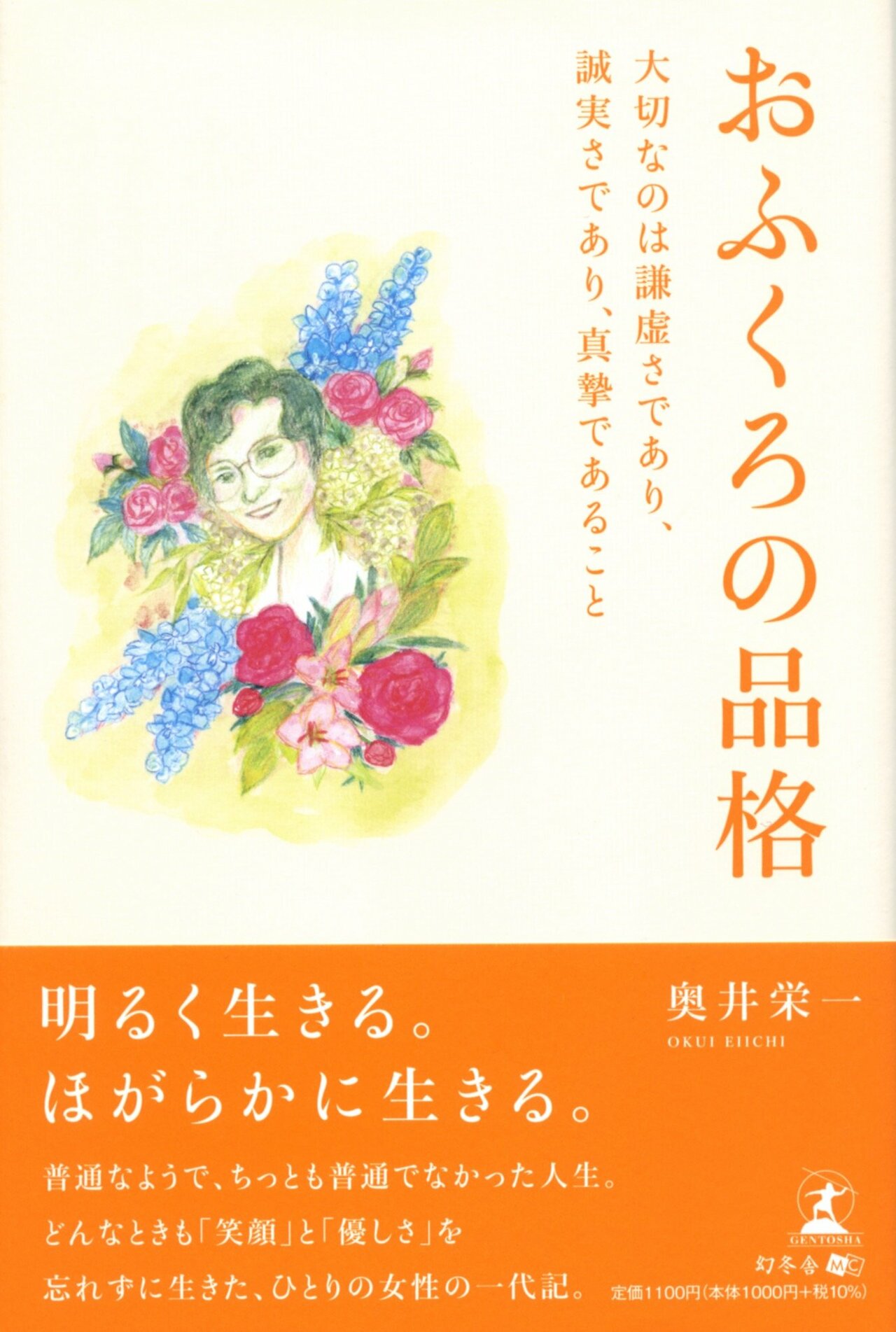第三章 土浦での新生活
食料難の時代
戦後の食糧難時代は、どこに行くにも「お米」を持って行かないといけない時代だった。明治時代に日本銀行ができて以来、紙幣や硬貨の時代になったというのに、まるで原始時代に逆戻りしたかのようだ。それほど、戦争の影響は重大だったのだろう。
ものの売り買いには物々交換が主流で、貨幣よりも「お米」が信頼される時代になってしまったのだ。
奥井家は、三百年以上前から土浦のこの地で生活していることが推察されるが、江戸時代に度々襲われた大水害・火災等により、その記録が紛失している。
奥井の住居が土浦城の大手門前にあることを考えると、このころから土浦で相当な資産があり、社会的に認められていた一族と考えられる※。
祖父の有一郎は長男の嫁を迎え、「家族にも親戚にもひもじい思いはさせない」と、四代前に養嗣子として奥井家に入った田中塚本家の農家に依頼、おふくろの実家の原家の食糧までも面倒を見た。また、当時は、健康保険制度ができる前で、支払いに困ったお客さんの芋、野菜での支払いを受けたようである。
※奥井勝二著『奥井家のルーツと先祖』(昭和六十年九月刊行)より。祖父・奥井有一郎の 七回忌に当たり編纂される。
土浦での新しい生活
親父の祖父である初代の有一郎は、茨城県北相馬郡の平沢家の人で、慶応四(一八六八)年に生まれ、明治二十八(一八九五)年に養嗣子として祖母のとみと結婚した。幼時より勉学に努め、北里柴三郎に師事したそうだ。
それから薬剤師となり薬局を開設し、薬剤師免許証第26号を取得した。茨城県最初の薬剤師であった。初代有一郎・とみの長女が、親父の母・志づであり、私の父方の祖母である。
明治二十九(一八九六)年五月四日生まれ。東京の普蓮土学園、明治薬学専門学校に学び、有一郎と同じく薬剤師となり、結婚して夫の英次郎(二代目有一郎)と共に薬局を開設した。