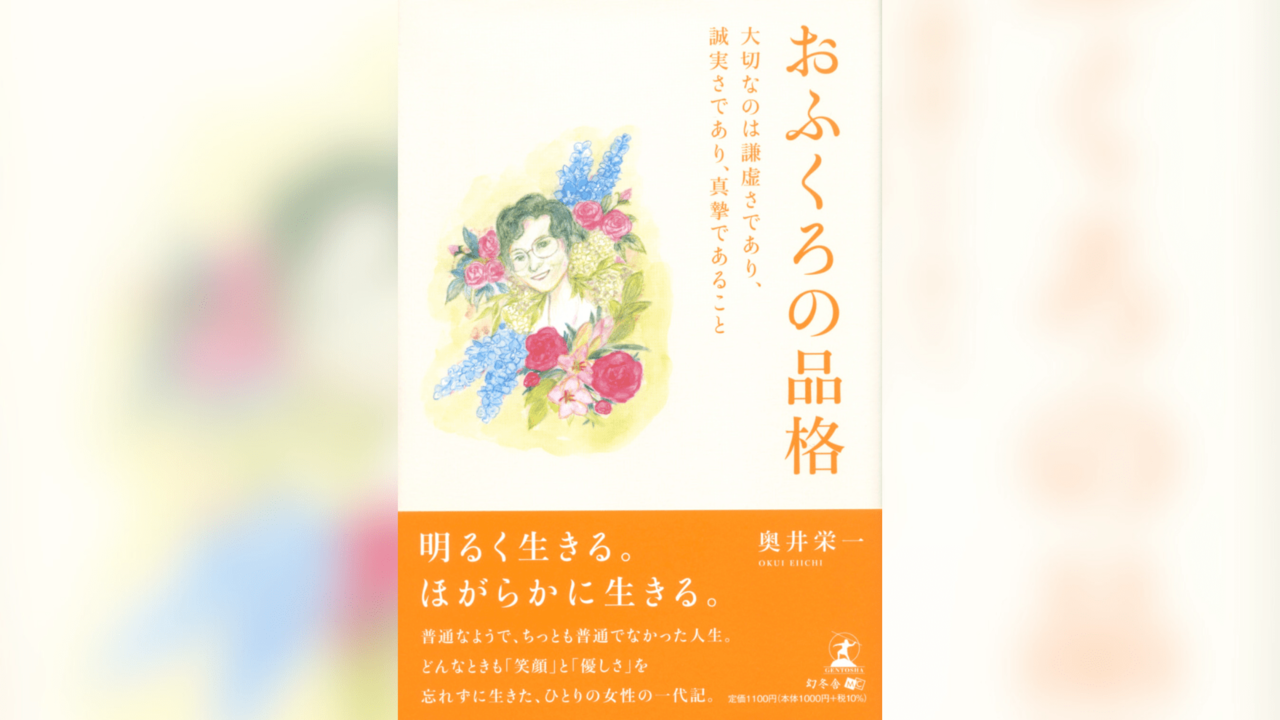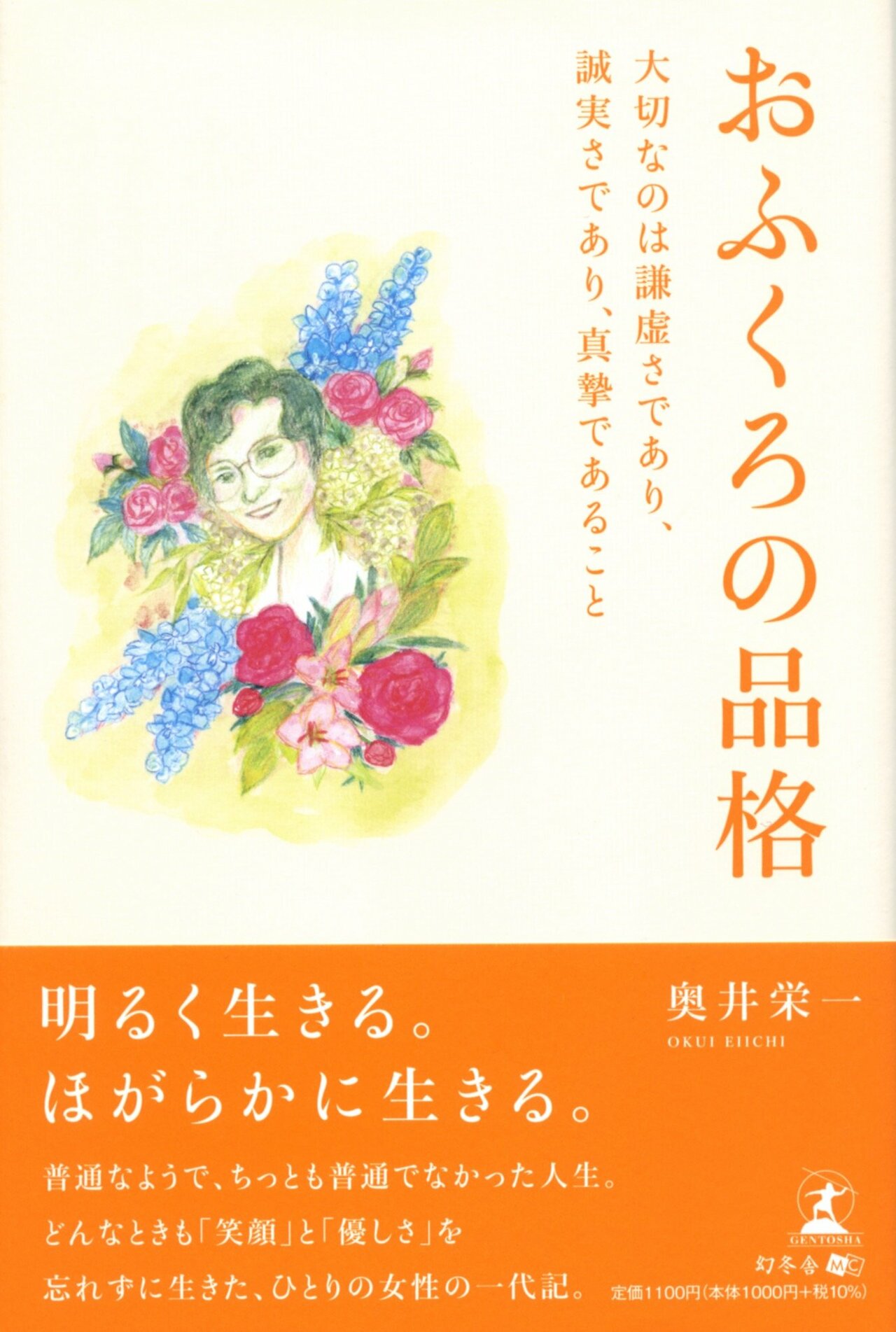【前回の記事を読む】宝塚歌劇団月組男役スターやバスケット部のイケメンにお熱だった女学生時代。おふくろはなかなかにミーハーだった
第二章 めぐり逢い
海軍療品廠(しょう)での出会い
昭和十六(一九四一)年一月、おふくろは十六歳を迎え、その年の暮れ十二月に太平洋戦争が始まった。
昭和十八(一九四三)年に入って戦局が不利になり、女性も「挺身隊」などと称して軍需工場に駆り出されていた。おふくろも昭和十九(一九四四)年一月に、海軍療品廠の研究部に任官された。
療品廠とは、医薬品・医療機器の製造を担当する海軍医務局所管の組織で、目黒にあった。海軍の将官の娘さんも多く、豊田連合艦隊司令長官のお嬢さんなどがいたという。研究部は、研究者が少なかったせいもあり、他の製造部とは全然雰囲気も違っていて、働き心地は満点だったそうだ。
昭和二十(一九四五)年一月の朝礼の席で、三人の海軍中尉が任官し紹介された。河合中尉、深井中尉、奥井中尉である。三人とも「イ」のつく中尉だったので、おふくろは印象に残ったという。
昭和十七(一九四二)年四月に旧制東京帝国大学医学部薬学科に入学した親父は、その後海軍軍医学校戸塚分校に入学、昭和十九年九月に旧制東京帝国大学医学部薬学科卒業、同時に海軍見習尉官となった。
そして海軍薬剤中尉に任官され、昭和二十(一九四五)年一月に第一海軍療品廠に配属になった。三人の海軍中尉の中でも親父は一番がっちりと身体が大きく、まるで少年のように赤い顔をしていた。
研究部に配属され、北側の小部屋で実験を始めた奥井部員(おふくろたちは上官のことをそう呼んだ)は、あまり器用ではないらしく、二十リットルの大きなコルベンをこわし、かしましい女性の話題になった。
大きな手がぷっくりとしもやけでふくらみ、同室の優しい女性はこれを見かねて、流しに山とたまった器具を、朝早く来てはきれいに洗ってあげた。
療品廠で一緒に働いていた多賀さんという方がいる。おふくろととても仲良しで、親父亡き後もお互いの家を訪ねては、療品廠時代の思い出話を夜遅くまでしていた。
その多賀さん曰く、「彼は、頭は良かったかもしれないけど、不器用だったのよね。とても見ていられない」──親父は、母性本能を揺さぶる才能を持っていたようである。優等生の親父と天然ボケ(?)のおふくろが、それまでの療品廠で共に過ごした日々をつうじて、お互いに意識し始めたことは、想像に難くない。
その年の三月十日、親父とおふくろが療品廠で働き始めてから二ヶ月も経たないうちに東京大空襲があったが、療品廠は焼け残った。しかし空襲はますます烈しくなり、研究部は富山の薬専の一部を借りて疎開することが決まった。実験道具を竹行李に詰めて、四月中旬に富山に移った。
移ってから間もなく奥井部員は本廠に呼び戻され、おふくろたち研究部の女性は、乏しい食料を寄せ集めて、おすしやすまし、酢の物などを作り、ささやかな送別会を開いた。「その時の、女性に囲まれて照れくさそうに歌を歌った姿が目に浮かぶ」──きっとこの時、親父はおふくろの心を掴(つか)んだのであろう。
普通であれば、親父が富山を離れて本廠に戻った時点で、親父とおふくろの縁は切れていたはずである。しかし、二人の縁を取り持ったのが上司の柳田少尉であった。
おふくろと親父が互いに惹かれあっていることを感じたのであろう柳田少尉は、「健康には問題のない男を紹介する」と、周おばあちゃんに親父を紹介した。後に親父が四十五歳という若さで死んだとき、周おばあちゃんは、「とびきり健康な若者を紹介すると言ったのに」と、恨み言を言ったという。