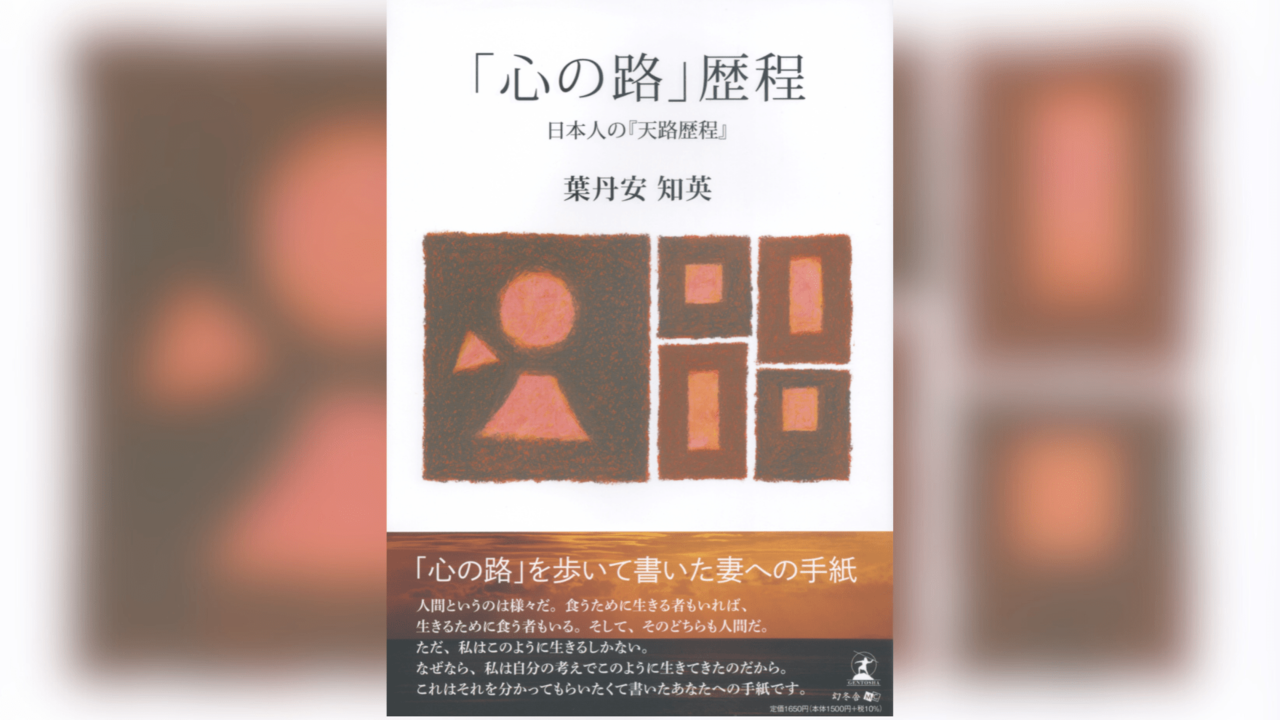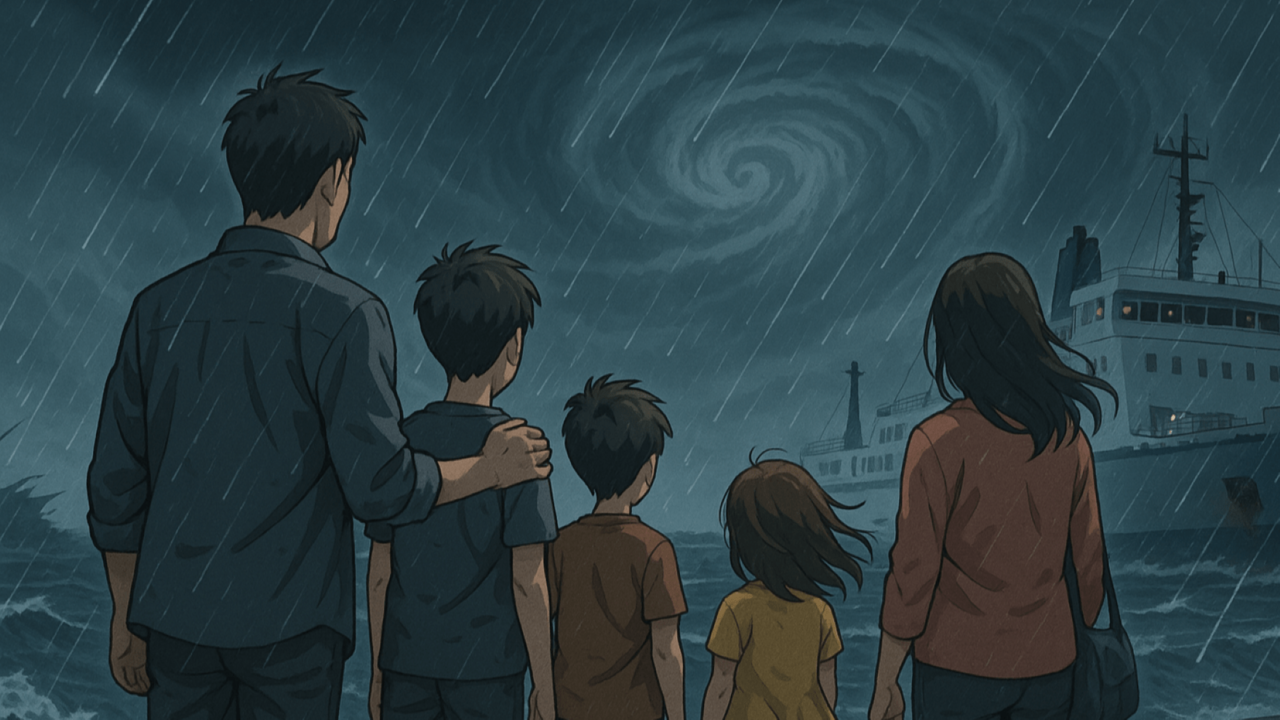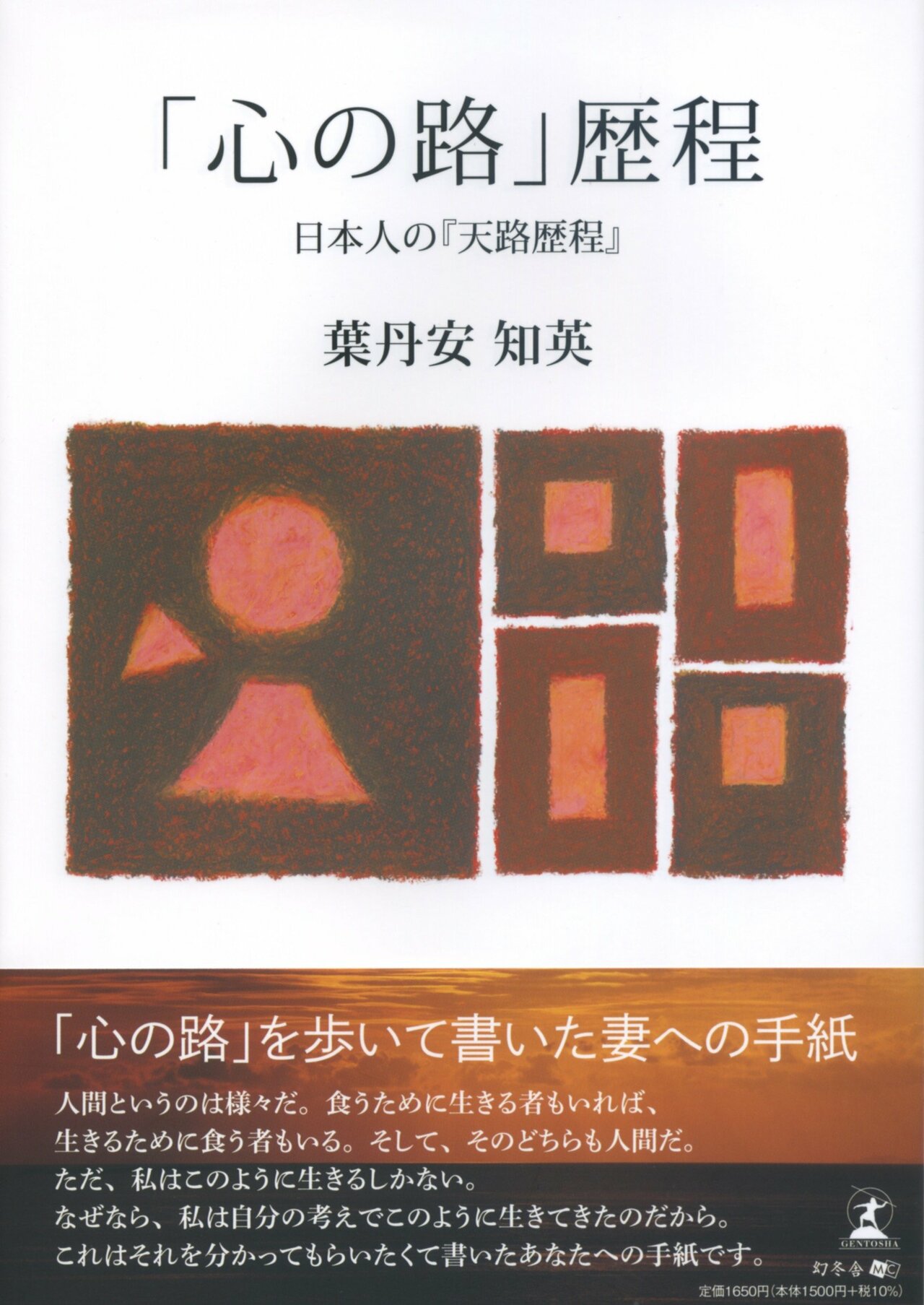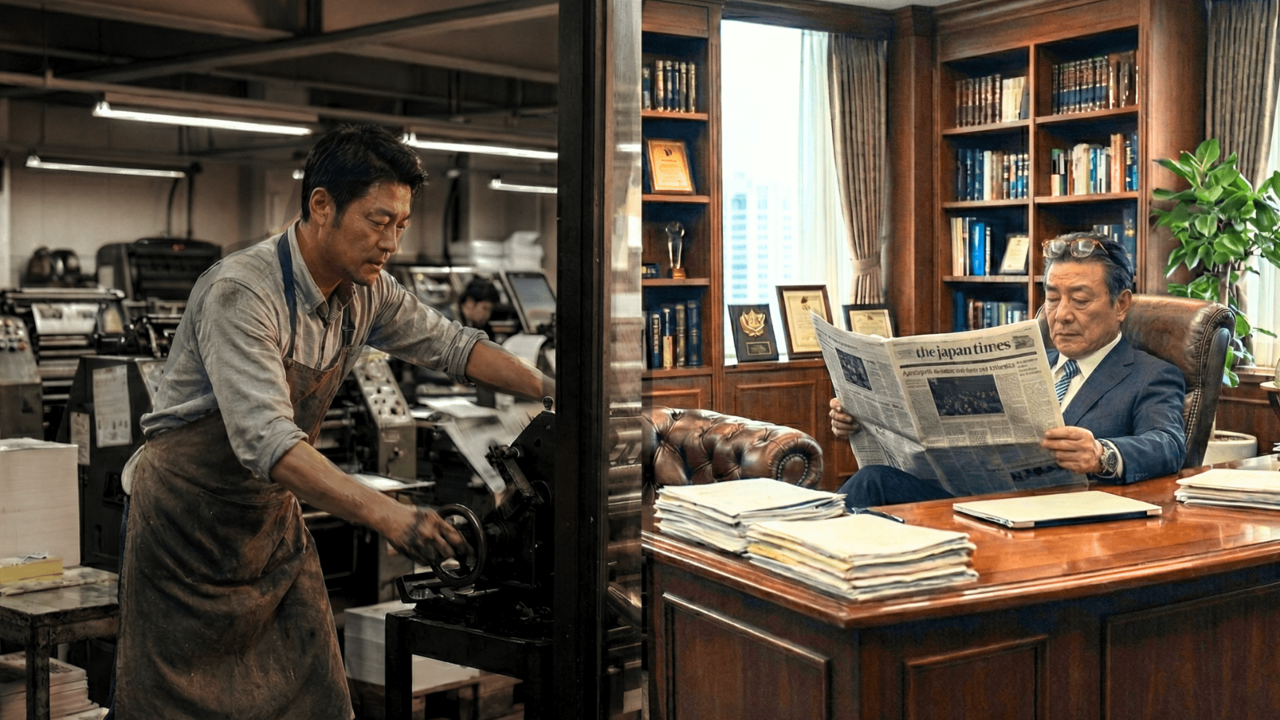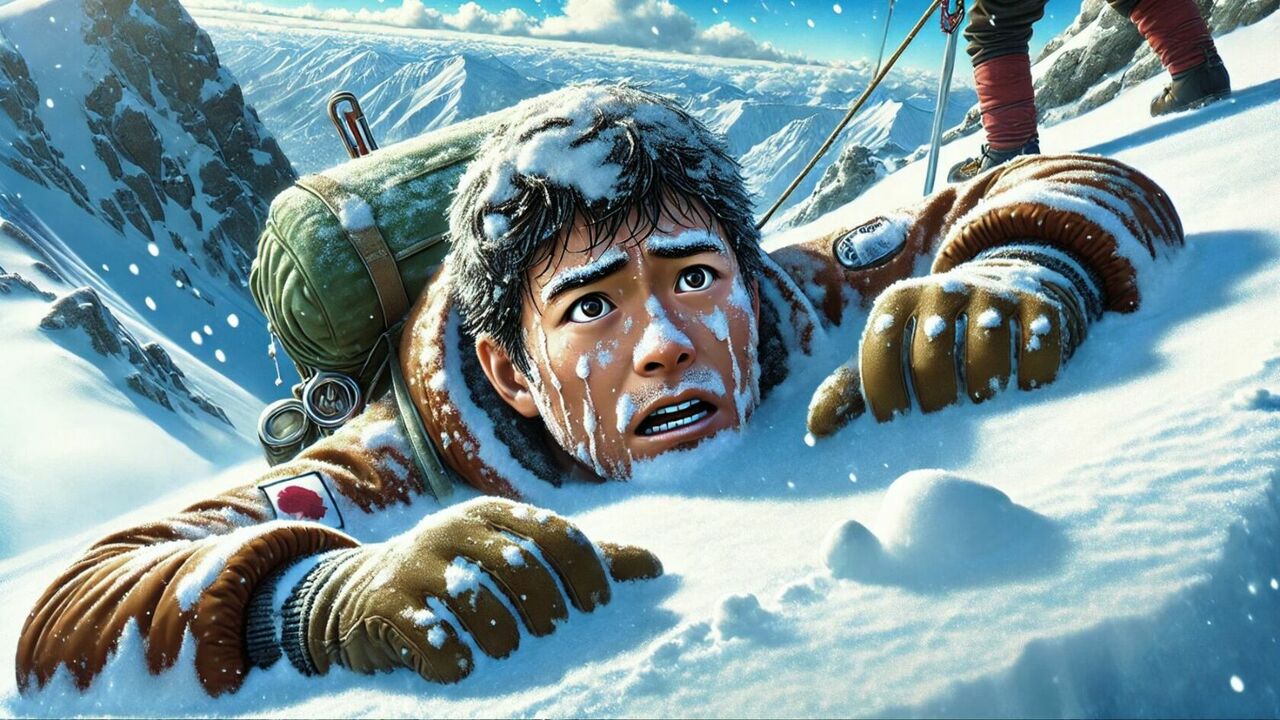【前回の記事を読む】心身ともに傷だらけの者たちは行き倒れるまで歩き続けるしかなかった。だがそれにより遍路は弱者・庶民の道として今日に残った
第一部
第一章 心の路
遍路の変遷と脱世間者
ところで私は、現象や信仰としての遍路の知識を深め、遍路研究者になりたいのではない。
世間の人たちが理解している遍路とはつくられた虚構だから、それをそのまま真に受けていては現代人としての批判的な自己反省の妨げとなることが、遍路関係の本を読んでみてよく分かったから、それを文章にして残しておこうと思って書いているので、それゆえ、自己反省にとって遍路を現象として捉える必要もないし、信仰の対象や精神的な価値のあるものとする謂れも全くない。
価値論を排して遍路を現象とみる書物の著者たちからすれば、私は何十万人ともいわれる年間遍路者数の一例であり、彼らが決めたカテゴリーのどこかに組み入れられる一人にすぎないが、彼らはそんなことをして一体なんになるのか。
現代人にとって遍路は、無信仰の結果地獄へ落ちるなどといった心理的抑圧もなく、追いはぎに出会う危険も少なく、自分の思いにしたがった物見遊山でよい。
ただ、途中のどこで行き倒れてもよいように墓標代わりの杖をもち、弔い料を懐にして死装束で歩くことが、脱世間した遍路者一般の心得なのかもしれない。と云うのは、『お四国』は殯(もがり)の四門に囲まれた墓であり、熊野の補陀落渡海の信仰が伝えられた水葬地の一つだからだ。
実際に行き倒れることになれば、そこの沿道住民には迷惑千万ではあっても、遍路者と沿道住民との間には、邊地順礼期以来の暗黙の約束事として阿吽の呼吸でつながれている「お接待」があると考えることができるからだ。
今日の遍路者一般は弘法大師信仰の表現者ではなく、むしろ弘法大師信仰に便乗し、宗教的外見に紛れて歩き、四国山海の風光を楽しみ、自分を慰撫して生き方を模索する、そうした観光と宗教が混じった旅人だといってよい。
遍路は札所寺やその元締めというべき高野山の側が経済的安定を図って、観光会社や近隣住民を取り込んででき上がった参詣誘引策の一つであって、宗教的観光商品となっていることは明白だからだ。
さて、人間界を二分して、食うために生きる世界を世間と云い、そこには「人間万事色と金」の「世間様」信仰がある。それに対して生きるために食う世界があり、そこでは人間はパンのみにて生くるにあらずという生活をせざるを得ず、そうした生活者を脱世間者と私は呼ぶ。
生きるために食う以上、ただ生きるのではなく、よく生きなければなるまい。
私もまた、自分の宗教的感情や欲求を遠い昔へと遡ることでよく生きたいという思いを胸に私流の「心の路」を歩きたい。心にある悲苦の元を知り、生きるために食う自律の歓びを知って、生きる勇気を獲得したい。自分がどんな存在者かを、現代の社会的歴史的位相において知りたい。
それができれば、あるいは脱世間の深淵から自分を掬いとって新たな自分を構築できるかもしれない。