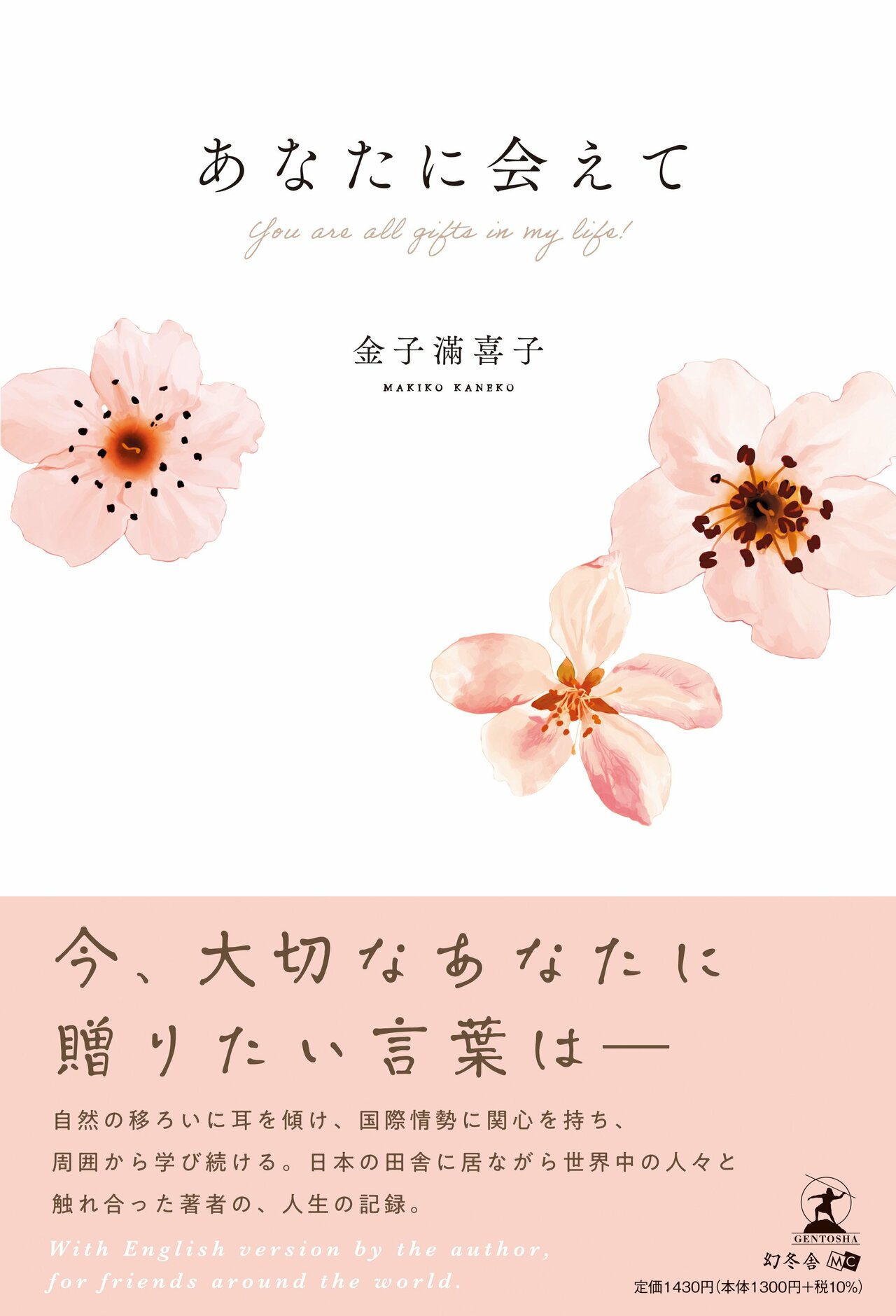中国への旅 1984年
高校生の時、本多勝一の『中国の旅』を読んで、日本軍の残虐な行為に大変な衝撃を受けました。又、大学で勉強した魯迅の著作や思想に感銘を受け、一度是非中国を訪問したいと思っていました。
1984年の秋に行われる広島県国語研究大会で、私が魯迅の『故郷』を題材に授業することになり、その前に是非中国をこの目で見たいと思いました。ちょうど折良く、広島県教職員組合三次地区支部が計画していた北京・南京・上海の旅に参加することができ、その年の8月に、紅い海かと見まがう長江を機上から見下ろしたのでした。
1984年の中国は現在とは違い、社会主義国そのもので、文革の後遺症もあり、大変な可能性とエネルギーを秘めながらどこに向かって進むのだろうという感じでした。
当時、中国では山口百恵の「赤いシリーズ」が大変な人気を博していて、日本人女性は皆彼女のように忍耐強く慎ましやかなのかと誤解されているようでした。日本語学習も盛んに行われ、若者達はエネルギーに満ち溢れていました。
朝、公園などを散歩していると、日本語で話しかけられることもありました。中国では、「天の半分は女性が支える」と言われ、女性が働くのは当たり前、家事も育児も男女で平等に行われるということを聞き、とても新鮮に感じました。朝、女性が朝食を準備している間に男性は子どもを連れて夕飯の買い物に行くのだそうです。
私達のお世話をしてくださったのは、公式な全国規模の労働組合連合である中華全国総工会で、北京では総工会の幹部から歓迎を受け、映画『ラストエンペラー』で有名な故宮や天壇公園を訪問し、月から見えると言われる万里の長城に登りました。何を見てもスケールが大きくて、百年単位で物事を考えるという中国の思想も、この国の長い歴史を知れば頷けるというものです。
南京は重慶や武漢と並び中国三大火炉と言われ、炎暑でしたがプラタナスの緑陰が美しい都市でした。夏休みでしたから、昼は学校の先生達とそれぞれの教育事情や取り組みについて交流し、夜は自動車工場で働く人達とダンスやゲームをして楽しみました。
辛亥革命の立役者、孫文の別荘やその陵墓である中山陵を訪れ、又、私を含む数人だけが魯迅の通った中学校に連れて行ってもらい、中の展示物を見ることができました。夏休みで学校は閉まっていたのですが、事情を話して特別に開けてもらったのです。