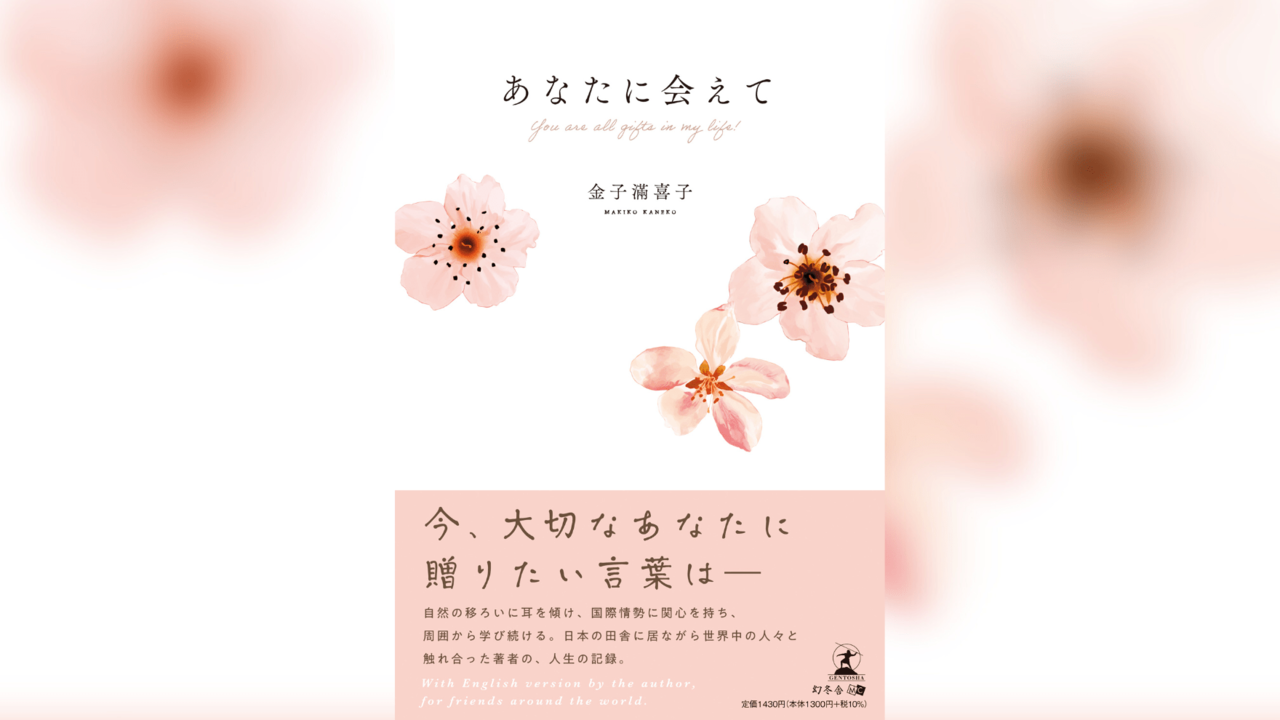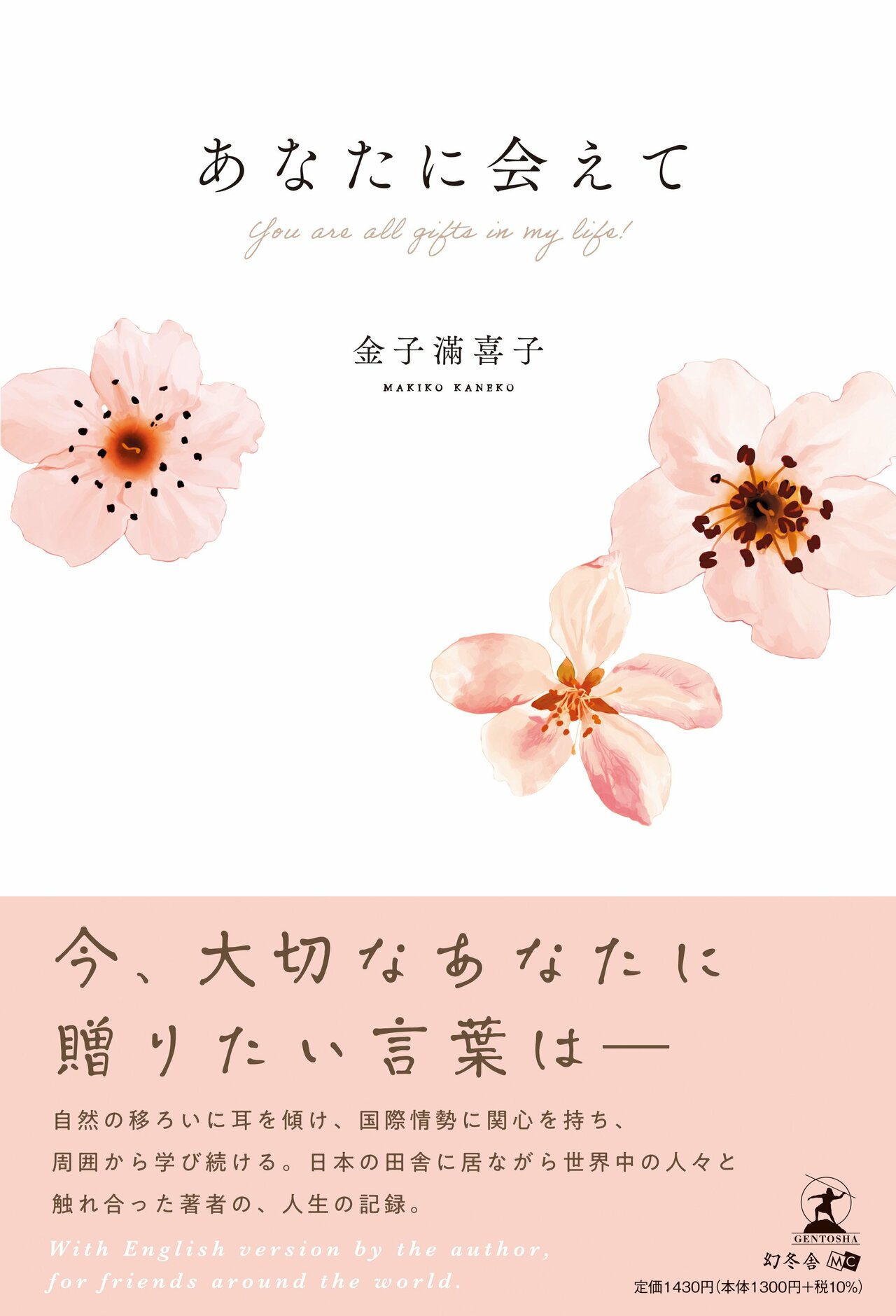【前回の記事を読む】コロナ禍をきっかけに綴られた心の遺産──田舎町での教師人生と懐かしき商店街の風景、孫に贈る"人との出会い"の記録
清少納言のように
秋は、日本の諺にもあるように「秋の日は釣瓶落とし」といって、日の暮れるのがどんどん早くなっていきます。仕事から帰る途中、家々に点る灯りが急に親しく感じられたりします。大気が引きしまり、木々の葉が赤や黄に色づく日本の秋は、最も美しい季節です。学生時代、友達と私はよくこの季節に京都や奈良の寺を巡り歩いたものです。
冬は、夜が面白いと思います。窓の外を見ると、冴え冴えとした寒空に月や星が煌々と光って、地面を照らしているのです。木々の間に光っているのは何でしょうか。目を凝らすとそれは、木々にぶら下がっている氷柱が月の光を反射しているのです。この雰囲気はまさに冬の饗宴といえるでしょう。窓には驚きの氷紋ができて素晴らしく美しいのです。
七年(とせ)を 辿りし道の 山桜
朝光(あさかげ)に映え 我を迎えし
蜩の 鳴く夕まぐれ 部屋にいて
彼岸と此岸を さまよいている
春に
春分の日は七日間のお彼岸の中間にあたる特別な日ですから、日本人は「彼岸の中日」と呼び先祖の冥福を祈るためにお墓参りをします。
日本のお坊さんは大抵、檀家の家々を訪れ、短いお経をあげてお布施を受け取るとスクーターか車に乗って帰っていきます。この日は町の中を走り回るお坊さんの姿をよく見かけます。
日本の諺に「暑さ寒さも彼岸まで」というのがありますが、「これは暑さも寒さも秋と春のお彼岸までのことで、それを過ぎると、涼しくなったり、暖かくなる」という意味です。しかしながら、春分については別の諺「彼岸過ぎて七雪」もあり、春分を過ぎても七回雪が降るというのです。
この二つの諺通り、春分を過ぎると徐々に暖かくなっていきますが、それとは反対に、春分を過ぎてもすごく寒い日があり、4月に雪が降ることもあります。そんなに沢山ではなくすぐに消えますが。だから、この諺は二つとも本当なのです。
桜の花が満開を迎える4月でも、このような寒い日があり、私たちは「花冷え」と呼んでいます。そして、満開の桜の花の下で震えながら花見と称する宴会を開くのです。たとえ震えていても、桜の花の美しさは格別なものです。夜、ライトアップされた夜桜は息を呑むほどの美しさです。
かつて庄原市にある上野公園の桜の下で送別会をしたことがありますが、その時の夜桜には、人の気持ちを狂おしくする妖艶な美しさがありました。