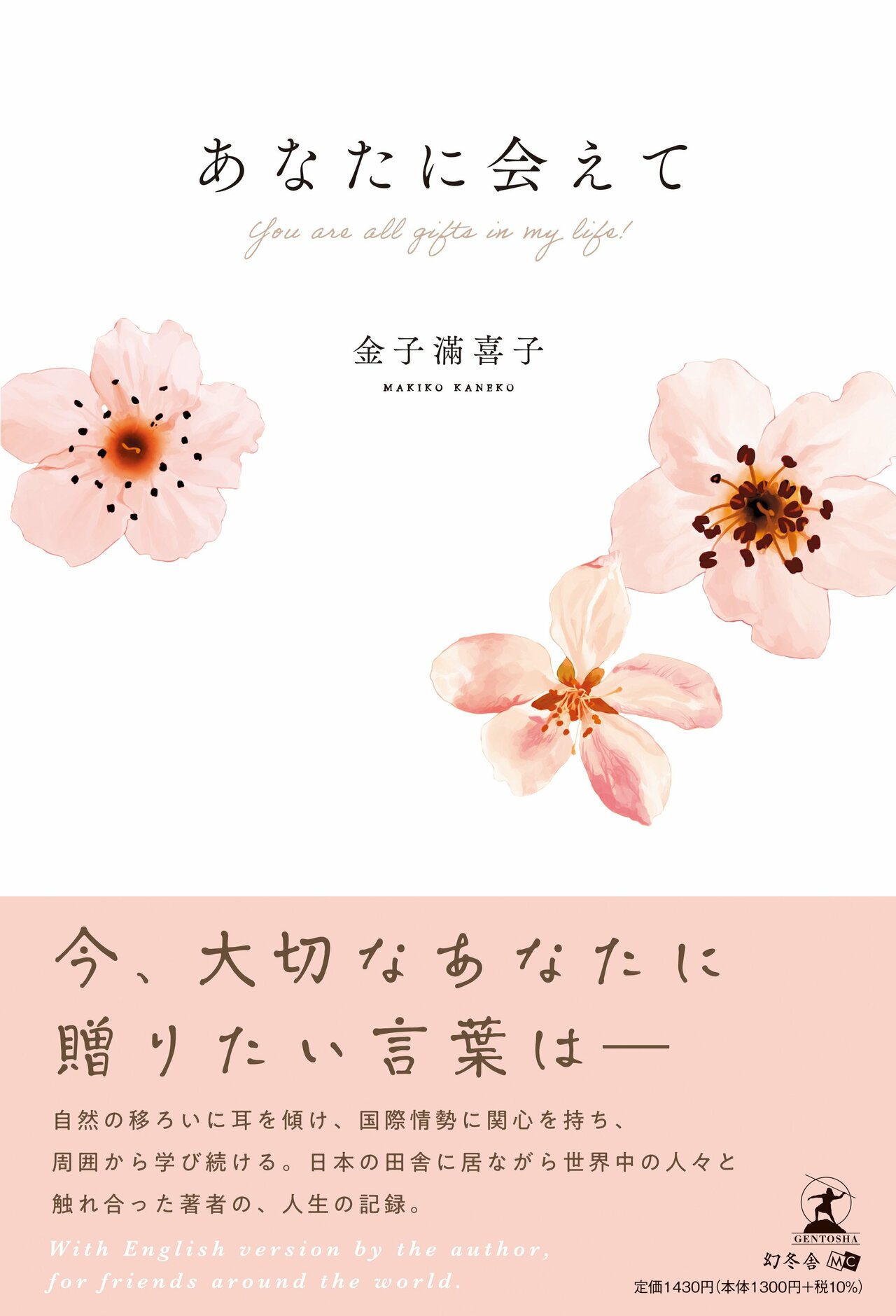私は京都市の北西にある仁和寺の桜も忘れることができません。一度、大学に通う途中にこのお寺に立ち寄りました。このお寺は桜の名所としても有名なので、春は特にいつも多くの観光客で賑わっていましたが、その日は何故かいつもより人が少なく、おかげで私は長閑な境内で一人、桜の美しさに浸ることができました。
古来、桜は他の花よりも多く短歌の中に詠まれてきました。有名な歌に「久方の光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ」があり、「こんなに日の光がのどかに射している春の日に何故桜の花は、落ち着きなく散るのだろうか」というような意味です。
短歌は伝統的な日本の歌で、31音節の文字で構成されています。花と言えば桜のことで、日本人の精神の不可欠な部分になっています。思うに、日本人がこれほどまでに桜を愛でる気持ちは仏教の教えである「無常観」と関係があるのではないかと想像します。日本人は優雅に散る桜の美しさが好きなのかもしれません。
私の実家の裏にある高等学校にもたくさんの桜の木があります。一度、その木々から桜の花びらが一斉に舞い散るのを見ました。それは春に降る雪のようでもありました。極楽の風景もこんなものでしょうか。
大学時代のサークル活動
疲れる受験勉強を経て、1976年私は京都にある立命館大学に入学しました。長いこと楽器の演奏に憧れていましたから、大学に入ったら吹奏楽部に入ろうと決めていました。
入部のお願いをするために吹奏楽部を訪ねると、部長は心配そうな面持ちで、この部は演奏活動だけをするのではなく、応援団と一緒に大学の応援活動をするのだと話してくれました。
といっても、楽器の初心者であった私に大学のオーケストラの門をたたく勇気はありませんでした。オーケストラの人達は、はるかにプロっぽかったのですから。結局、私は来る日も来る日も狭いリハーサル室の壁に向かって、クラリネットの練習をすることになりました。部員は約50人で、火曜日を除いた放課後の5時から7時まで練習しました。
火曜日は普段より早く集まって、5時前には練習を終えました。私達はよく隣の御所に出かけて行って、そこのグランドで野球をしました。クラリネットの練習は大変だったので、これは良い気晴らしになりとても楽しみでした。私はよくピッチャーをやり、打っても大抵塁に出ていましたね。