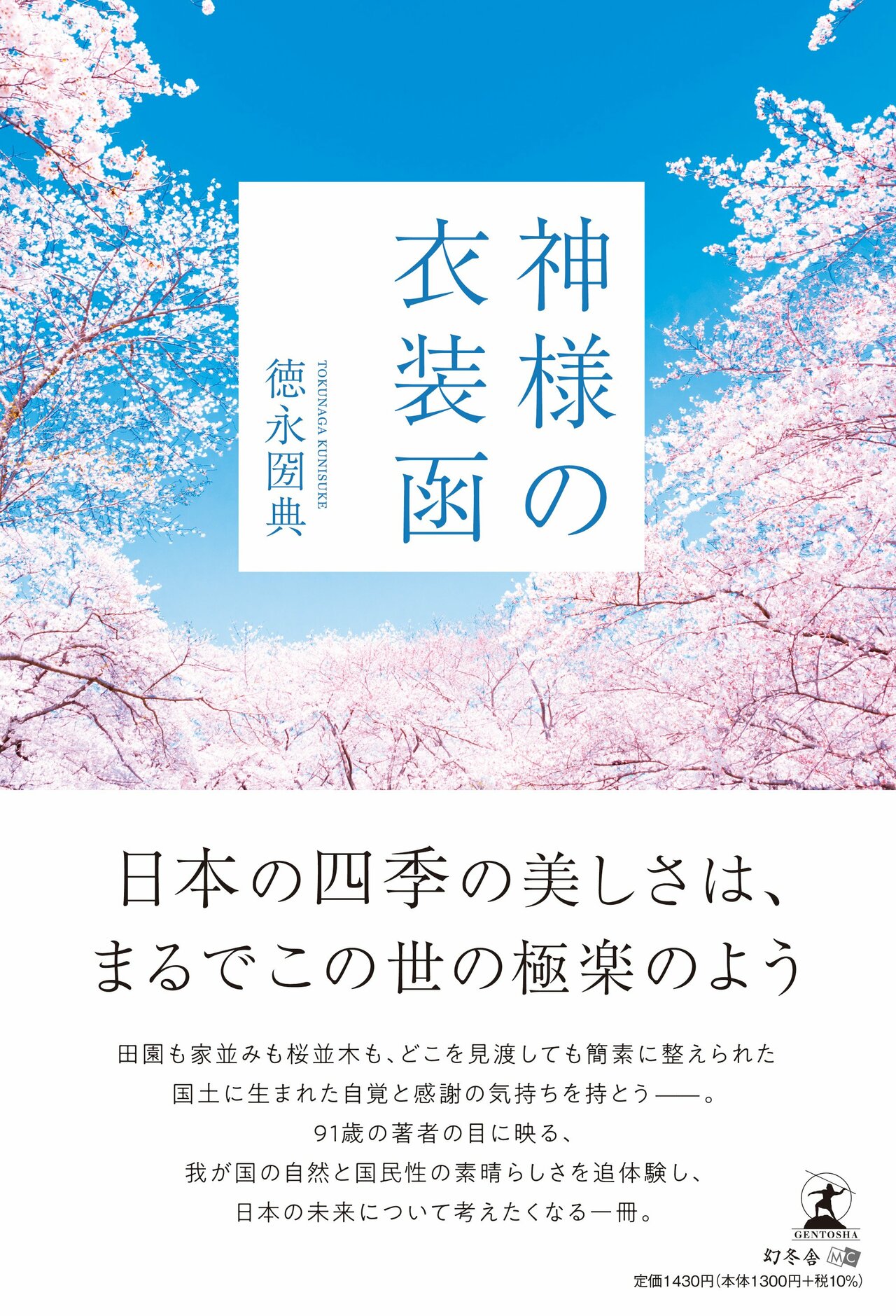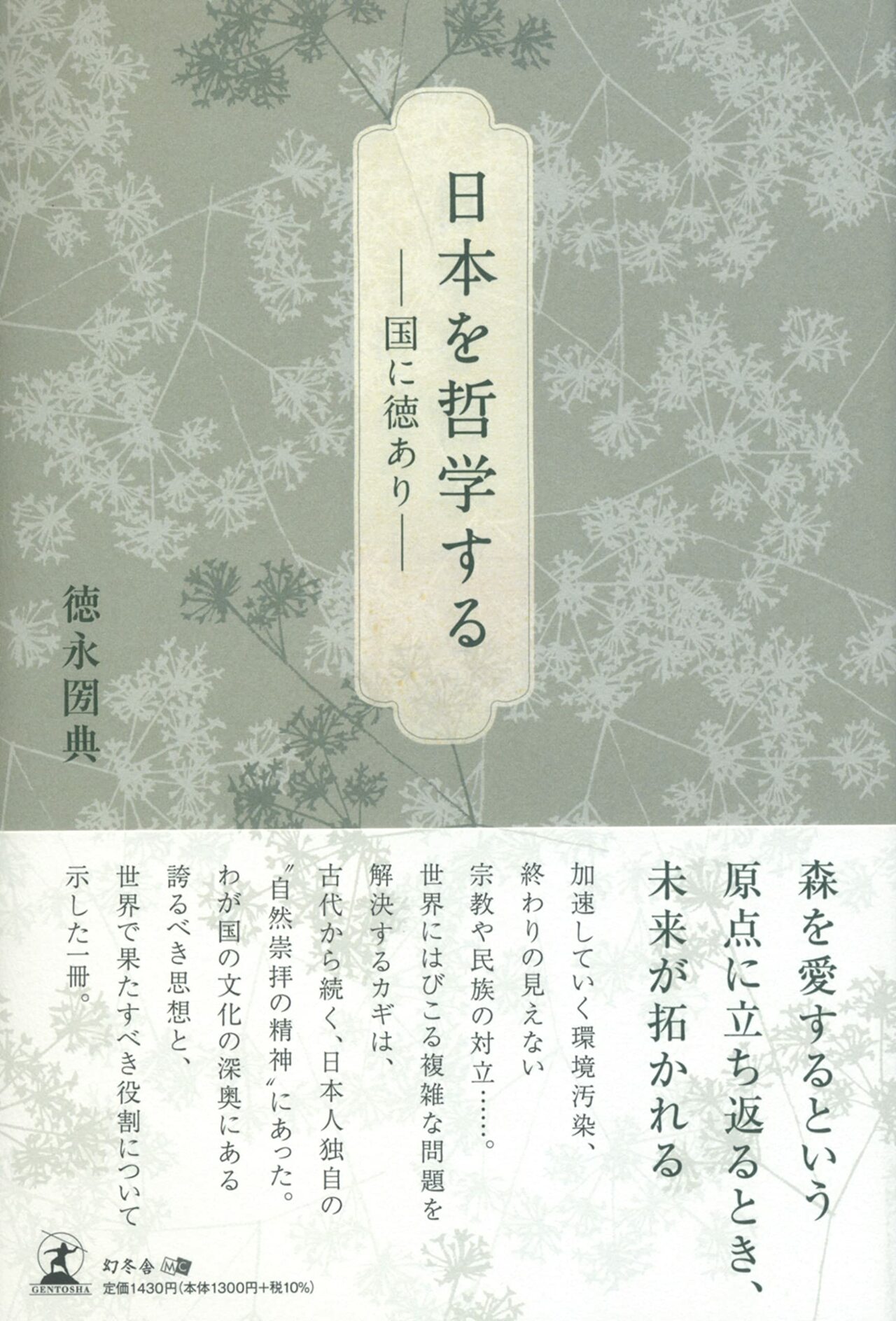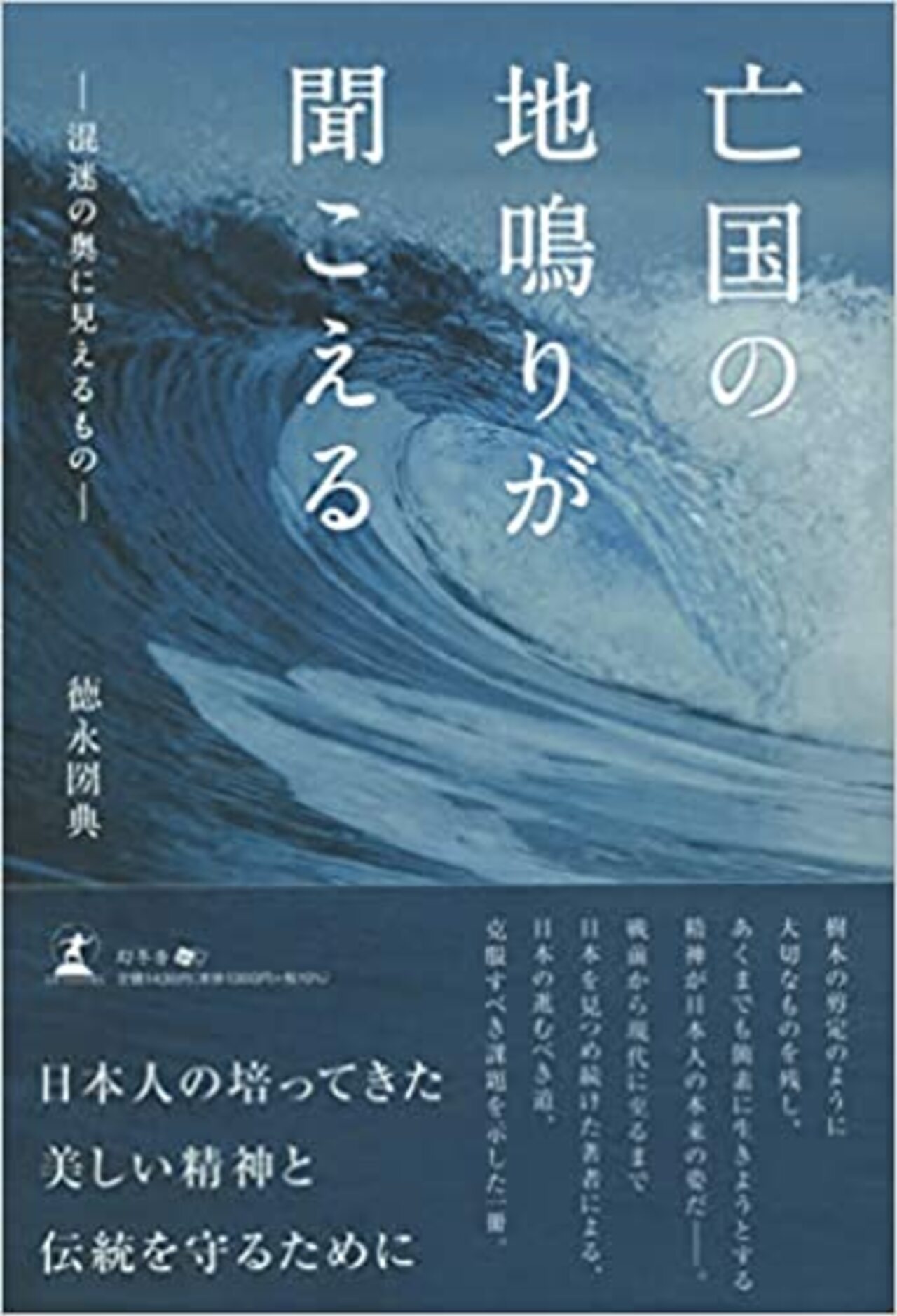そのホトトギスの声だが子供の頃に用瀬の裏山で聞いて以来久しく聞くことがなかった。ところが、思いもかけず聞いたのは一昨年の夏のことであった。大和の奥は吉野と境を接する竜門岳で聞くことができた。
吉野から急な山を登り、神武天皇伝承のある女坂峠に向かって縦走する途中、室生寺を襲った台風で、なぎ倒された倒木の散乱する明るい傾斜地で休んでいた時、尾根筋から突然、キョ、キョ、キョと鋭い声が空に響いた。「あっ、ホトトギスだ」と思った途端早くも山裾に姿を隠してしまった。関西では中々聞けないだけに、暫く興奮が覚めやらなかった。
それにしても、カッコウと鳴くから郭公と名づけられたことは分かるがホトトギスと呼ぶのはなぜであろう。漢字が入る前から、この鳥はホトトギスと呼ばれていたらしいが、なんと雅やかな名前であろう。
鳥の名前にしても、花の名前にしても、日本人の詩的な感性が日本語に滲みでている。一つの花にしても鳥にしても、漢字表現は幾つも変化する。郭公も呼子や、換呼鳥から閑古鳥と詩的に使い分ける知恵も、他国には見られない日本語独特の情緒的な表現である。
古稀を迎えたこの歳になり、日本語は美しいなあ、とつくづく思う。京の都の歌詠みはその声を珍しがってホトトギスの初音を聞きに連れ立って山深く入る物好きもいたという。
されば、私も今年は初夏の頃、友を誘い竜門岳でホトトギスの声をもう一度聞いてみたいと思う心や切である。その時は、ホトトギスよ、いつか聞かせてくれた声をもう一度、私に聞かせておくれ。
五 思いつくままに 平成10年12月2日 日本海新聞 潮流
はやきもの
それは水の流れ、百代の過客、光陰などと書き連ねると大層な調べとなるが還暦と共に一市井人となりて過ぎ去りしここ七年は矢の如しであった。この間敬愛してやまないまだ若いといえる知人友人の死をただ呆然と然し厳粛に受けとめた。
悠々たるかな宇宙のことなどと思いを馳せていても天地自然の創造進化の必然は一刻の休みもなく粛粛と行われている。人の生死の後先などはつかの間のことなのであろう。
【イチオシ記事】彼と一緒にお風呂に入って、そしていつもよりも早く寝室へ。それはそれは、いつもとはまた違う愛し方をしてくれて…
【注目記事】(お母さん!助けて!お母さん…)―小学5年生の私と、兄妹のように仲良しだったはずの男の子。部屋で遊んでいたら突然、体を…