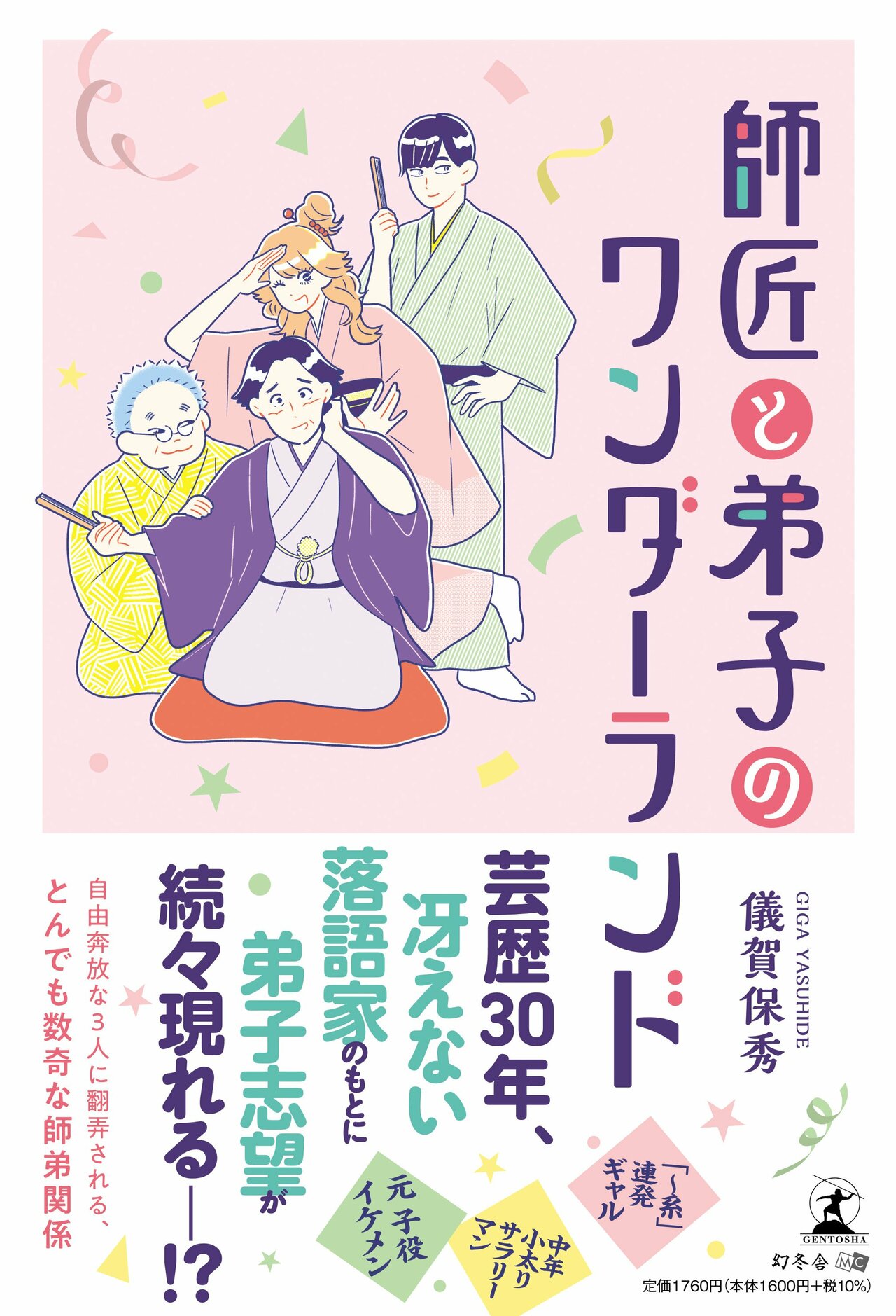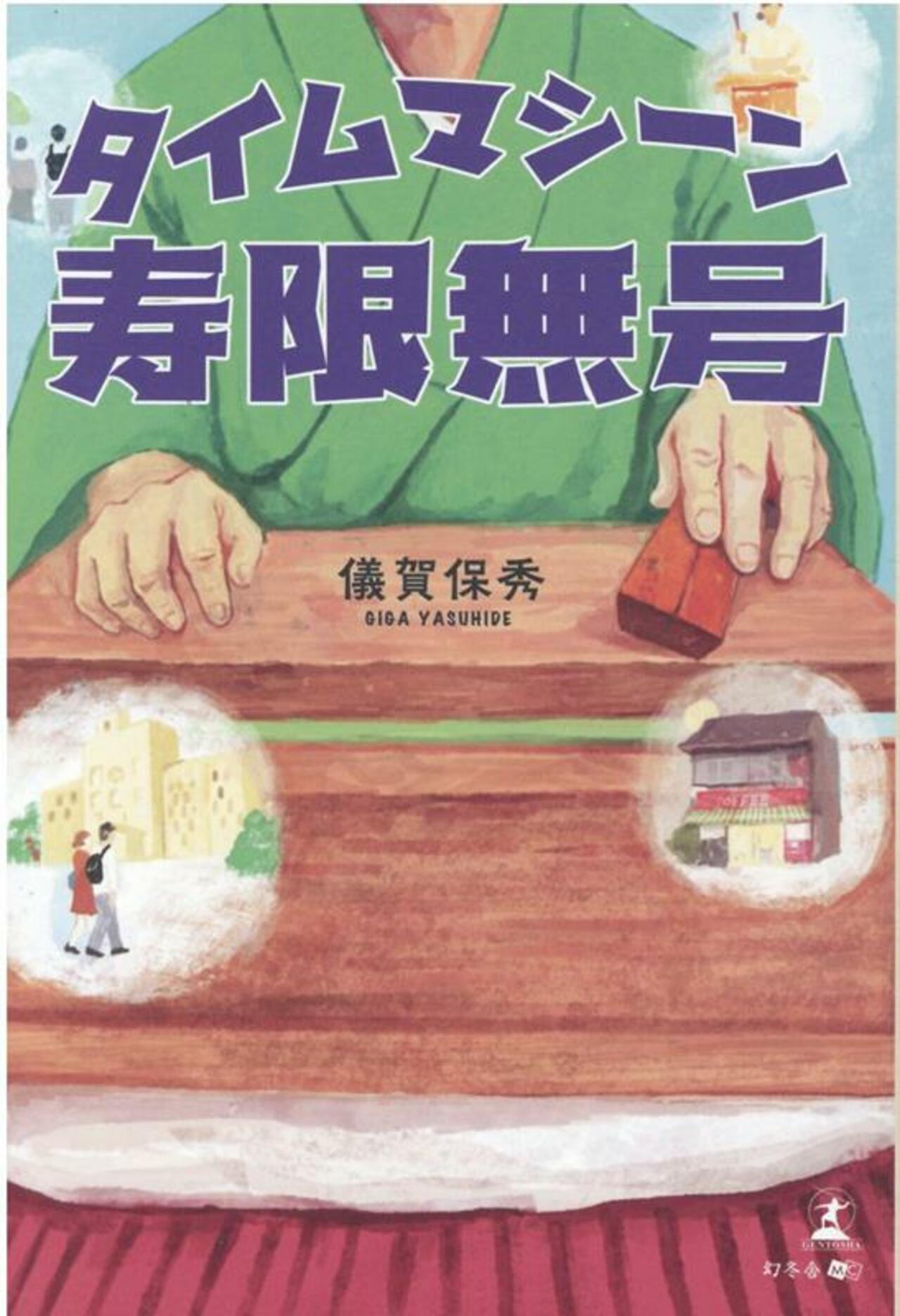当時、花楽亭喜桜は既にかなりの高齢であった。格好良くいえば、孤高の噺家。そんな気配が漂っていた。世間におもねることなく我が道を行くという感じ。
落語家ならば世間におもねるべきだとも思うが、喜桜はそんなことはどこ吹く風。
他の誰もがやらないような珍しいネタを多く高座で披露していた。
……と思いきや、突然、誰もが知り尽くしているようないわゆる前座ネタを堂々と演じることもよくあった。
そんなふうでありながら、尖った雰囲気は全くなく、容貌もニコニコ顔。マクラでも毒舌気味の話をすることもなく、いたって穏やかな話題に終始する。
そうしたところが喜之介の気に入った点であった。
大学を卒業していったん就職したものの、やはり落語家になるという思いは断ちがたく、思い切ってプロになろうと決心。「さて、誰の弟子になるか?」と思案した時、まっさきに思い浮かんだのが喜桜だった。
この人となら何だか楽しくやっていけそう。そういう思いだった。
確かに源太郎が言うように、自分の人生を託すほどの大げさな思いはなかった。
それより、修業が厳しくなさそう。そんな思いのほうが強かった。
また、喜桜には誰も弟子がいなかったことも大きな要素だった。ということは自分が入門すると、一番弟子ということになる。
一番弟子。その響きが気に入った。
少し真面目な考えとしては、「花楽亭」という亭号を残したいという、わずかな使命感もあった。落語家辞典のような文献を見ると、明治期には「花楽亭」という亭号で活動する落語家は多かったが、その後、あっという間にジリ貧状態となり、戦後は喜桜の師匠、喜之介からすると大師匠にあたる三代目喜桜だけになった。その弟子が喜之介の師匠である四代目喜桜で、もし彼が亡くなってしまうと、現役の「花楽亭」の落語家はいなくなってしまう。そんな状況だった。
そういう使命感が少しはあったが、源太郎のように落語家としての自分を大きく飛躍させるというような将来を見据えた視点はなかった。
源太郎と喜之介の落語家としての今の立場の違いは、既にその時点からハッキリと分かっていたといえる。
売れてみせる! そういう気合を充満させていた源太郎と、とりあえず落語家になるだけで幸せだ。そんな喜之介とは大きな違いがあったのだ。