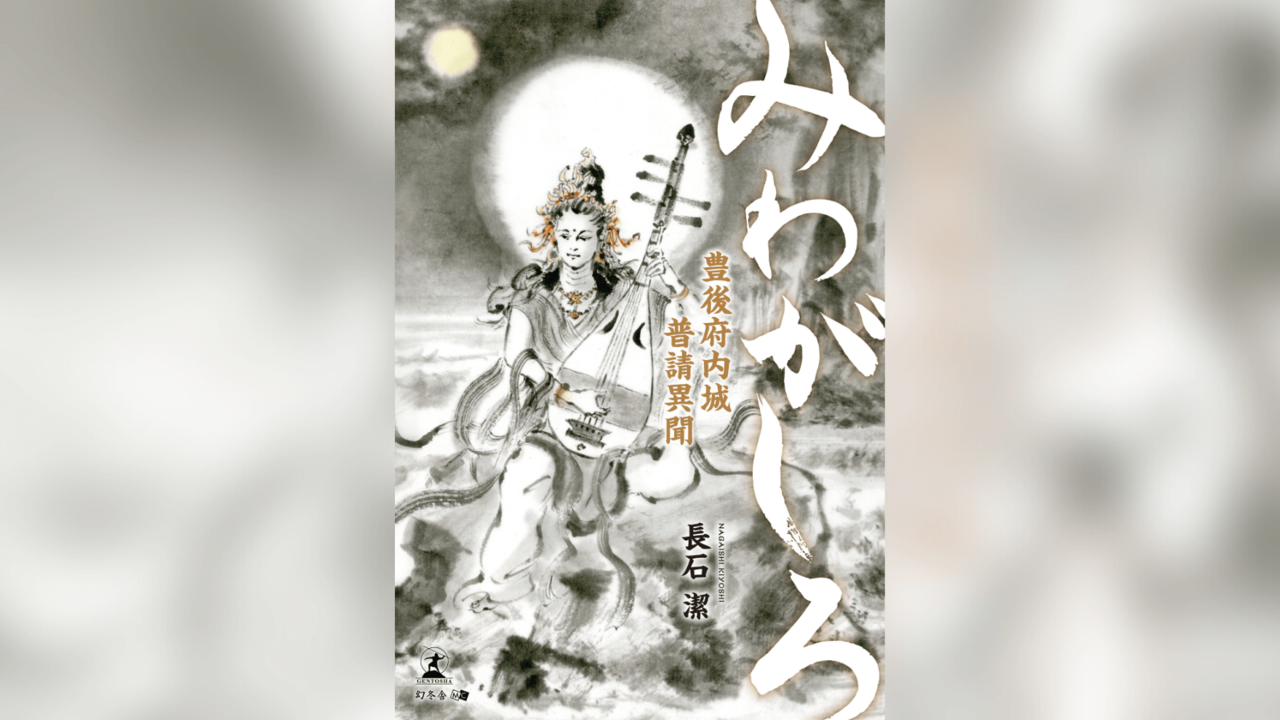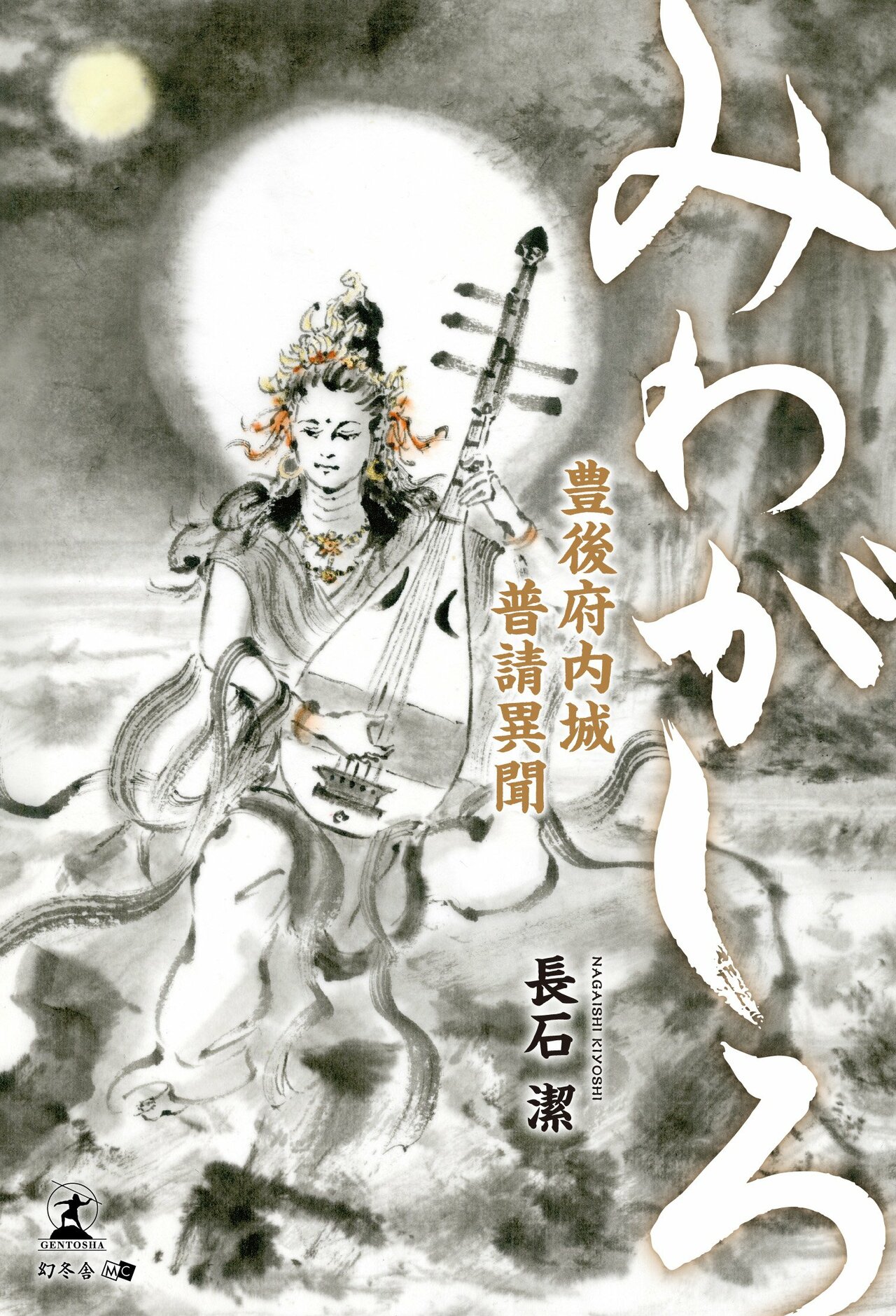【前回の記事を読む】正月行事に奔走する若き中小姓。ふと気づけば三月に……年中行事の手引きに気になる記述が
第一章 プロローグ
本来であれば、この手紙は城内の中間が持参するのが通常であるが、かねてから抱いていた疑問解消の鍵を見出した雄之助は、自ら持参することにした。
三月十七日、昼八ツ過ぎ(午後一時半頃)、御用所を出て天守台の石垣に目をやりながら大手門に向かった。城に天守はなく土台の石垣が残るのみである。寛保三年(一七四三)に町家が火元の大火があり、本丸と二の丸の大半が焼け落ちたため、幕府の許可を得てそれらの修復が図られたが、天守は再建されなかったのである。
屋根の上に鐘楼(しょうろう)の載る大手口多聞櫓(たもんやぐら)を潜(くぐ)ると、中間の治助が供待に腰掛けていた。三の丸へと続く廊下橋を渡り切ったところで治助に寄り道をする旨を伝え、二人は自宅とは反対側の東へ向かって歩を進めた。
いつも雄之助に寄り添う治助は、雄之助誕生のときからの付き合いで、実の両親のたっての願いで養子先についてきた。それは幼少から雄之助の世話を焼き、遊び相手になってきた治助の願いでもあった。治助はもう五十を過ぎ老境に入っていた。
目指す寺は廊下橋から一町(約百九m)ほど離れた三の丸の東端にあるが、寺へ向かう道すがら堀に目をやると、腰に脇差しの見えるどこかの中間とおぼしき初老の男が、堀に向かって網を投げるのが見えた。まるで漁師のようなその姿に思わず雄之助の口元が緩み、後ろに従う治助も失笑した。
大分川の支流河口付近にある府内城の水堀は、その河口の水を引き入れているが、それにより潮汐(しお)の干満の影響を受けることとなるため、その汽水域(きすいいき)と呼ばれる川の水と海水が混じり合う流域を好む、鯔(ぼら)や鱸(すずき)、そして黒鯛(くろだい)などが入り込んでくるのである。