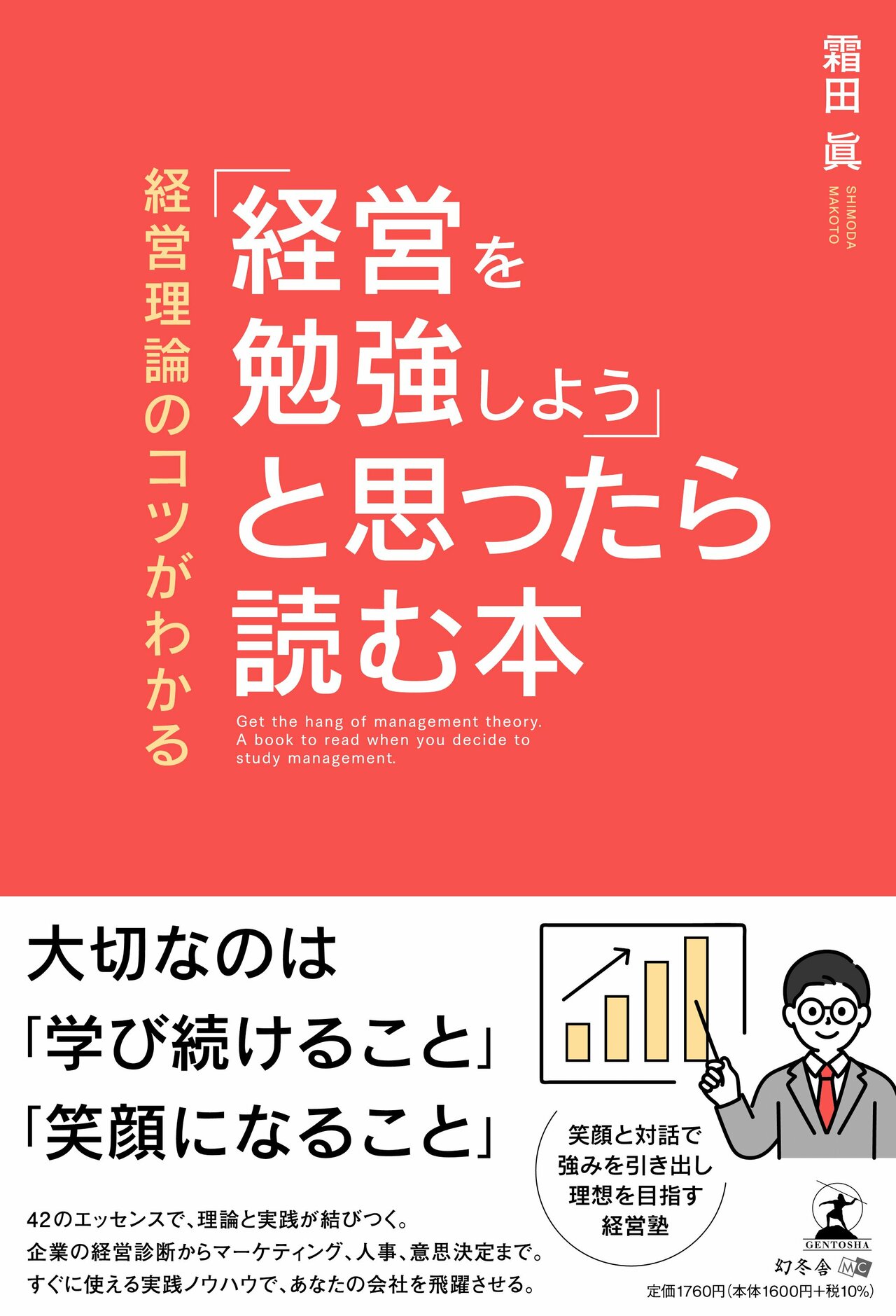・5つの原則
ピーター・M・センゲは『学習する組織』で5つのディシプリン「自己マスタリー」「メンタル・モデル」「共有ビジョン」「チーム学習」「システムシンキング」を示すとともに、
「ディシプリンを実践することは手本に倣うこととは違う。」
「彼らはみな部分をみてその部分をまねる。彼らが目を向けないのは、すべての部分がどう連携しているかです。」
「5つのディシプリンが一つにまとまったとき、究極の『学習する組織』ができるのでなく、むしろ実験と進歩の新たなうねりを生み出すだろう。」
と記しています。
以下は筆者の解説(私見)です。
1. 自己マスタリー:自分のスキルだけでなく人生と一体化して成長を目指します。
2. メンタル・モデル:自分の固定観念を明らかにして行動を改善します。
3. 共有ビジョン:個人ビジョンから生まれる全員が目指すビジョンを共有・実現します。
4. チーム学習:対話で学習を引き出し、チームの高い能力を作り出します。
5. システムシンキング:問題が複雑に絡み合うことを認識して考えます。
「既存のものから学ぶ」のではなく、チームの学びを「生成する」ということです。
[代表例]
根本孝著『ラーニング組織の再生』では、「ラーニング組織としての3社(トヨタ、ホンダ、日産)の特徴を分析し、 3社3様のラーニング組織の類型を分析」しています。同書では、「継続改善型のトヨタ」「夢追求型のホンダ」「危機突破型の日産」と位置づけられています。
たしかに日本では現場の一人ひとりが学び、改善する意欲が高く、それが企業そのものの成長に結び付いています。また、同書では学習しない組織の代表として、「官僚制組織」「大企業病組織」を挙げています。頭が固いとか縦割りだとか、いわれるような会社には、学ぶ文化は根付いていないんでしょう。
・ダイアログ(対話)
学習する組織を実現するうえでは、ダイアログが有効です。対話(ダイアログ)を通して、かかわり合いを築き、情報を共有し、学びを深めていきます。従って、ダイアログの場を設定していくことが大切ですし、その場でのファシリテーションも大切です。
6 暗黙知を活かす~強みを見つけ知識を創造する
・暗黙知とは
頭ではわかっているのに言葉で伝え切れないことがあります。暗黙知は「経験や勘、直感などに基づく知識」「簡単に言語化できない知識」です。日本企業の文化にもなっています。「名人のコツ」のような技能的な意味合いと、言葉にしにくい「感情のようなもの」「思い」「世界観」を意味することがあります。昔の職人は「俺の背中を見て覚えろ」と言ったとか。
転職が当たり前の時代になると、暗黙知の継承・活用が大きな課題となります。「個人の暗黙知」が「組織共有の形式知」になっていないと活かし切れていないことになります。ベストプラクティスには暗黙知があるはずです。その企業の強みが隠れているかもしれません。
👉『経営理論のコツがわかる 「経営を勉強しよう」と思ったら読む本』連載記事一覧はこちら
【イチオシ記事】「大声を張り上げたって誰も来ない」両手を捕まれ、無理やり触らせられ…。ことが終わると、涙を流しながら夢中で手を洗い続けた