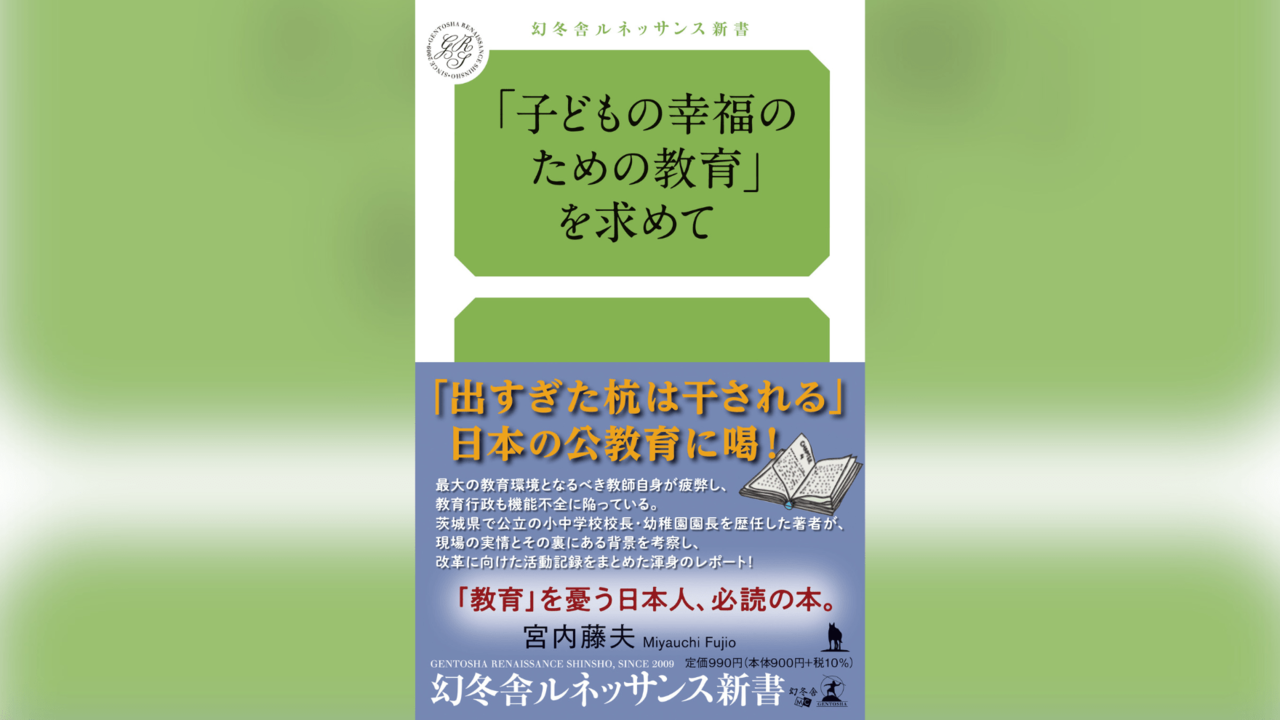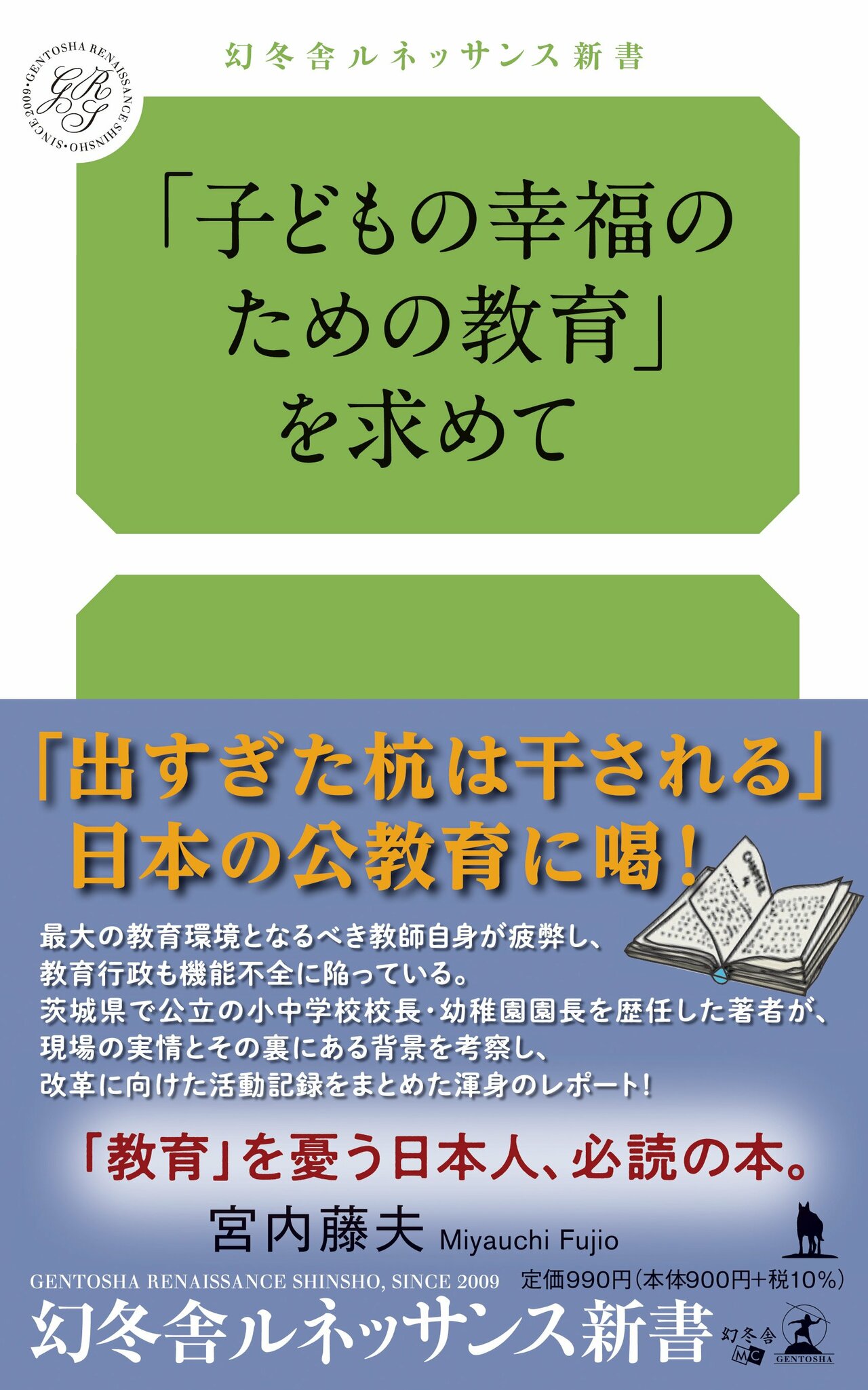【前回の記事を読む】信頼と人気が揺らぐ「教師」という職業。一部の不祥事や過酷な労働実態がマスメディアで取り上げられてしまい…
序章 私の教育実践
校長時代の思い出
学力が主要4教科合計平均点で、市内の同学年他校と比べて最低だった50名の学年が、2年後には平均点で48点も向上し、市で一番になるという奇跡的な成果をあげたのです。
子どもたちは、自分で決めたことに取り組み、先生や保護者の励ましを受けながら自ら振り返れば、必ず努力する習慣がつく、と確信して取り組んだことでした。
4月に決めた目標を確認しながら全児童と面談し、2月にその成果を確認するかたちでまた全員と面談しました。その取り組みにより、ほぼ全員が、それまでよりよい学習や生活の習慣を身につけていったのです。自分で決めた目標であれば、子どもたちは誰でも、妥協せずに取り組むことができるようになるものです。
その後の人生もそうあってほしいと、子どもたちを思い出す昨今です。
支えてくれた優秀な先生が亡くなられて
私が県内一の大規模校で教務主任のときと、閉校した小規模校で校長のときに、優秀な担任として私を支えてくれた、まだ49歳のきわめて優秀な女性の先生が、2021年12月16日に亡くなられました。私の離任式のときに、一粒種の優秀な娘さんが私を讃える送辞を送ってくれるなど、深い縁のある先生でした。
私が校長だった小規模校では、いつも笑顔で生き生きと、驚くほど優秀な指導力を発揮されていた先生でした。
管理職に挑戦してみたいとの気持ちがあり、小規模校6校が統合された大規模校に転任すると(茨城県では小中両方の経験がないと、管理職になれない決まりがある)、担任した三十数名の子どもたちにいじめや不登校などのトラブルが続き、同学年の先生方との仕事の調整などで、神経をすり減らすことが多くなり、次第に笑顔が減っていったそうです。
そのあと、管理職を目指して中学校に移動すると、いきなり全学年2学級ずつ6学級の社会課主任として教科指導を任され、責任感の強い彼女は、毎晩深夜までわかりやすく授業をするための準備をしていたそうです。
初めての部活指導でも、子どもたちに軽く見られないよう、厳しめの指導をしたことで、生徒たちの反発にあい、そこでもずいぶんと苦しんだようです。
40代半ばで中学校教師になると、教科担任としても部活顧問としても初めてのことばかりで小学校との違いに戸惑い、悪戦苦闘しながら深夜まで授業準備に取り組み、部活指導でも生徒に反発されるなどして、肉体的にも精神的にも限界を超え、療養休暇を取らざるをえなくなってしまったのです。
そのあと、地元の小学校に転勤しましたが、中学での挫折が尾を引き、出勤と療休を繰り返し、体調をさらに崩して、お亡くなりになってしまったのです。
誰にも弱音をもらさず、限界を超えた肉体的精神的な苦闘の末に、療休を取らざるをえなくなり、回復が果たせなかったわけですが、小学校で成功体験を重ねた先生が、中年になって中学校に移ると、うまくいかずに苦労する話は、茨城県ではよくあることです。
私も、小規模で落ちついた小学校から荒れた中学校に転任した際には、そのギャップに驚き、散々苦労しました。私の場合は、まだ30代前半だったことや、気迫と風体の怖さとで、荒れた子どもたちもなんとか抑えることができましたが、40半ばの生真面目で細身だった彼女には、すべてが大きすぎるプレッシャーになったようです。