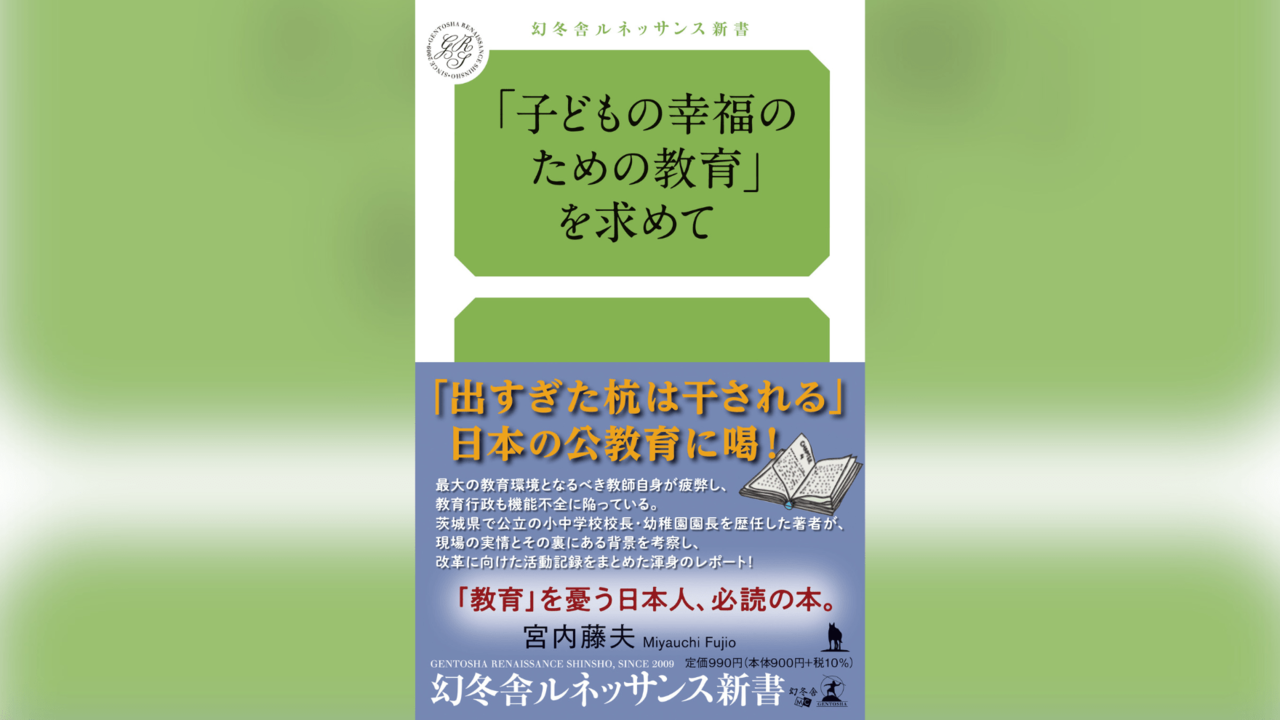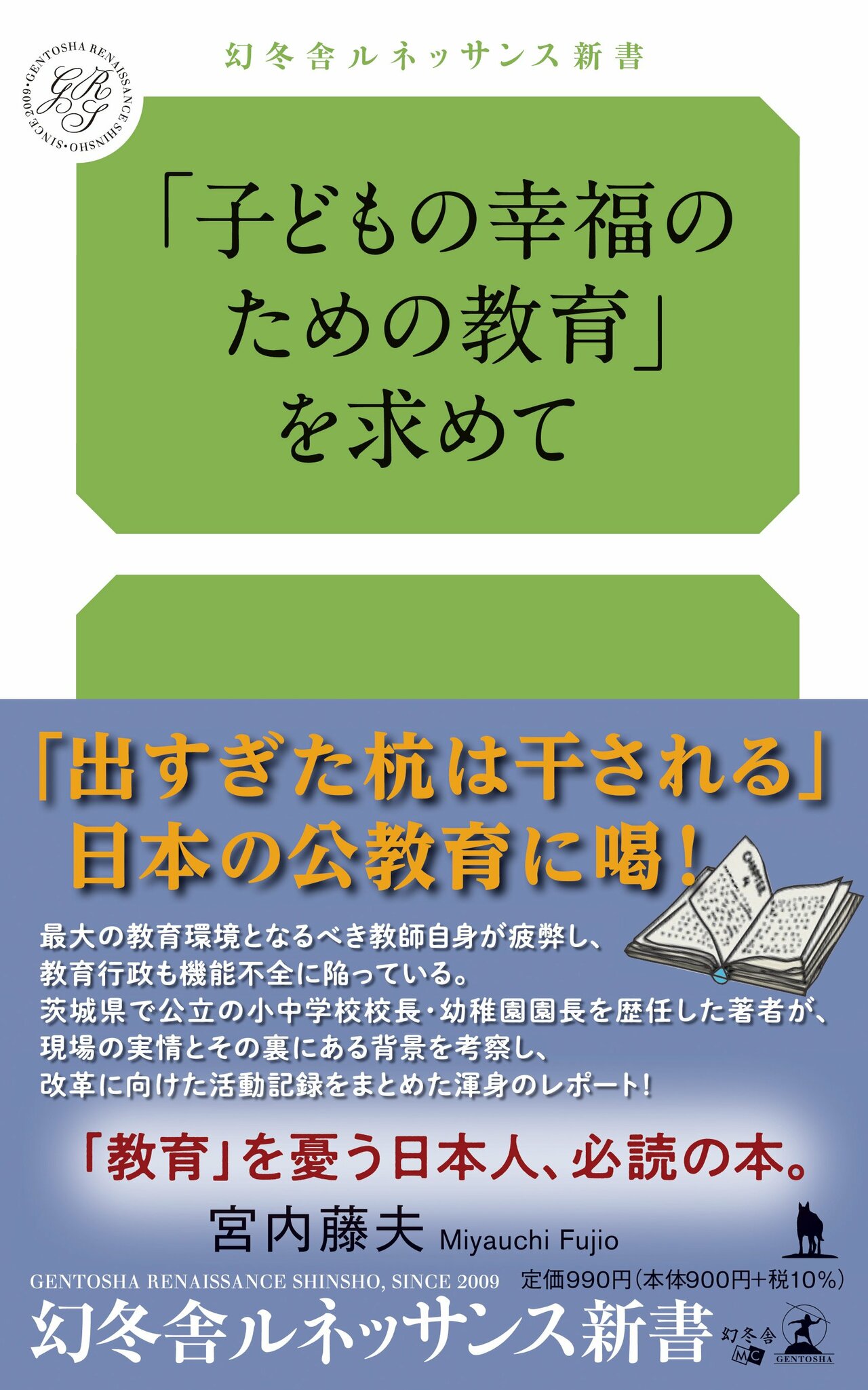はじめに──日本の教育の常識は、世界の非常識
なぜ、日本の教育には、教育行政間の格差が大きいのか、少子化が進む一方なのにいじめや不登校が増えるのか、特別な支援を必要とする児童生徒が激増しているのか──私はこれらの問題を現役教師や校長の時代から考え続けてきました。
その一方、目の前の子どもたちへのより効果的な指導や、先生方がより生き生きと子どもたちを指導できるようにするにはどうしたらよいかが喫緊の課題であり、与えられた教育条件に目を向ける余裕はそれほどあったわけではありません。
教育現場から離れた今、教員不足や教員志願者の減少問題が深刻化し、日本の教育の未来、ひいては日本社会の未来が危うい状況になっているなか、「子どもの幸福のための教育」を実現するための教育改革運動が不可欠であることを痛感します。
前後しますが、私は、創価大学教育学部1期生(全学部では6期生)として、1979年に茨城県の小学校の教員に採用されて以来、小学校中学校の教諭として4校24年、教頭として3校7年、校長として2校5年の教員生活を経験しました。その36年間の教員生活のなかで、一貫して考えてきたことは創価教育学会の創立者牧口常三郎先生の理念である「子どもの幸福のための教育」の実現であります。
冒頭に述べたように、教師は与えられた条件のなかで、精一杯取り組むしかありませんが、与えられた条件自体に「子どもの幸福のための教育」とは、ほど遠い多くの問題があります。
「日本の教師たちの教育条件は、教育先進国である欧米諸国と比べて極めて低い」という現実が横たわっているのです。