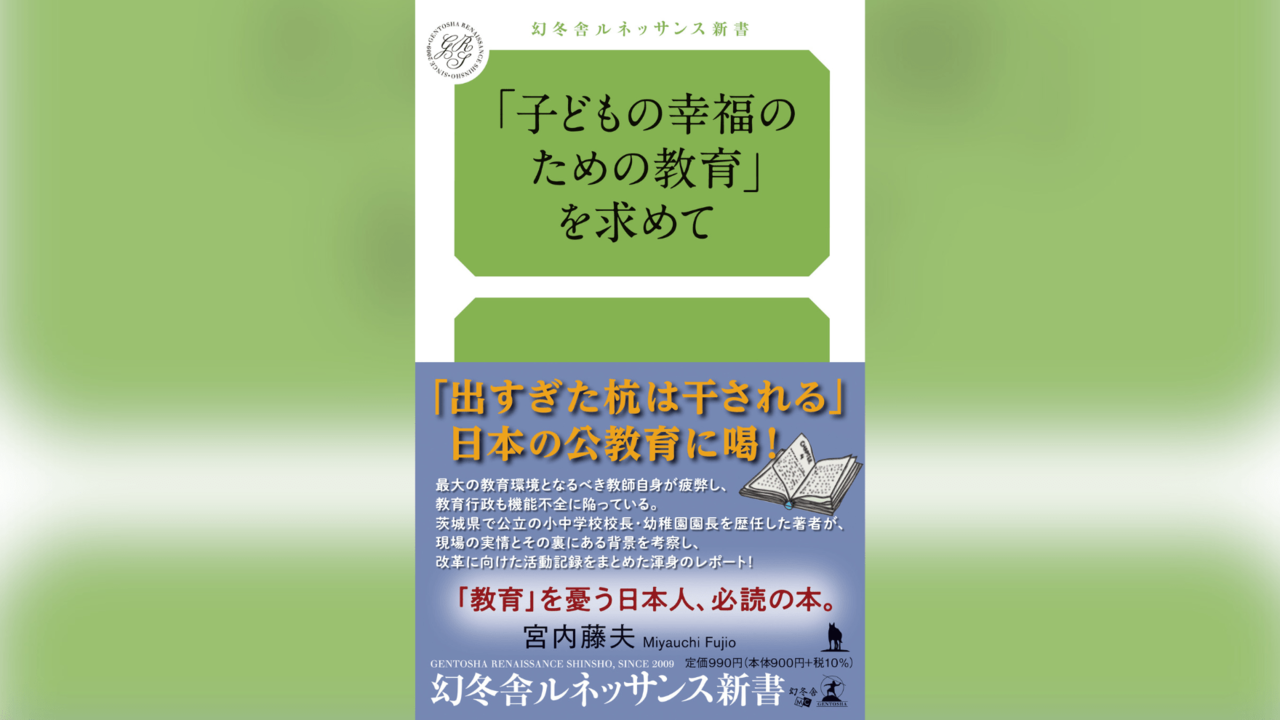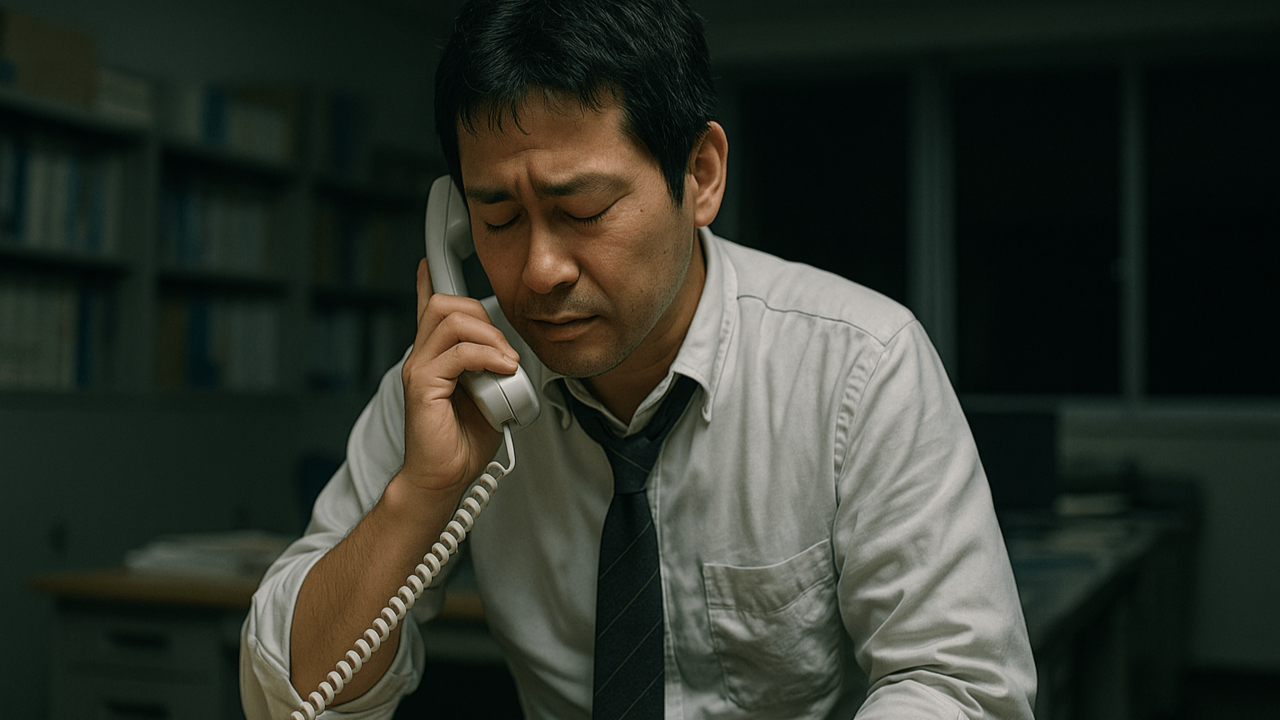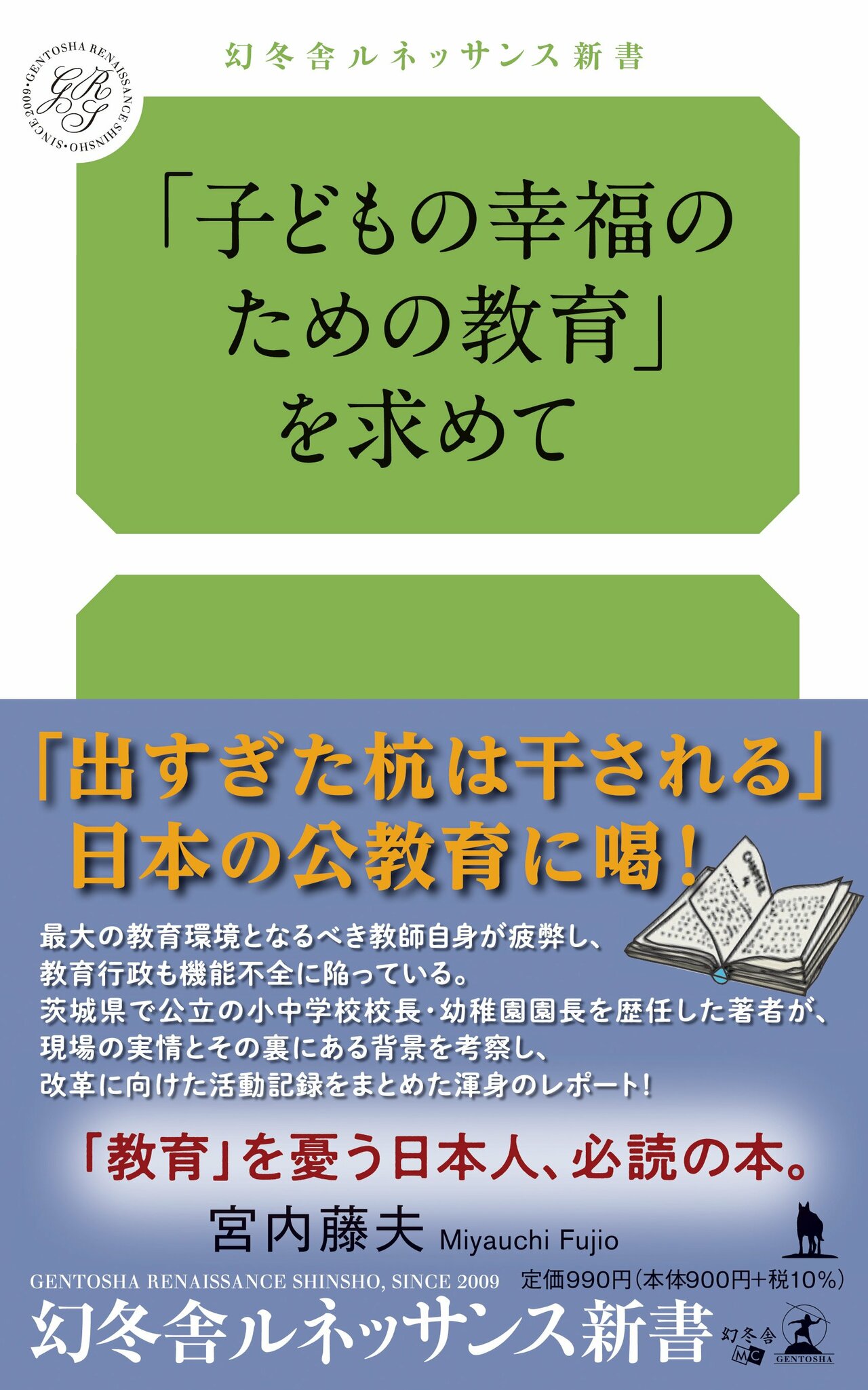【前回の記事を読む】日本社会の未来が危うい。いじめ、不登校、少子化、教育行政間の格差…元校長が語る「教育改革運動」とは。
はじめに──日本の教育の常識は、世界の非常識
社会基盤となる教育が充実した社会になれば、自ら学ぶ意欲を獲得した若者や奮い立つような使命感を持った人たちが、いかなる分野のいかなる課題にも果敢に挑戦する勇者となって勢揃いし、日本のみならず今の地球が抱える問題を力強く根こそぎ解決するような力になってくれるのではないでしょうか。
そのような教育原点の大改革をすべての人間の叡智を結集して成し遂げ、世界平和の実現や地球規模で広がる環境問題や食料問題などのあらゆる問題を解決する力になれるよう、宇宙船地球号を支える乗組員として、互いに活躍しあえる社会を実現していきたい。
そんな思いを、できるだけ多くの皆さんと共有したいと願い、この本を上梓させていただきました。
序章 私の教育実践
少人数学級での思い出
私は教員になった当初、茨城県の鹿島町(現鹿嶋市)にあった120人程度の小規模小学校に採用されました。主に高学年担当で、一人ひとりに対応したきめ細かいかかわりと教育ができました。
当時は放課後のミニバスケット少年団の担当もしました。全員参加のチームで試合をし、30校中1位となり、県大会に出場したこともありました。この学校で教えたときは、一人ひとりの個性を把握し、丁寧に指導ができましたし、子どもたちのこともよく覚えています。
結婚式に呼ばれたり、子育ての相談を受けたり、経営するお店に食べに行ったり、今も多くの教え子とよい関係を続けています。
一方、その後に赴任した大きな学校の、ほぼ40人学級の教え子たちに対しては、勉強を教えるにも一人ひとりには対応しきれませんでした。いじめもトラブルもモグラ叩きのように多発しました。
卒業してからの連絡もありませんし、忙しかったこと以外には、一人ひとりを思い出すこともできません。これらのことからも、より人間的な関係も深めながら、質の高い学びの場を提供するためにも、少人数学級での指導を基本にすべきだと思います。