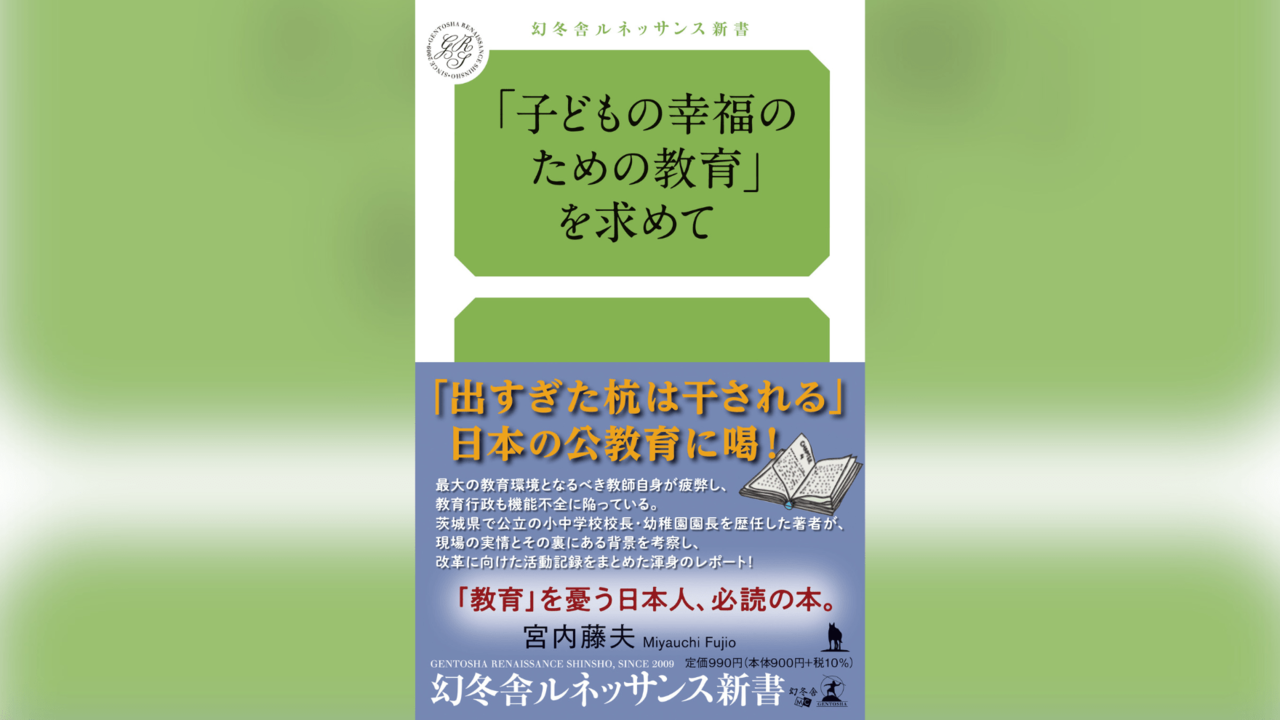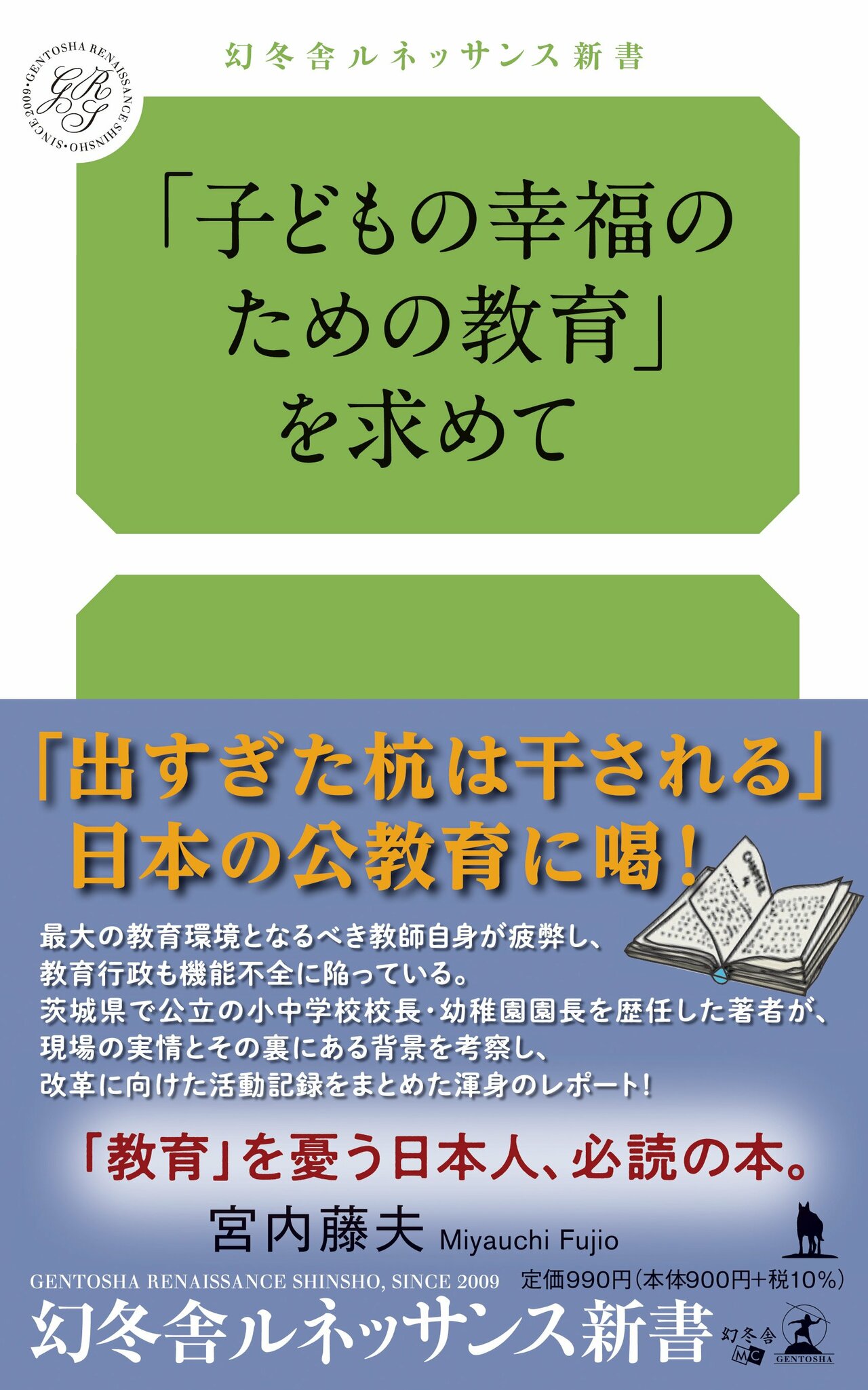【前回の記事を読む】地域でも有名な荒れた中学校に転任 いちばん問題行動の多い生徒の集まる柔道部の顧問を務めると...
序章 私の教育実践
21年間、毎週発行し続けた「教職員研修」
しかし、不適格教師の問題や学校業務のブラックな実情が、新聞をはじめとしたマスメディアに取りあげられるようになってから、教師への信頼と人気は揺らぎはじめ、「教員免許更新制」などの足かせをはめられるようになりました。
今の教員不足や志願者減は、研修への厳しい認識を共有する教師たちが、あれもこれもとやるべきことを増やされながらも、必死に学ぶ時間を確保しようとしてきたにもかかわらず、一部の不届き者ばかりがクローズアップされた結果にほかならないと思います。
ほとんどの教師たちの日々の努力を裏切る、一部の教師たちの不適格性ばかりがクローズアップされ、そんな教師ばかりが増えているという印象ばかりが撒き散らされたのです。
そのことへのご理解をいただき、もう一度、教師という職業への尊厳性と信頼を回復させてほしいと願う昨今です。
参考までに、2013年4月に、私が校長として赴任して、牛堀小教職員研修の第一号として、挨拶代わりに全教職員に配ったものは以下のようなものでした。「牛堀小教職員研修No1」(2013年4月3日)
赴任挨拶でお話ししたとおり、校長室便りも兼ね、毎週「教職員研修」を発行します。 研修は、教職に就いている私どもにとっては、必要不可欠なものです。
ふだんには研修の間もなく、いつも児童のために忙しく時間を費やしている先生方が、「なんのために」との原点に立ち戻り、これからの教育に必要な視点や論点を思索し、相互に触発し合っていく材料を提供させていただければと考えております。
初回は、「研修」の意義について考えてみたいと思います。
研修とは、研究と修養のこと
研修の機会①:地公法第39条第1項職員には、その勤務能率の発揮および増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
研修の機会②:教育公務員特例法第22条第1項教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
研修の義務:教特法第21条第1項教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
研修への協力:地教行法第45条第2項市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。