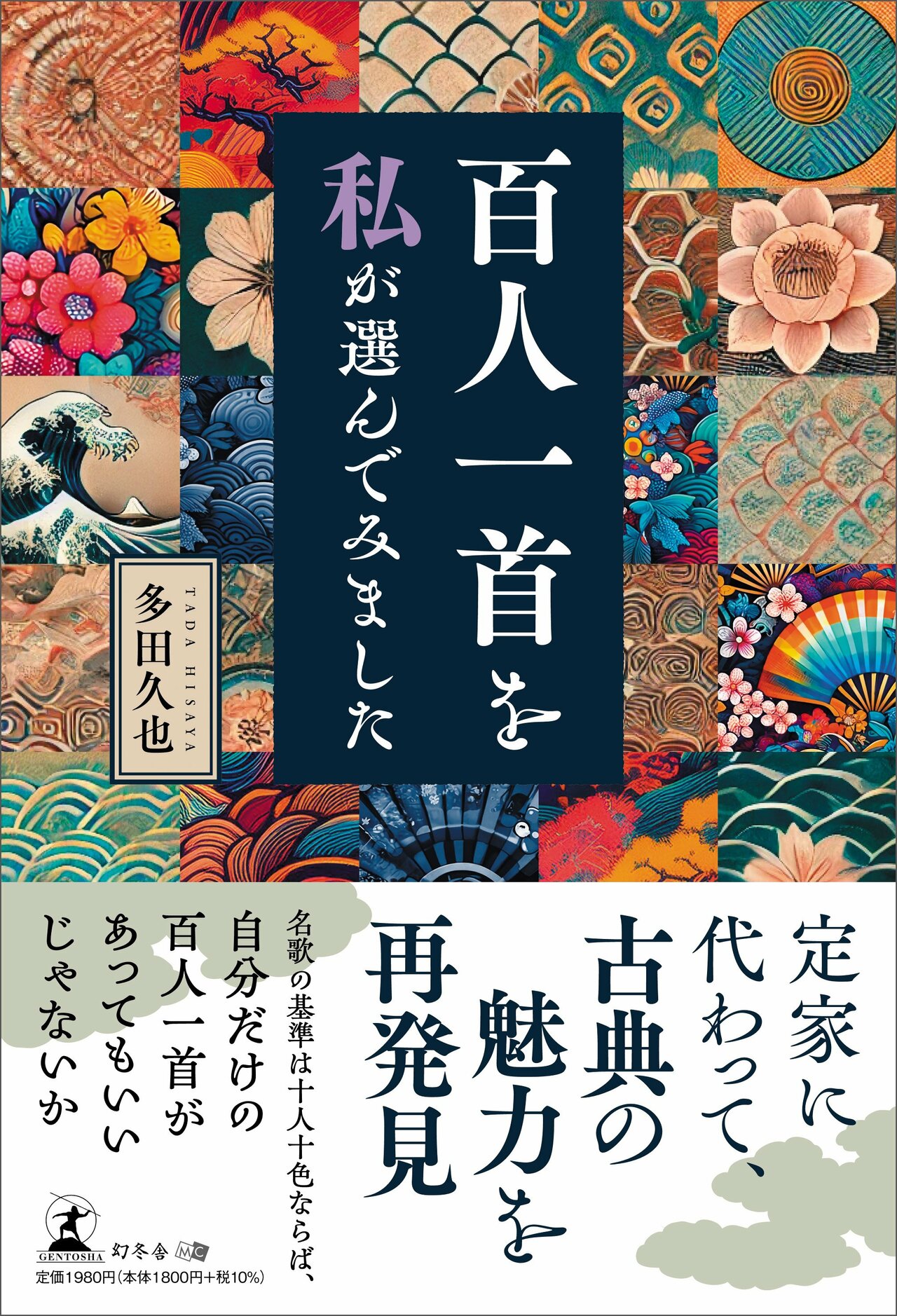10 小野小町(生没年不詳)
はかなしやわが身のはてよ浅みどり野辺にたなびく霞と思へば
(はかないことだ、わが身の果てよ。それはただうっすらとした藍色の野辺にたなびく霞であると思うとよ)
第三句の「浅みどり」がポイントである。「野辺」に枕詞風に繋がるとともに、霞のはかない色を示唆している。もしこの鮮やかな色彩の詞がなければ、単なる陰鬱な響きの歌になってしまうだろう。なお、浅みどりは薄い緑ではなく、夕空のような薄い藍色である。
また、「霞」とは、荼毘の煙が天に立ち昇るという意味である。憂き世の恋も悩みもしがらみも、死ねば焼かれて野辺にたなびく浅みどりの霞になるだけ、という小町のひそやかなつぶやきが聞こえてくるようだ。
小野小町は、日本ではクレオパトラ、楊貴妃とともに世界三大美人の一人とされている。
小町の出生・経歴とも不明だが、小野篁(たかむら)[本書11番]の孫あるいは娘とする説がある。絶世の美女であったこと、仁明天皇・文徳天皇の頃宮廷に仕えていた点だけは諸説共通する。『古今和歌集』に残されている贈答歌から、在原業平、遍昭、文屋康秀らと親交があったということも確かである。
しかし、晩年の小町が乞食姿で諸国を放浪し老醜をさらしたという伝説は、全く根拠がないことと言わざるを得ない。
小町の歌には女性らしい繊細さの中にも情熱的な恋愛感情が描かれているものが多い。
『古今和歌集』仮名序で、紀貫之は彼女の歌を評して「あはれなるやうにてつよからず。いはばよき女のなやめるところあるに似たり」と、つまり、しみじみとしたところがあって、貴婦人が病んでいるような風情がある、と述べている。勅撰入集は六十五首ある。小町といえば夢の恋歌を多く詠った歌人という印象が強い。
その中から特に惹かれる二首を挙げたい。
うたたねに恋しき人を見てしより夢てふものはたのみそめてき
(不意に落ちたうたた寝に恋しい人を見た。その時から、夢という頼りないはずのものを、頼みに思うようになった)
思ひつつ寝ればや人の見えつらむ夢と知りせばさめざらましを
(恋しく思いながら寝入ったので、その人が現れたのだろうか。夢だと知っていたら、目覚めたくはなかったのに)