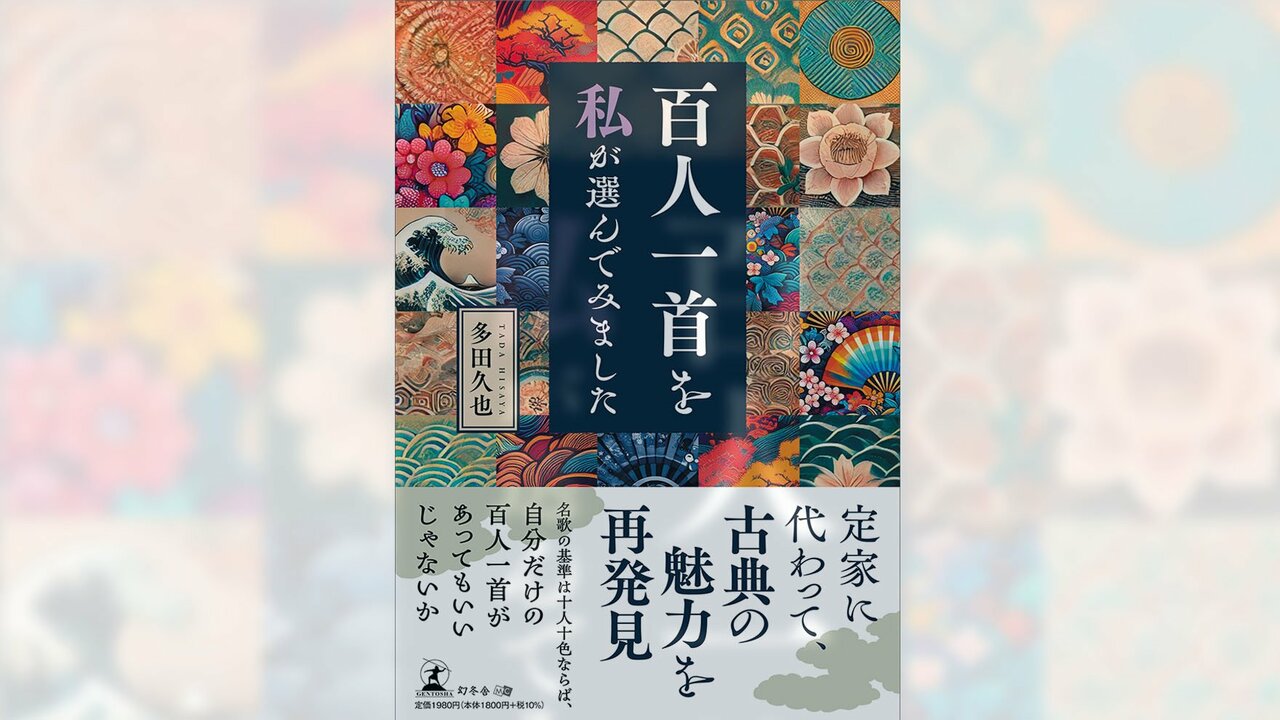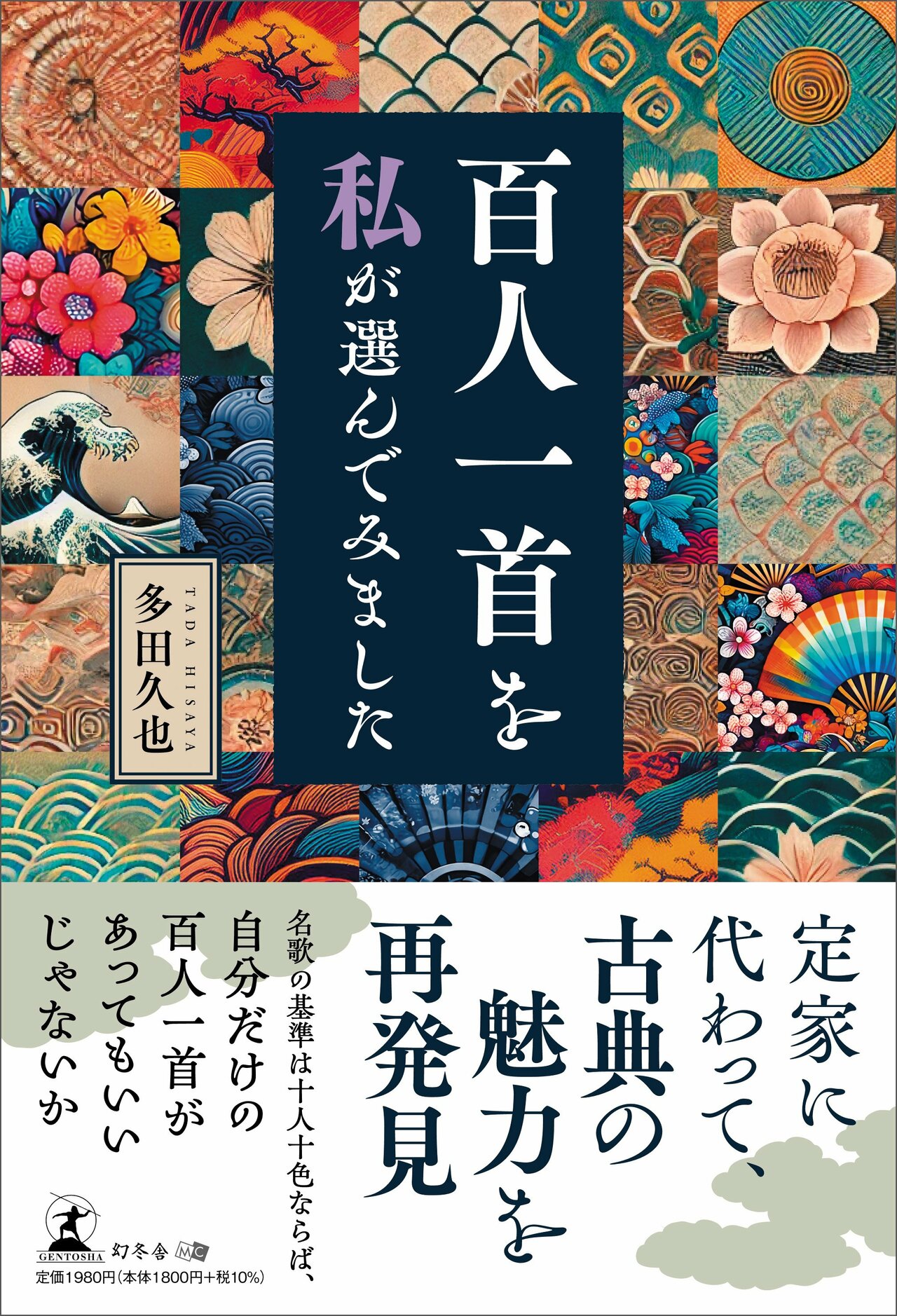【前回記事を読む】万葉集に宿る普遍の心――親子の情を詠んだ山上憶良と春愁を描いた大伴家持
9 大伴家持(七一八~七八五)
大伴家持は大伴旅人の嫡男である。弟に夭折した書持、叔母に坂上郎女がいる。坂上郎女の娘・大嬢(おおいらつめ)を正妻とした。
代々軍事を司る家系の高官で、今で言えば自衛隊の幕僚長のような立場であった。最終的には中納言まで昇ったが、藤原氏の勢力に押されて、謀反に関わったとして左遷や解任されたこともあり、官人としては波乱に満ちた人生であった。
家持は人麻呂や赤人らの宮廷歌人の伝統を引き継ぎ、万葉歌の世界を総合した大歌人である。『万葉集』の撰者・編纂者といわれ、『万葉集』に四七三首という最も多くの歌を残した。勅撰入集は六十三首ある。『万葉集』四五一六番、最終を飾ったのも家持の歌だ。
新しき年の初めの初春の今日降る雪のいやしけ吉事(よごと)
(新しい年のはじめの初春の今日降る雪、この降り積もる雪のように、いよいよ積もりに積もれ、佳き事が)
正月の大雪は豊年の瑞兆(ずいちょう)とされたのである。『万葉集』はこのように、未来の幸せを願う歌で終わる。このとき家持は四十二歳。この歌以降、生涯を終える六十八歳まで、家持が詠ったとされる歌は残されていない。
小倉百人一首
かささぎの渡せる橋におく霜のしろきを見れば夜ぞふけにける
(かささぎが白い翼を広げて天の川にかけた橋のように見える御所の階段に、白く霜が降りているところをみると、夜もずいぶん更けたのだなあ)