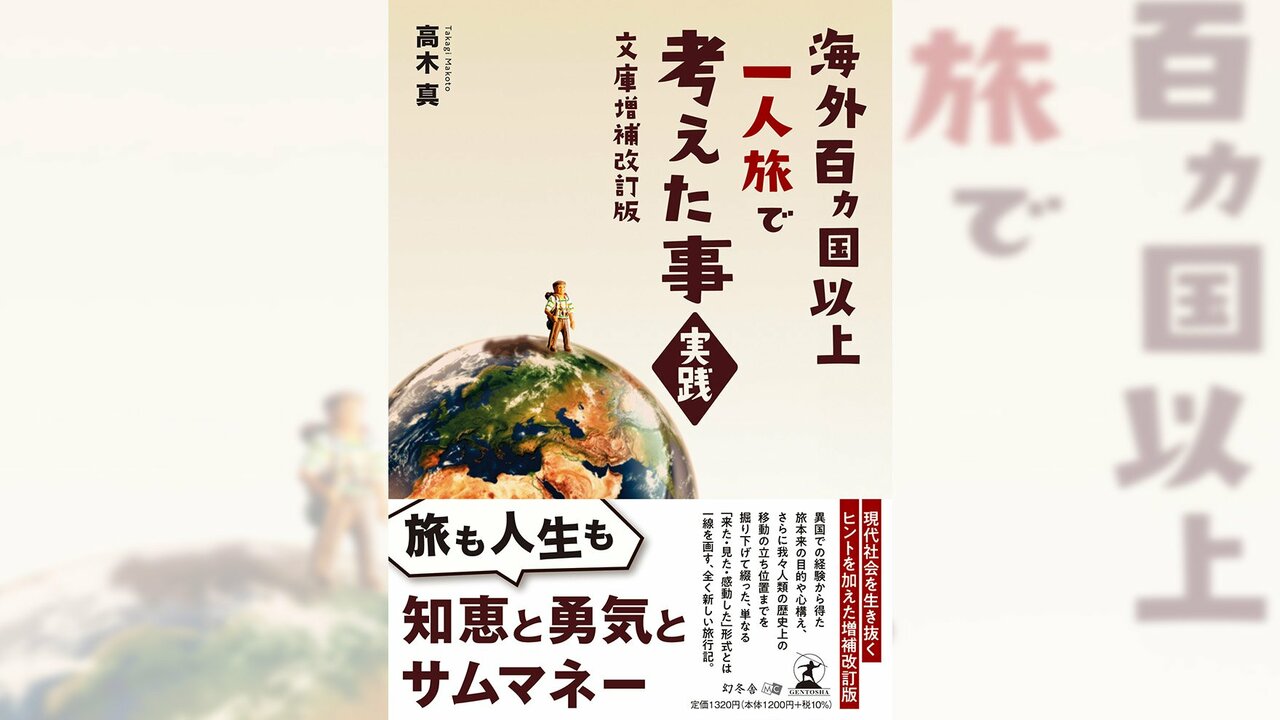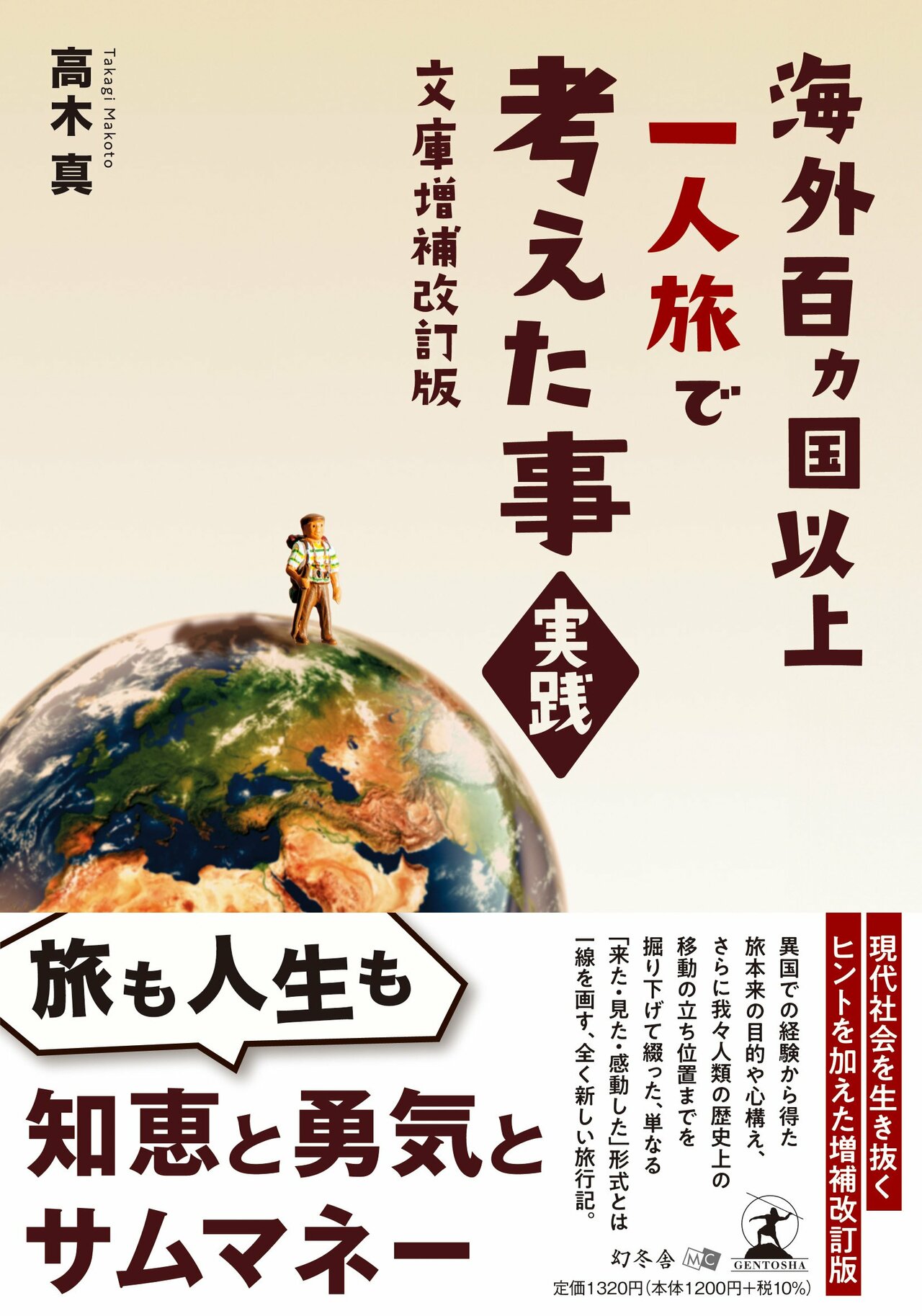【前回記事を読む】第一次世界大戦が始まった。バルカン半島を巡って様々な対立、そしてサラエボ事件を引き金に、無関係の国が次々と巻き込まれ…
私の国内外の旅と旅とは何かについて
海外旅行を加速させた円高
円高は、日本の輸入・海外旅行には有利だが、輸出や海外へのドル建て資産(外債)保有では不利に働き、そのための日本国内不況、その対策として金利安(公定歩合の引き下げ)・円通貨量の増大(中央銀行・日銀の買いオペ、債券を買い取り通貨を市場に放出する方法)、
銀行も利ザヤ稼ぎのために(金利低下で利ザヤが減少したため、貸出額を増やし、量・ロットで利益を確保しようとした)積極的に不動産・株取引に融資し、結果としての金余り・日本国内のバブル発生、
すなわち株・不動産へ過剰な資金が流れ、株・不動産からのそれ自体の収益よりも、上がるから買うまたそれを担保に銀行に金を借り更に買うというスパイラル状態が続き、株・不動産価格の異常な暴騰、そしてついに銀行の融資規制・貸出禁止・貸し渋り・貸しはがしが起こり、
結果として誰も買わなくなる・買えなくなるという逆のスパイラル状態となり急落を招き、バブルが崩壊した(日本のバブル崩壊の直接のきっかけは、当時の不動産融資総量規制の一片の通達だったと思う。これで全国の銀行が一斉に、「オカミ」からの通達として不動産融資をしなくなった。
徐々にやればいいものを、急に血液を止めるような事をしたので、その後不動産関連会社からの倒産が始まった)。その後、バブル後処理のため失われた20年が続いた。
それ以前の、戦後の急激な円高前の、日本人の主な海外渡航は、生活のため(略奪・交易のためも含む)・仕事のため・留学・研修のためであった。
決して旅行としての海外旅行ではなかった(仕事にせよ、海の時代の外航航路を行き来する・海外に行ける、異国情緒漂うマドロス(昭和の時代のはじめの歌謡曲によく出てきた、船乗り・船員の意味のオランダ語由来)は、現在の空の時代のパイロット・スチュアーデス(キャビン・アテンダント)同様、あこがれの職業だった)。
唯一例外が考えられるのは、第一次世界大戦の戦場にならず、ヨーロッパへの日本の輸出の好景気で、成金(将棋で歩から金になる所からきている)になって、汽船で海外旅行(一時的に日常生活の場から離れて、物見遊山で外国に行く。ただし、船による旅で相当な時間がかかったと思われる)が出来た人たちぐらいであったであろう。