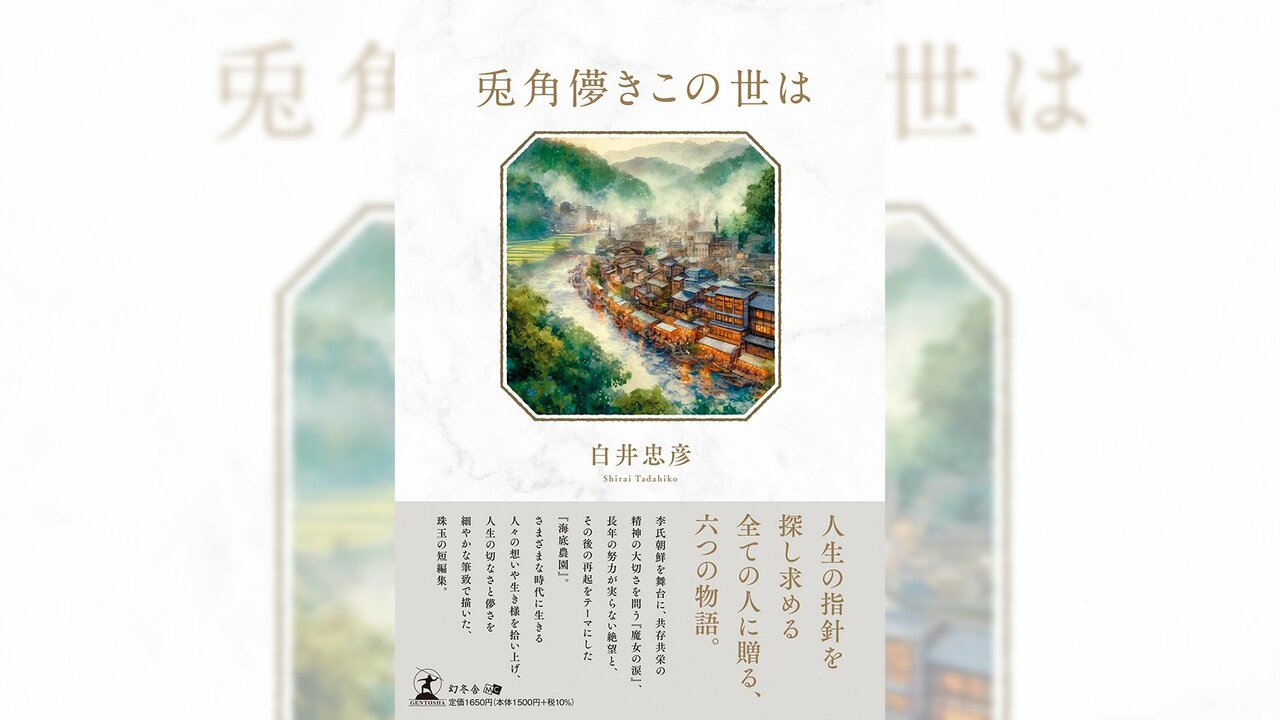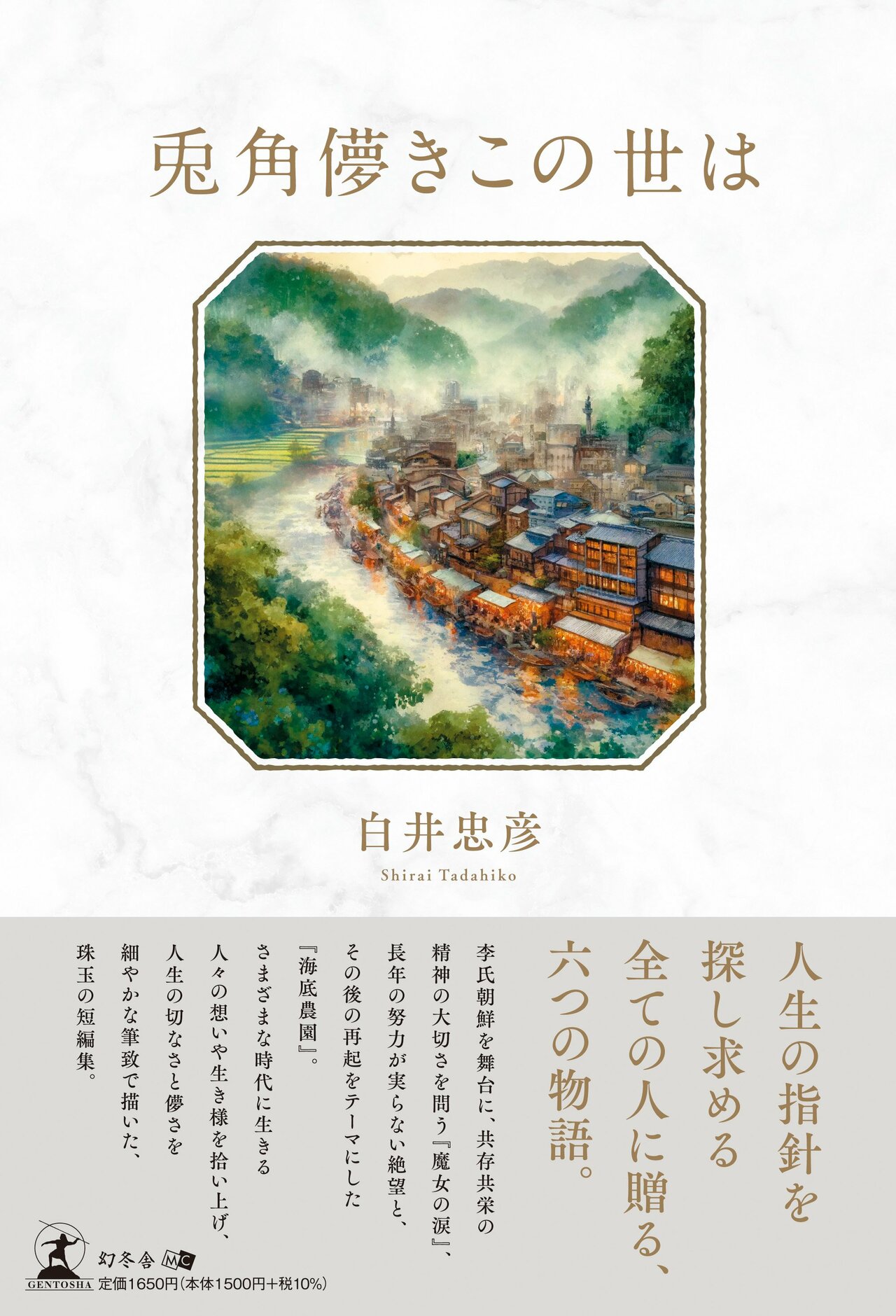【前回の記事を読む】暴君となった王は、かつての気高き心を取り戻すことが出来るのか。握った刀の行き先は…。
海底農園
一
終戦、それは悲劇の結末でありながらも多くの日本人が待ち望んだ結果であり、地上では暴力を通して善悪を決定する時代が終焉を迎えた。未だ力ある者による搾取や横行が微視的な日常の中には潜んではいたが、取締りの強化もあり、民間の人々が武力を持つ必要性は徐々に減少した。
武司は先の戦争で上官を務めた父を持ち、幼少期から剣術を習わされた。比較的小柄であった武司にとって、年上で体も大きい仲間との訓練は苦痛そのものであり、毎度ぼろぼろになっては、ぐずりながら帰って来た。
剣術を辞めたいと弱音を吐くと、母はそのような脆い心では世の中生きていけない、相手を言い訳にせず、自身の向上を考えなさいと喝を入れた。
戦後父は一般の企業に就職したが、上官時代のプライドの高さと硬い頭では馴染むことができず、孤立していた。武司は成長と共に時代に対応できない父を嫌うようになった。
更に、嘗(かつ)てのように外で下の者を動かせない鬱憤を晴らすかの如く、家庭内で吠え散らかす姿の醜悪たること、たいそう甚だしかった。
武司が剣術の訓練をサボれば夜中に何時間も説教し、拳を上げた。母にもきつく当たり、同じ被害者同士であるはずなのに、母が父を否定することはなかった。寧ろそれは横暴な父に加担しているのと同義であり、そのような母に対してさえ恨めしいと思った。高校に進学すると、剣術三昧だった武司は部活を楽しむ周囲を羨むようになった。
剣術も仲間と訓練するわけで部活と大差ないと父は言う。然し、一体感がまるで違う。剣術仲間と仲が悪かったわけではないが、目標はお互いに異なっており、各々が黙々と鍛錬していた。
一方で部活とやらというものは部員同士が堅い絆で結ばれており、一つの目標に向けて全員が同じ方向に翔けていくその輝かしさたること想像を絶するものである。
そのようなこと等、父が知る余地もない。人は本来生きていく中で思考を更新し、成長していくはずである。然し、自分の価値観に固執し続けては、人間としての価値が向上しないどころか、もはや退化すらしていることになるだろう。