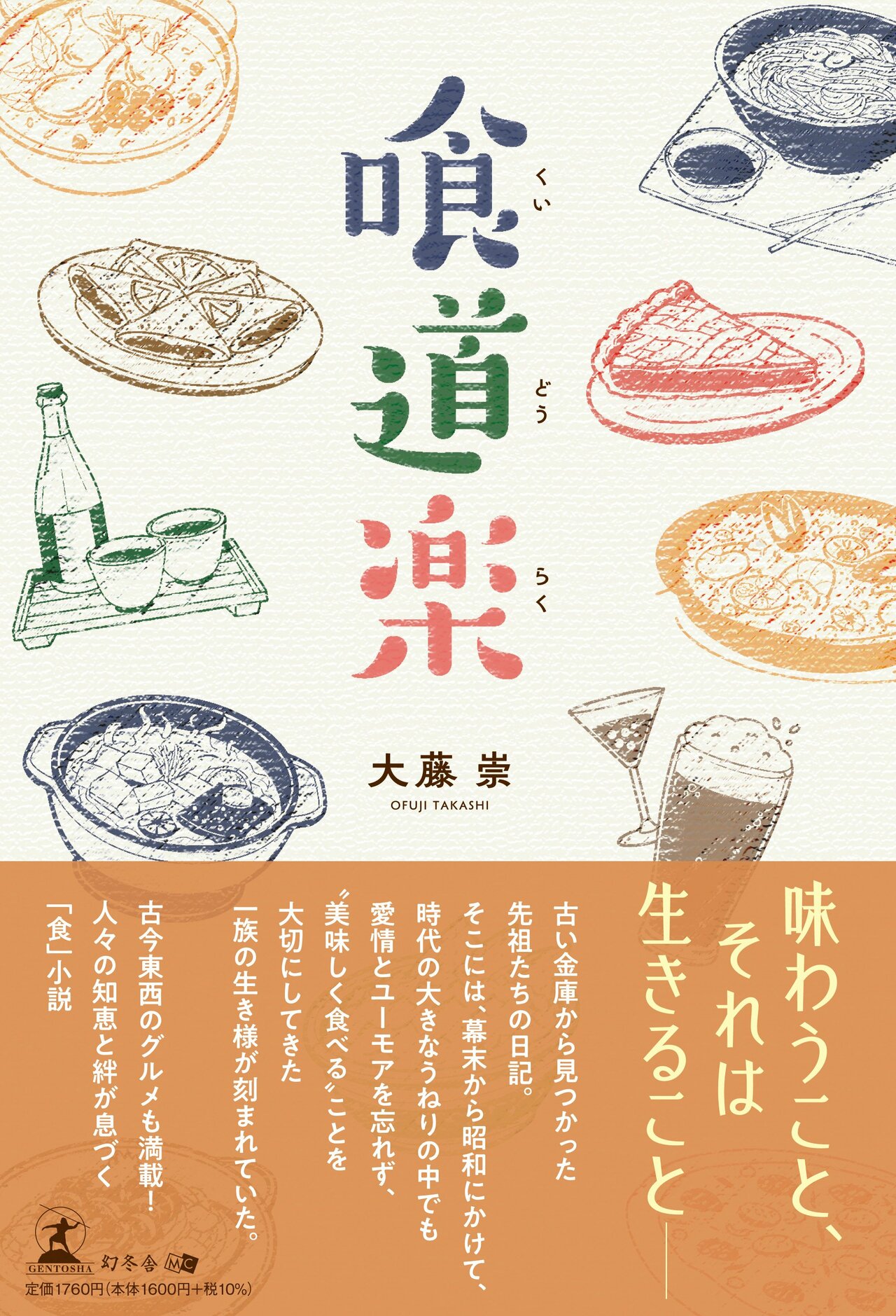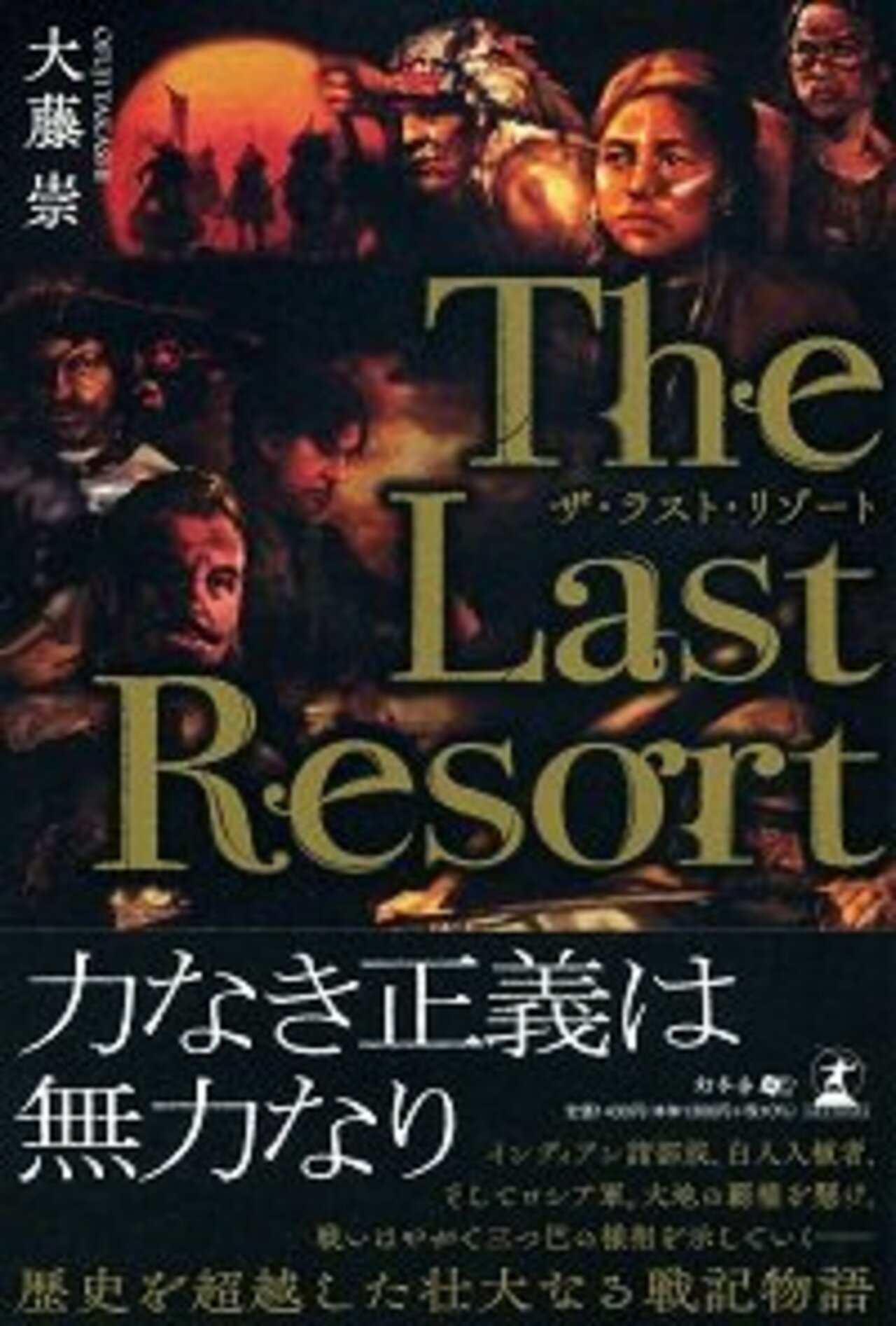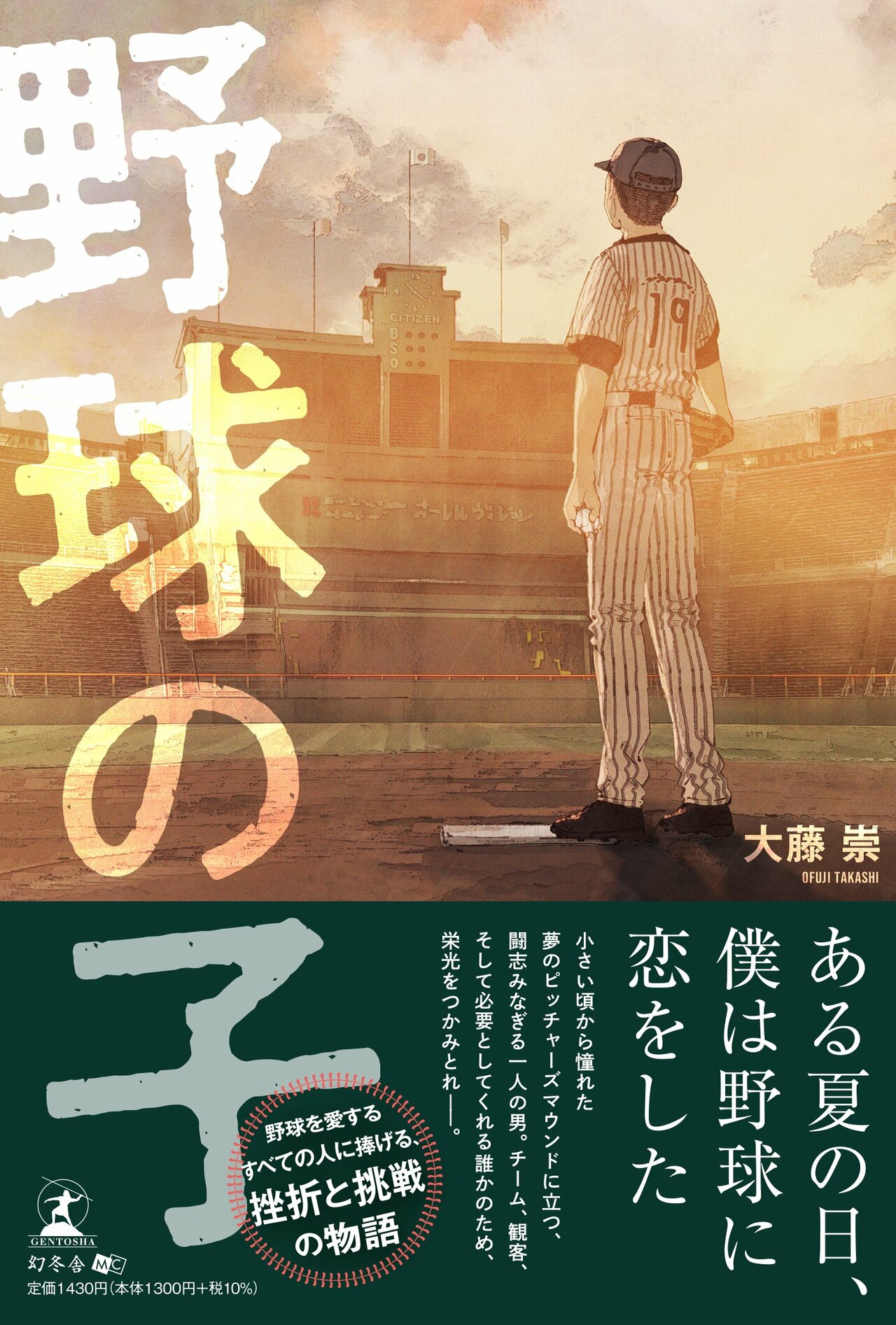さて牛鍋、いやすき焼きならば、ここ人形町には、誰もが知る名店がある。左程高くなく、味付けは関東風の濃いめ。嬉しいのは、特定の酪農家と契約していないことだ。
毎年、バイヤーが各地を訪れ、牛の品質を見て決めるので、味が落ちないという訳だ。うん、丁寧に物を作るというのは日本人の美点と思う。
新潟には、鮭の瓶詰で有名な店があるが、ここのバイヤー達は、東北に北海道、アラスカに北欧と、その年一番の鮭を追い求め、それを買い付けるという。
すき焼きは元々関西のものだが、あちらではまず最初に肉を焼き、砂糖と醤油で味付け、生卵と共に食べる。
福沢諭吉が大阪で学んでいた頃から、牛鍋屋がすでにあったそうだ。もっと遡れば、秀吉公の時代、小田原城を攻めた際に、武将の蒲生氏郷が、友人の大名達に、牛鍋をふるまったという。
氏郷公はクリスチャンでもあったから、宣教師の影響で、牛肉に抵抗がなかったのかもしれない。
そのすき焼き屋から程近い所には、鳥鍋の店がある。江戸時代から続き、文豪谷崎潤一郎も愛したとか。この店の鳥鍋も、すき焼きの一種だろう。
割り下には、砂糖と酒を一切使っていない。潔い味だ。生醤油とみりんのみで味付け、軍鶏を一枚ずつ焼き、温泉卵で食べる。
死んだ親父が好んだのは牛丼だが、これもすき焼きの変形だろう。具はほとんどかわらないし、生卵が付くのがその証拠ではないか。
私はかって、高村光太郎の有名な詩に魅せられ、モデルになった浅草のすき焼き屋に、当時の部下と共に行ったことがある。
その詩では、もうもうと煮え立つ、というフレーズが何度も何度も繰り返される。まさに食は命なりという感があり、食欲をそそる詩だ。その店に入店すると、人数分の太鼓を鳴らしてくれる。
古い木造で、明治に出来た店だ。その時代をそのまま体現したかのような造りだ。肉質も味もいわずもがな、無論旨いのだが、誰と食べるか、どういう状況かで味はかわってしまう。
【イチオシ記事】折角着た服はゆっくり脱がされ、力無く床に落ち互いの瞳に溺れた――私たちは溶ける様にベッドに沈んだ
【注目記事】「ええやん、妊娠せえへんから」…初めての経験は、生理中に終わった。――彼は茶道部室に私を連れ込み、中から鍵を閉め…