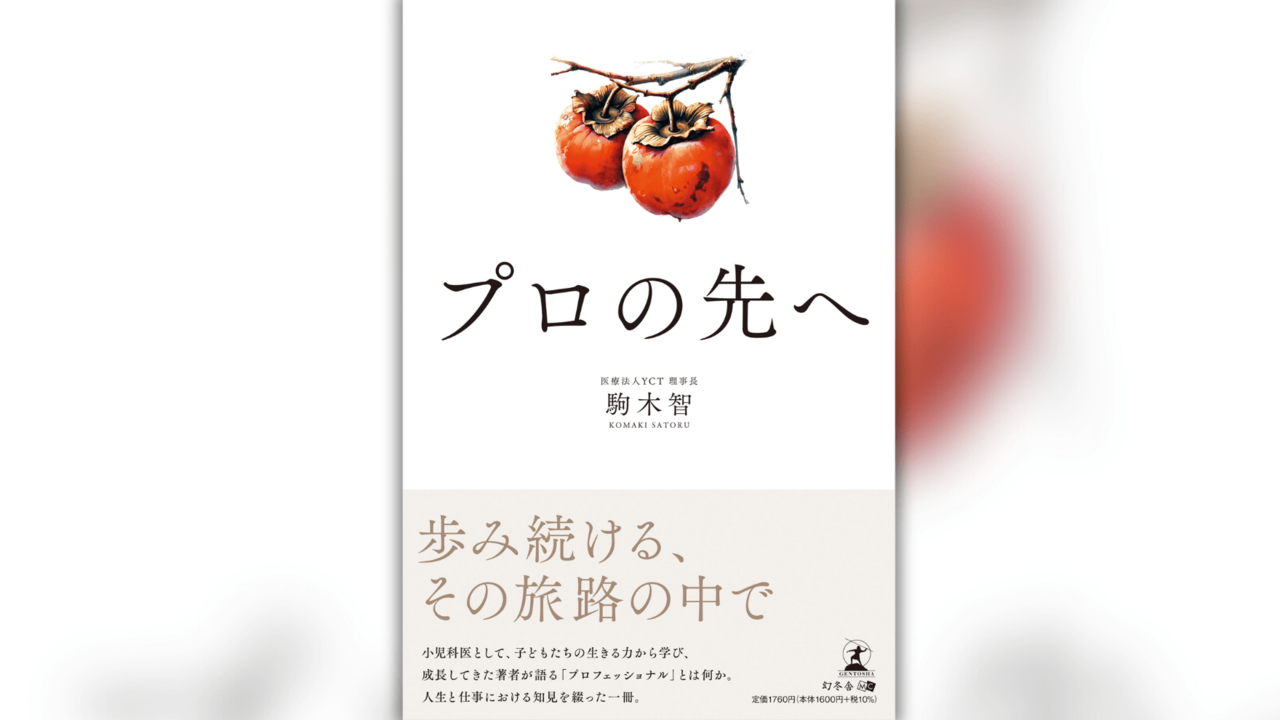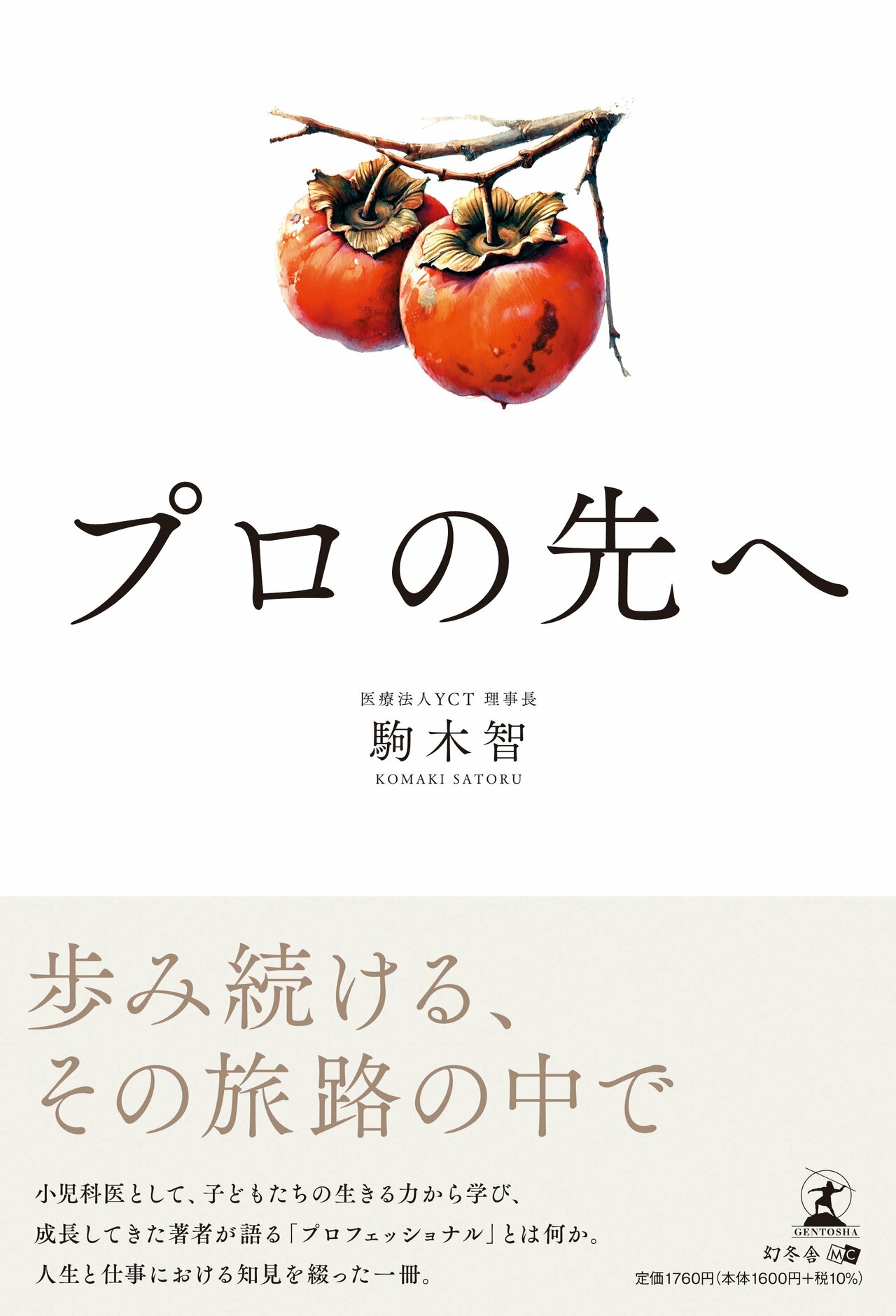【前回記事を読む】30年以上前、医師国家試験に合格し、ある日突然小児科医になってしまった。小児科医になりたての頃は患者さんと全然話もできず…
1 子どもは「生きる」プロ 〜小児科医になって子どもから学んだ生きる基本〜
問い1 感情
「診察中には赤ちゃんが泣いたり、検査では幼児に大暴れされたり、小児科では診察自体が大変そうですね。子どもさんの泣き笑いや怒りなどの感情表現って大人と違うんですか?」
喜怒哀楽の感情表出は、脳の大脳辺縁系の扁桃体という場所の神経細胞が頑張ってしてくれているそうだ。そこは本能行動や情動行動を司っていて、知性を司る大脳皮質よりやや原始的な脳なのだ。
子どもさんを診察して面白いのは、「泣き」も「笑い」も脳のとても近い場所で生じているという事が、実感としてわかる事だ。感情の表出として、これらは不快と快だけど、実はどうみても脳の中ではごくごく近場にありそうなんだよね。
例えばたまにだが見るからに不機嫌そうな親が、病気の子どもと一緒に診察室に入って来る時があって、そういう時は私も緊張してしまう。そしてその子どもさんの診察の最後になって、その不機嫌な親が「じゃあどうも、有り難うございました」といって笑顔を見せて帰ってくれる事は、なかなか難しい。
でも子どもだと、泣いているうちにすぐ笑い出すからね。「今泣いたカラスがもう笑う」の極致でね。これを見るとボクはとても楽しくなる。悩んで、泣いてもいいけど、別に笑っていたっていいよね。
ただ大人でもある、しくしく泣いていたのが、最後にちょっと笑いがでてきたり、こういうのも僕はとても好きだなあ。悲しくなっていたのが、ちょっと最後には笑ったり、逆に笑ったりしながら、最後に悲しくなってきたりとか、ね。
ちょっと知性がついてくると、悲しみは悩みになり、笑いは楽しみになる。
悩みも楽しみも大脳皮質の働きだが、子どもはまだ発達していないから、悩みも楽しみも大きな存在にはならないんだ。感情や知性の表出からみると、「泣き笑い」のもっと上層にある「楽しみや悩み」だって、ひょっとして大きな違いはないのではないだろうか。ちょっと悩みに対して大らかになれそうだ。
「泣き」も「笑い」も実は感情の表出という面では大きな違いはなくて、楽しみや悩みだって、他人がみたら同じにみえるかもしれない、という可能性は、長く生きる上で良い気づきになったと思っている。
もう一つ、幼児までの子どもは、怒りの感情が薄くて、怒ってもそれを維持できないんだ。1歳の子どもに注射すると、最初怖がって泣いて、実際の注射の時に大泣きして、でも10秒もすると、泣き止んで、手をふってくれたりする。この身軽さ! 痛くて泣くけれど、それが終わったら、手をふってくれるんだ。これは大人とは違う。
大人では「あの病院の看護師の採血はめちゃくちゃ痛くてさあ、もう行かないよ」などという声を聞くけど、子どもはそんな事はない。怒りとか恨みが持続できないというのは、まだ大脳皮質が発達していないからなのだけれど、時々は大人になっても維持したいものだなあ、と思っている。