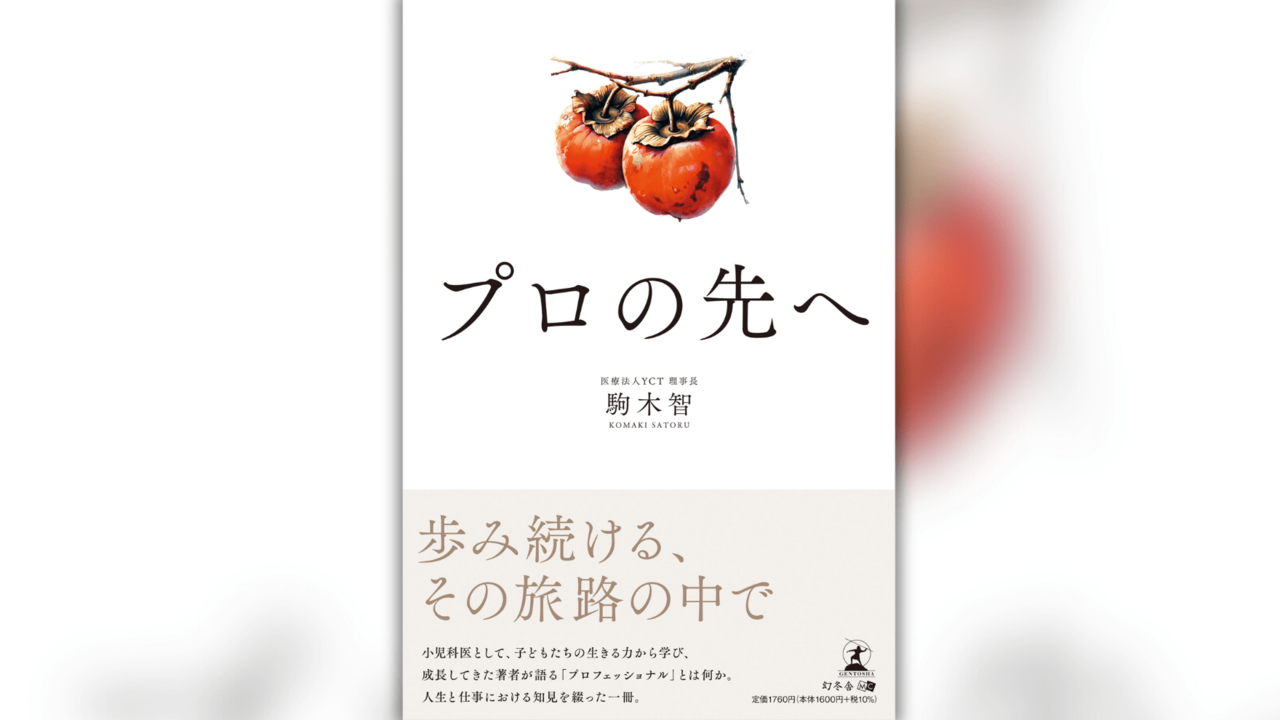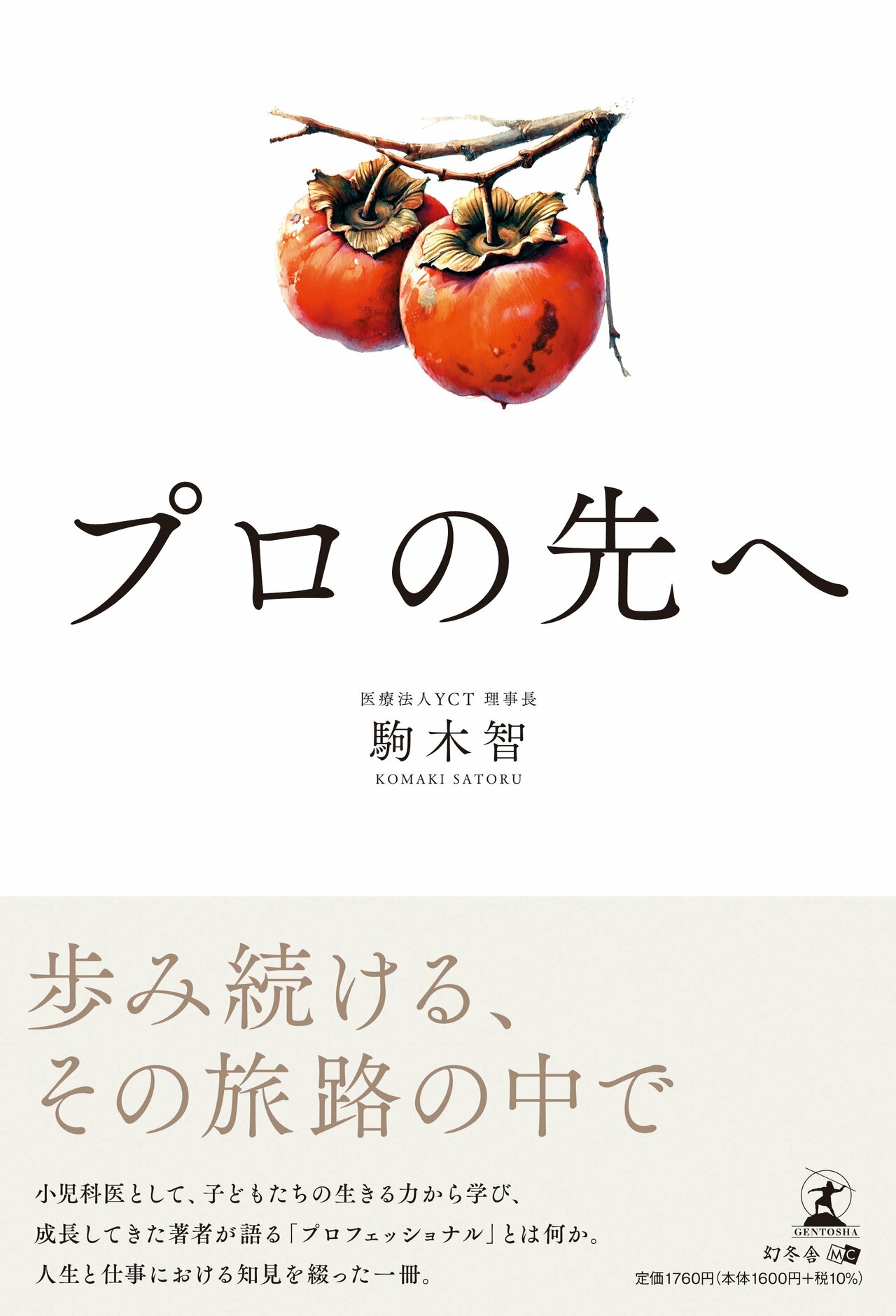【前回記事を読む】若い人に伝えたい。「他人と違う事を考えても十分生きていける」――小児科医になって、自分が生きていく上で子どもから学んだ事
まえがき 〜自己紹介〜
それで5年ぶりくらいに読み返してみたら、やっぱり良い事が書かれています。
でもやはり何にも残らないのです。これを読んだというだけで、プロになったという方はいないと思います。どうしてでしょうか。
答えとしては、プロは長年やって来たからだけあって、そのお話つまりエピソード自体はとても面白いのですが、まとめた金言はごくごく当たり前の事が書かれているだけだから。「すごいなあ」という事は、読者にとって、結局は想定内の事であって、長く記憶に残る事はありません。
年配のプロが、若い時の多くは失敗のエピソードを書いて、この時にこうしてプロになった、という感じ。でもどうしても「これは成功の後付け理由でしょ」という感じが否めない。
読者は、そこで「わかる」ということに対して満足感も得られるし、そうするとその本もよく売れるので、良いことなのでしょう。
ただ「わかる」事の確認では、単に忘却のための読書にすぎない。つまりおおかたの本というのはちょこっと読んで、忘れ去られるためにある、それは消費の為なので致し方ないのです。
ただ同時に「思い出す事」の喜びもあるので、読書はやはりとても良い事を含んでいます。この本では、常識のある作家の方とは違う形で、いつもと違う事を書き、その時に忘れるのはしようがないとしても、「何か変な事が書いてある」と気づいて、余韻が残り、5年後10年後にまた読んでもらえたらいいなあ、という思いで書きました。
長い間生きてきて、子どもの頃は表(おもて)しかないと思っていたのに、実際は裏が結構強いどころか、とてもとても強い事がわかりましたし、また「毒を喰らわば皿まで」、「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあり」、「清濁併せ呑む」などの意味がうっすらでもわかるまでに50年以上は経過しました。
それは自分でも他人と比べて理解が遅すぎると思ったりもするし、また逆にそれはそれでゆっくりわかって良かった気もします、要するに常に解釈は揺れ動くのです。
しかも私は「こうあらねばならない」と考えた事は、その時点で「間違っている!」と強烈に思っている人間ですので、こういう輩は説得力もない文章しか書けません。