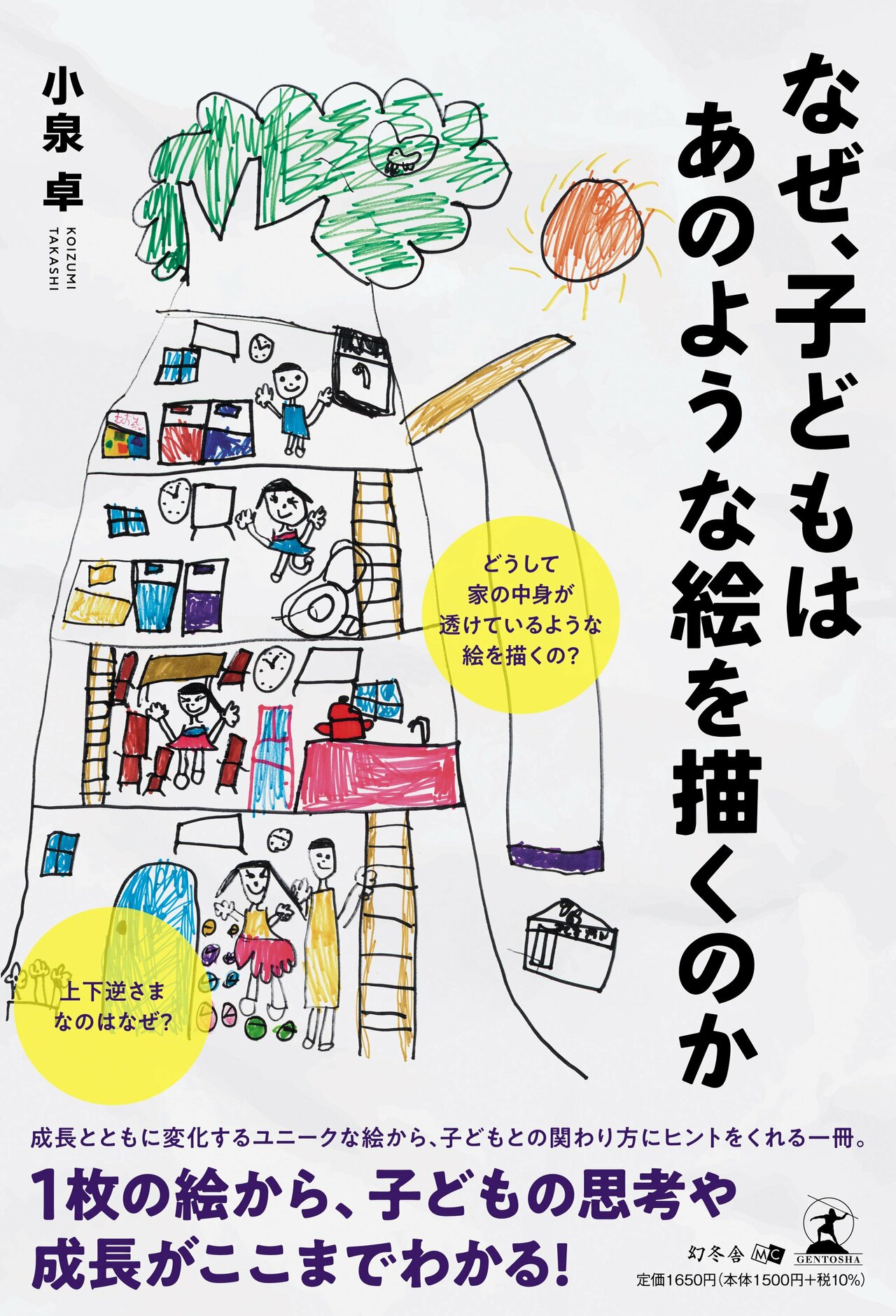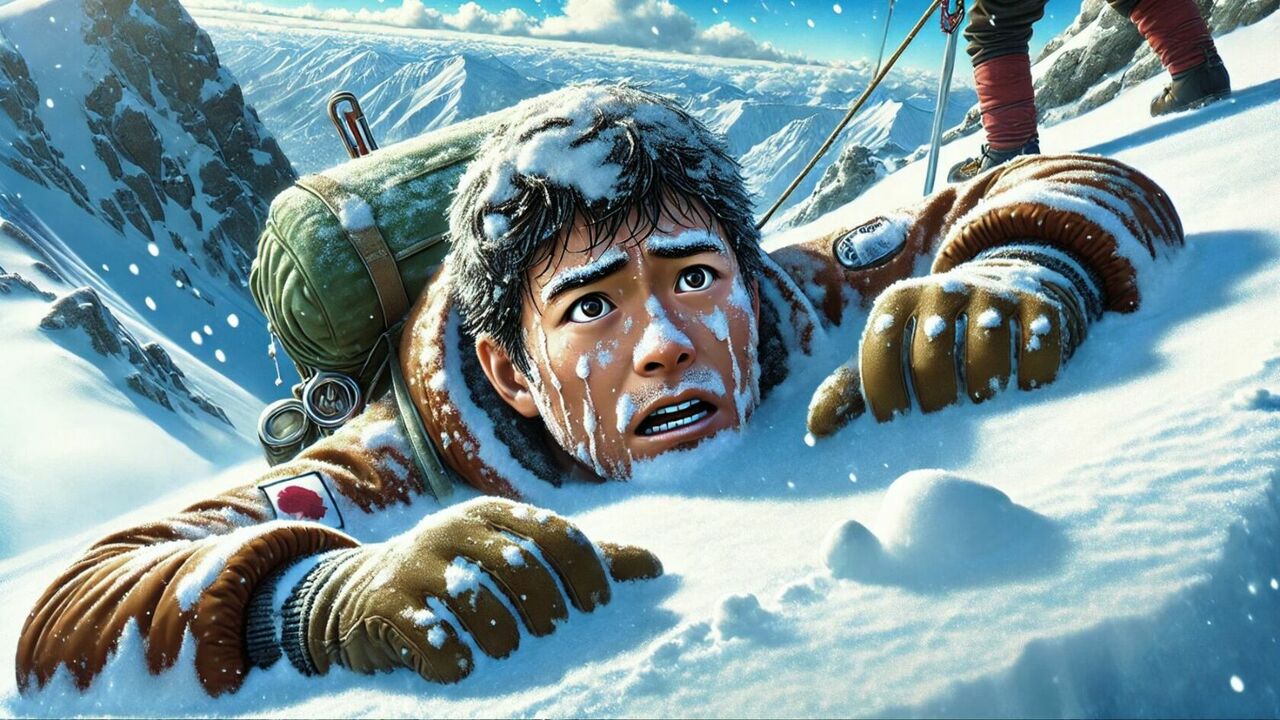②コミュニケーション
いつの時代も、幼児から高齢者まで、手を使い、人と話し合い、適宜な食事をとることの重要性は変わりません。さらに、手による活動は、大脳そのものを活性化させるとともに協同による創造活動を生む契機になります。それ自体、人間と人間、人間と自然、人間と芸術とのコミュニケーションの広がりや発達を生みます。
「コミュニケーションとしての芸術」と、アメリカのナショナル・スタンダード冒頭の「哲学的基礎と生涯の目標(1)(2014)」に書かれました。それまでの学校の美術は、描くことや作ることの表現に重心がありましたが、ここでは鑑賞の重要性が述べられています。表現と鑑賞は相補(そうほ)的な関係で相互に重要だということです。
鑑賞は、自らが表現を経験することでより深くなります。表現することは、他者からの応答(鑑賞、批評)を待ちます。そして見る人の心に作品への共感が生まれ、それが制作者に届いた時、その作品は完結します。表現する人と鑑賞する人がいて美術は成立しているのです。
スポーツは、最初、勝敗を決めることが目的でしたが、現在はどのスポーツも観客からの応援を強く期待しています。
応援を受けることが選手の背中を強く押してくれるのです。応援する人たちも、そのチームが優勝すると自分事のように歓喜し祝杯を挙げます。こうした両者の関係は、美術における表現者としての子どもと、鑑賞者としての親(周囲の人)との関係でもあります。
子どもは、なぐり描きをしているとき、最初は、描くことそれ自体を楽しんでいるのですが、やがて周囲の人からの温かい言葉をもらうようになると、描くこととともに周囲の人たちの自分の描画への共感を得ることも喜びになっていきます。親や周囲の人からの温かい言葉は、子ども自身の自己肯定感及び創造性を高めてくれるのです。
このように、手の活動は、生きること、コミュニケーションすること、創造することの基盤的機能を活性化し、同時に他者からの共感は、社会的人間的な能力を開示する、重要な契機になるのです。
(1)NCCAS,(2014),“National Core Arts Standards: A Conceptual Framework for Arts Learning”, Philosophical foundations and lifelong goals. https://www.nationalartsstandards.org/content/national-core-arts-standards,11/10.2018 p. 10.
👉『なぜ、子どもはあのような絵を描くのか』連載記事一覧はこちら
【イチオシ記事】折角着た服はゆっくり脱がされ、力無く床に落ち互いの瞳に溺れた――私たちは溶ける様にベッドに沈んだ
【注目記事】「ええやん、妊娠せえへんから」…初めての経験は、生理中に終わった。――彼は茶道部室に私を連れ込み、中から鍵を閉め…