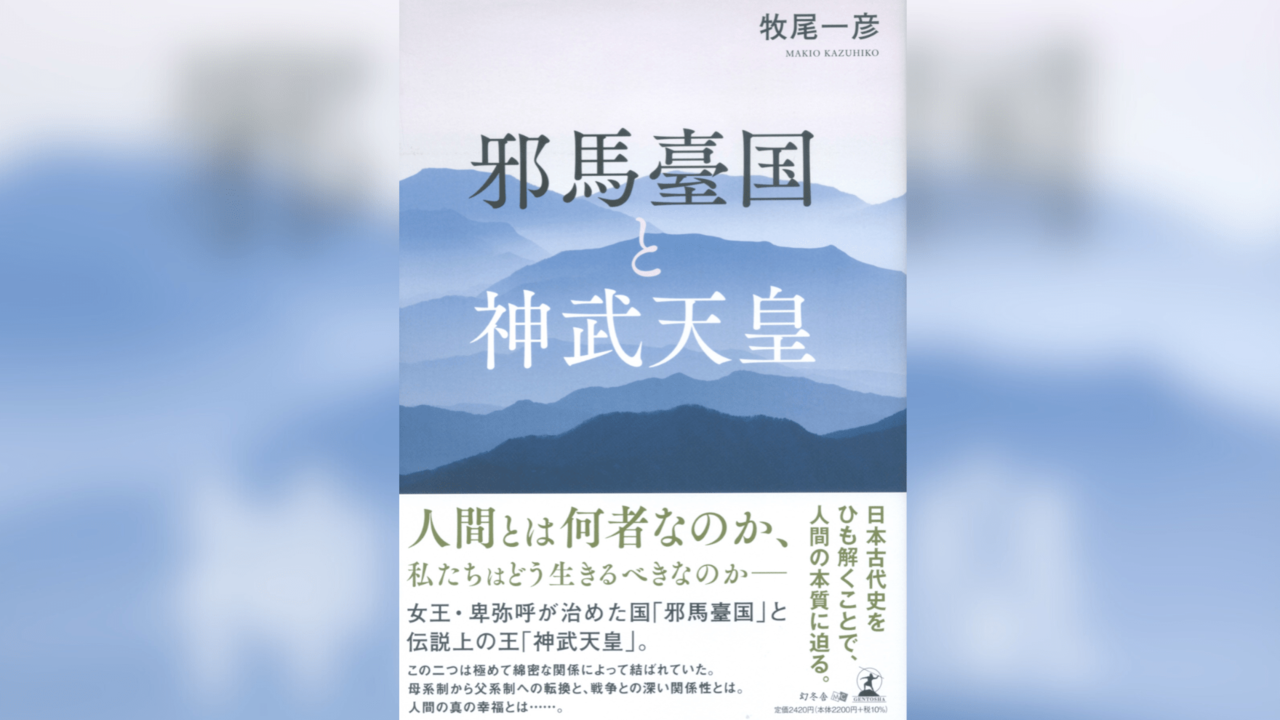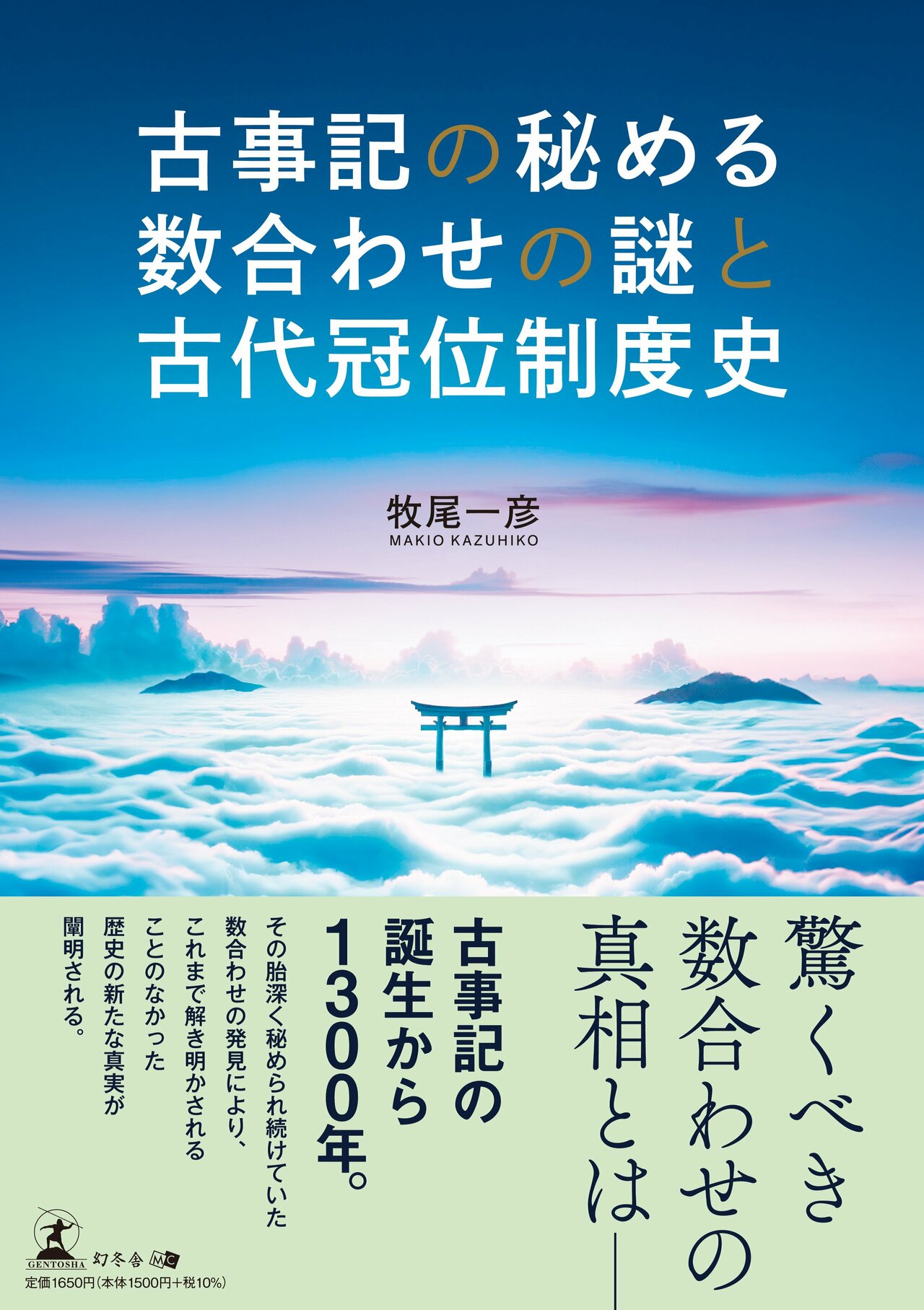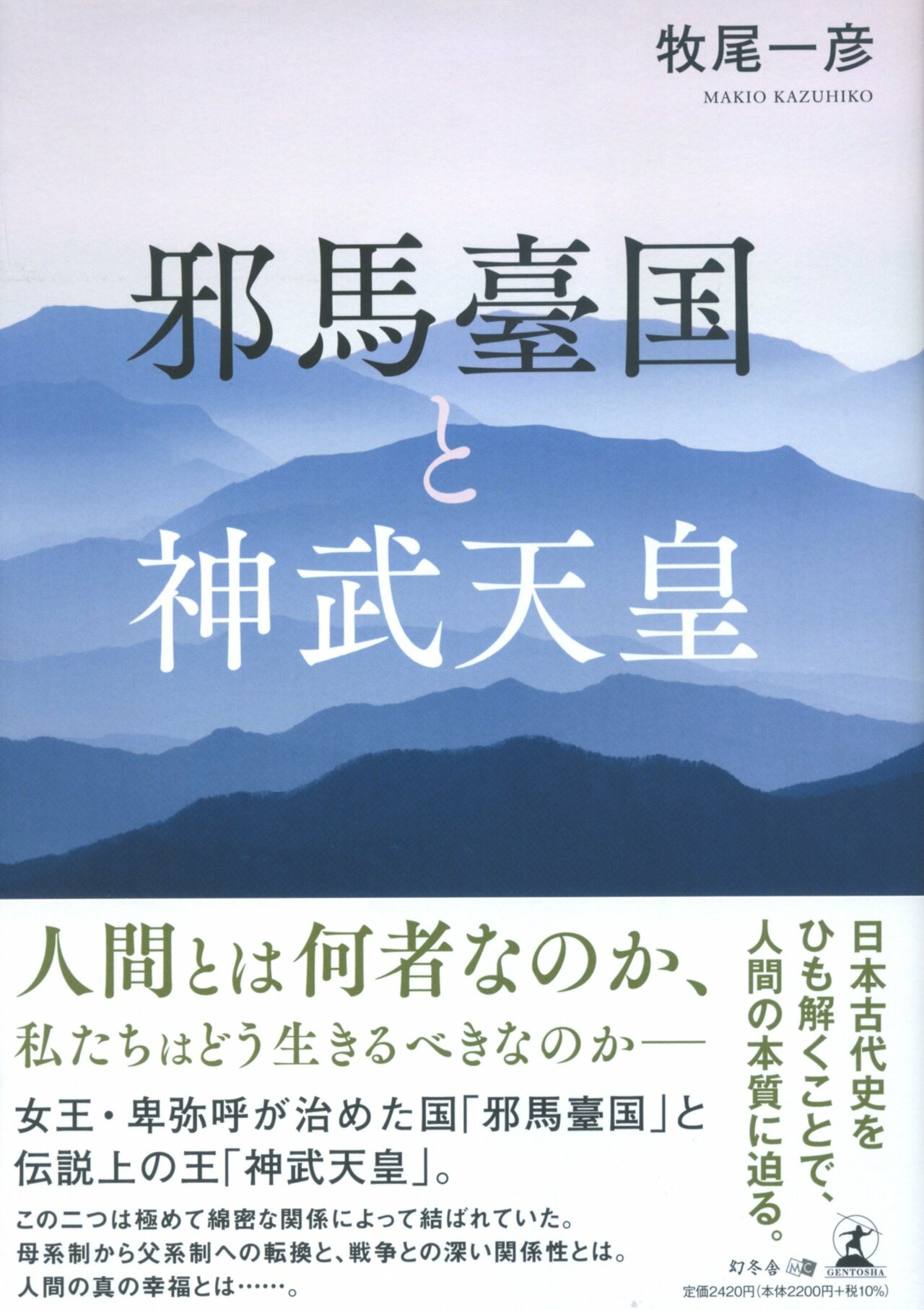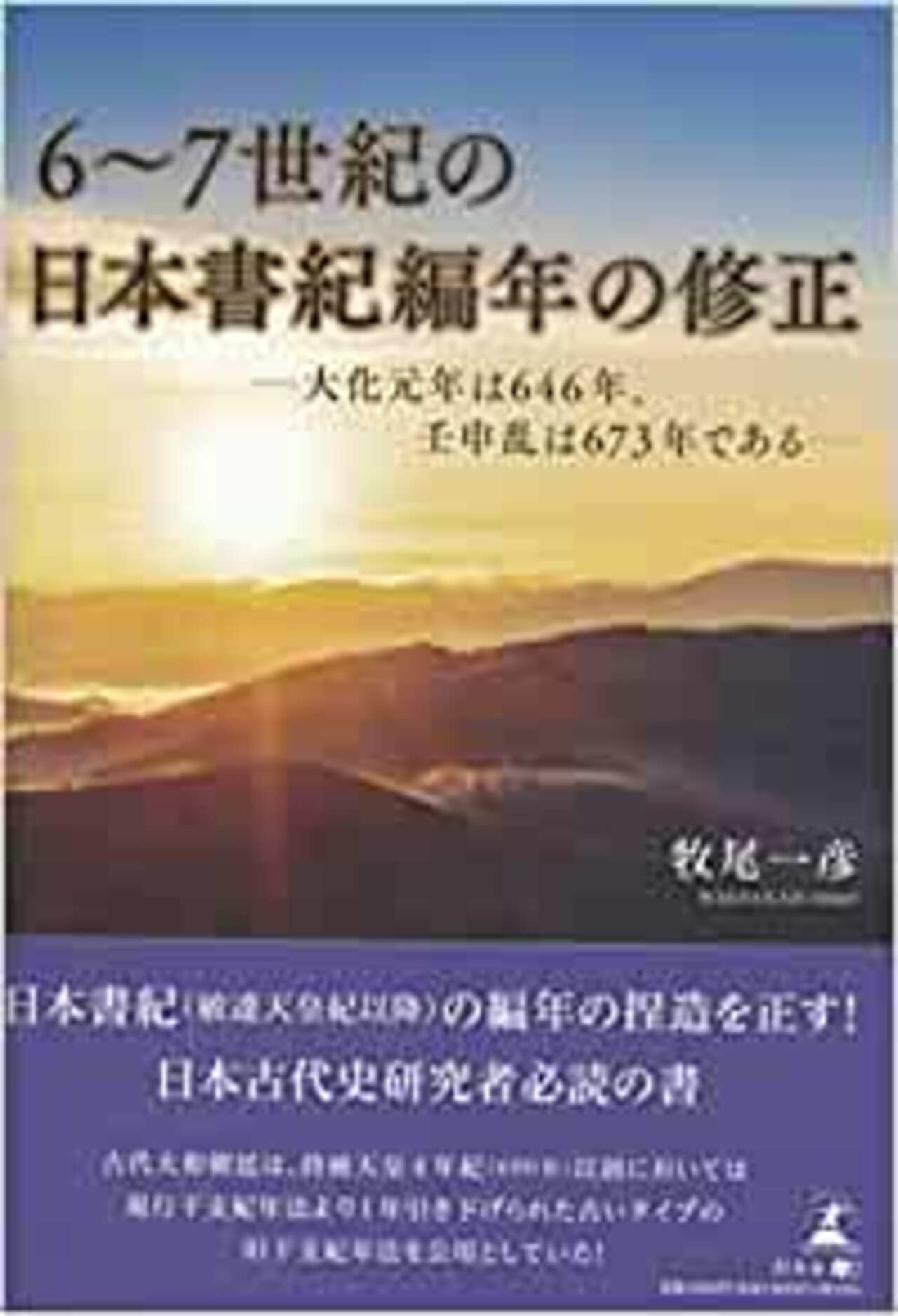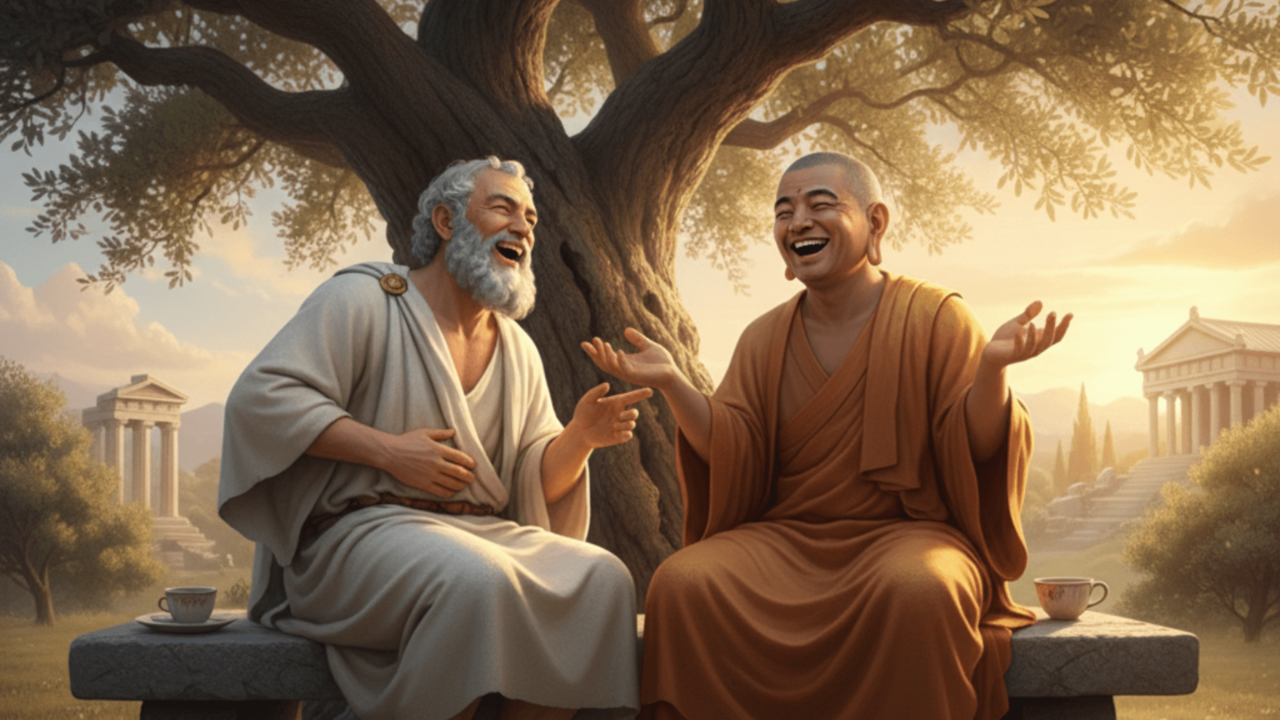【前回の記事を読む】戦争という、極めて非人間的な行為が、極めて人間的な事件として世界史に立ち現れるからくりにも、人間の本質が関わる
序論
第一節 日本古代史への動機とシャカムニの思想および母系制と父系制についての序論
人間存在に限らず、存在一般の本質は、存在する物それ自体にあるのではなく、存在と存在の間に横たわる、関係律という、目には見えぬ法則にある、と説いたのは、いまから二五〇〇年ほど昔に、中インドで活躍して原始仏教の開祖となった、シャカムニ・ブッダ・ゴータマ・シッダールタである。
シャカムニとは、シャカ族の聖者の意味。ブッダとは、目覚めたる人、聖覚者の意味。ゴータマは姓で、最上の牛の謂い。シッダールタは名で、大願成就の謂い。そこで、シャカムニ・ブッダ・ゴータマ・シッダールタとは、シャカ族の聖者にして目覚めたる人、ゴータマ・シッダールタさん、である。
以下、この原始仏教の開祖を、簡単に、シャカムニと呼ぼう。日本語で言えば、お釈迦様である。
当時、中インドに盤踞したシャカ族は、言い伝えによれば、古くは兄弟姉妹婚、族内婚を行っていた、最も古いタイプの、弱小な一部族であったようである。後代の文献に、当時シャカ族は、犬や野狐のように自分の妹たちと夫婦になるものの末裔だといって罵られたと伝えられている。
兄弟姉妹婚を婚姻制度とするこの古い家族形態を、民族学では血縁家族と呼ぶ。シャカ族も、古くはこの血縁家族の状態にあり、これが後世的な批判を受けることになったものと思われる。
しかしそのシャカ族も、シャカムニの頃には、すでに族外婚を行う父系制の段階に達している。
血縁家族時代から父系制時代に至る中間に、母系制時代を挟んでいたはずであるが、その時代の記憶は、歴史の狭間に消えている。あるいは、シャカ族は、周辺の、すでに父系制段階に達していた強力な部族の影響の下で、長期の明確な母系制時代を経るまもなく、父系制習俗への同化を余儀なくされていたのであったかもしれない。
当時シャカ族を取り巻いた環境は、戦乱の世であった。コーサラ国、マガダ国、ヴァンサ国、アヴァンティ国など十六大国と呼ばれる、大小の父系専制君主国が林立し、互いに侵略戦争による離合集散を繰り返していた時代である。
これら十六大国中に数えられることもなかった弱小のシャカ族が、こうした環境の中で、部族の族制をはやばやと変容させざるを得なかったとしても、むしろ当然の成り行きであっただろう。
シャカムニの母マーヤーは、シャカ族の東隣に住むコーリャ族という、シャカ族の胞族、すなわちシャカ族と互いに姻戚関係にある近親氏族から、シャカ族の王家の妻に迎えられるという、父系制下での族外婚をしている。
マーヤーは、結婚後、出産のため、みずからの出身地、コーリャ族の地に帰る途中で、シャカムニを産み、七日の後に、他界したと伝えられている。出産を出身部族の地で行うのは、父系制といいながら、なお母系制的要素が残遺していたことをうかがわせる。