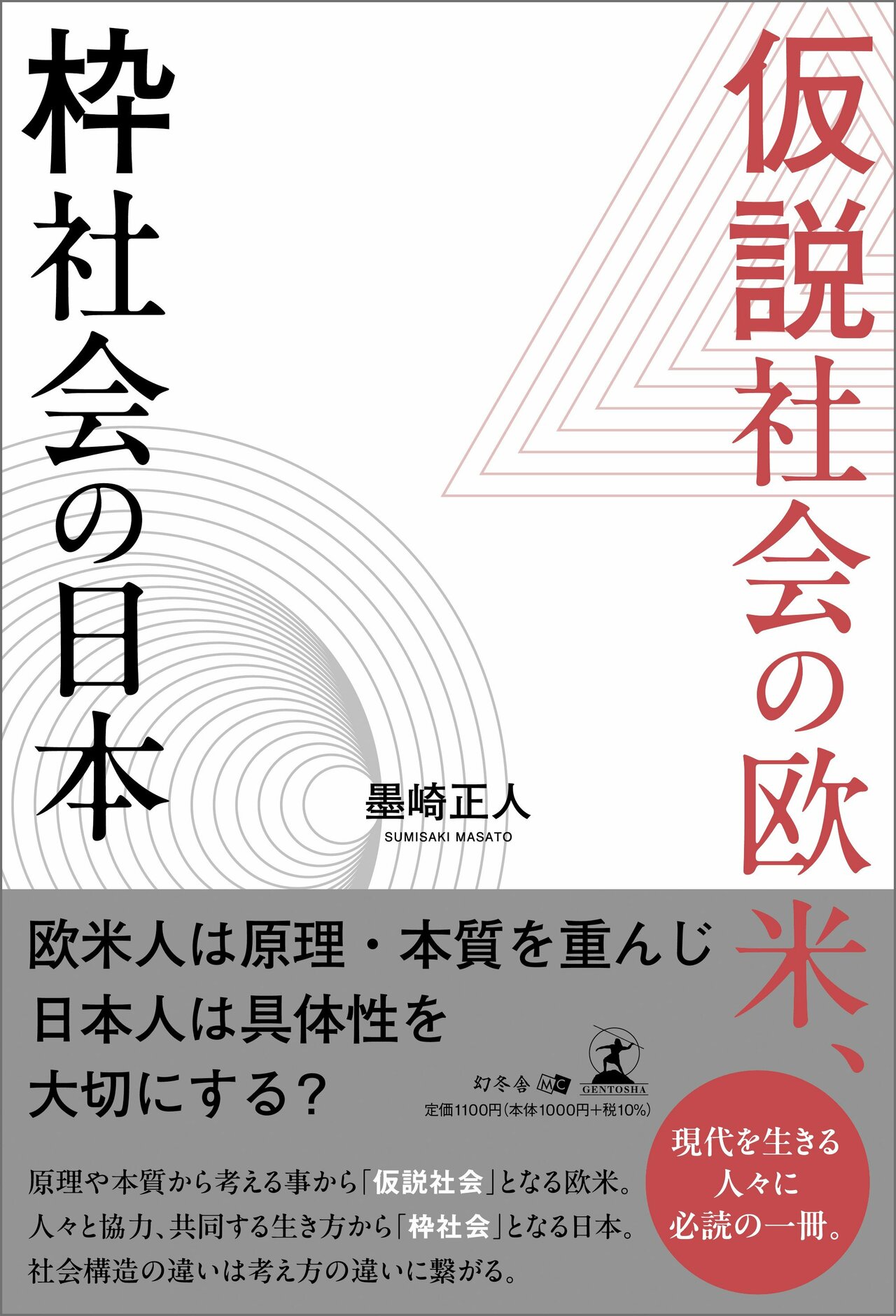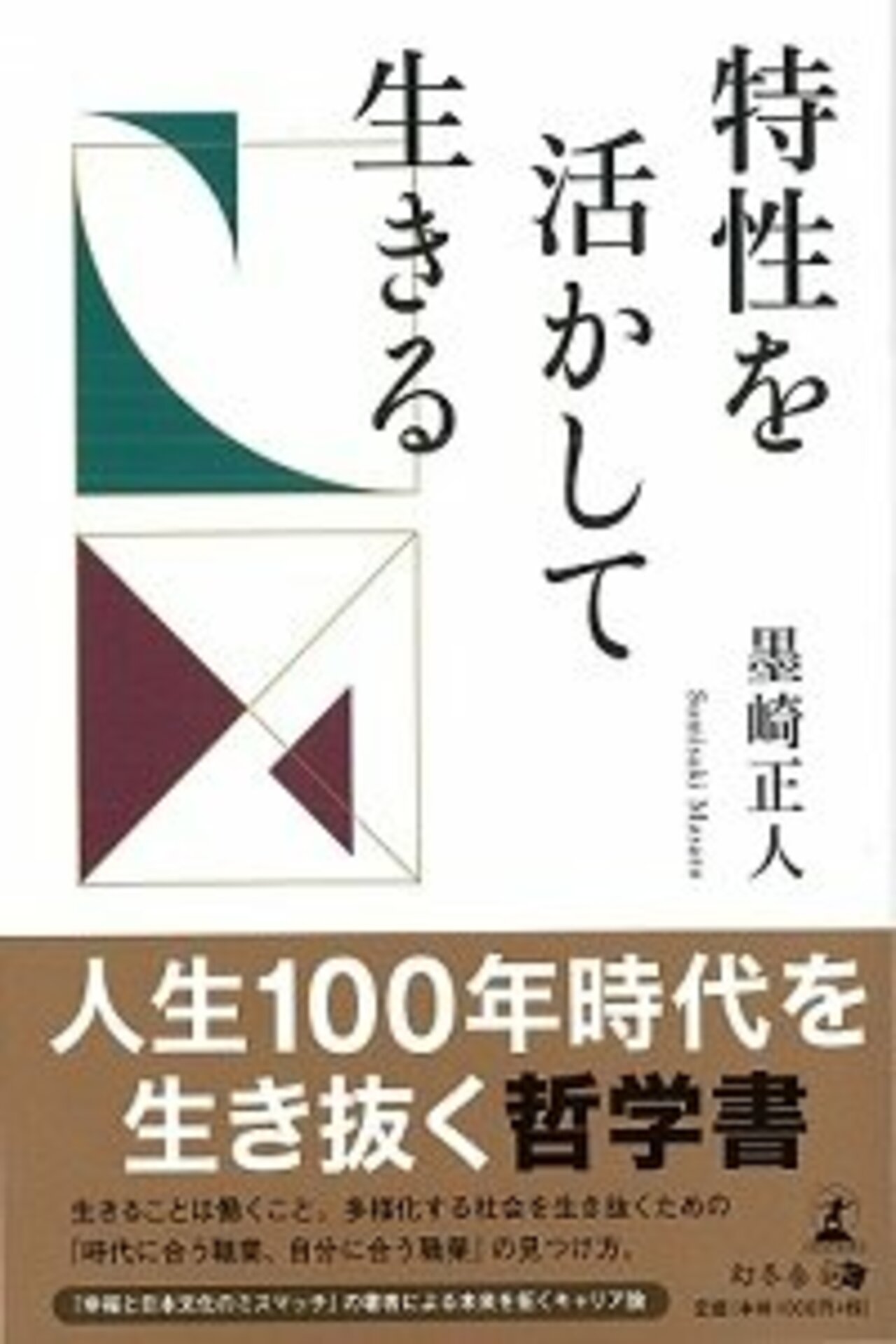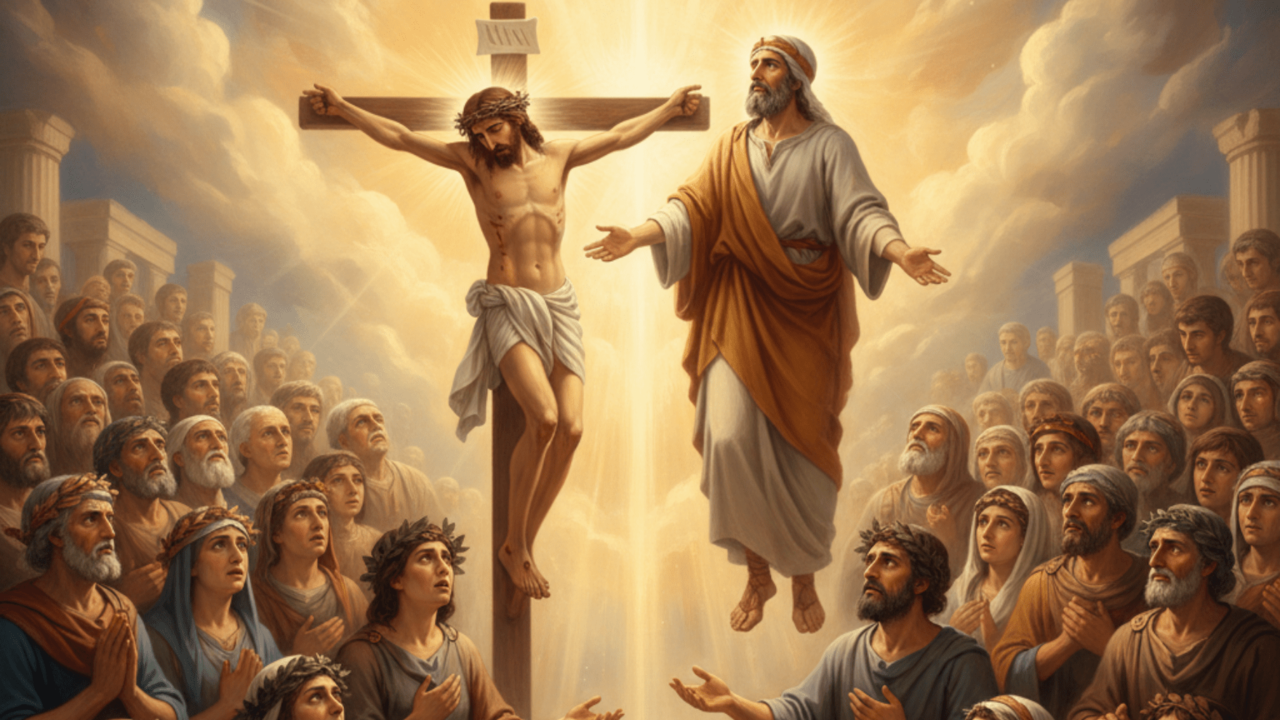固有の地政学から発想するロシア その②
人は元々与えられた環境から抜け出す事が難しい処があります。人は親からの躾や育った家風に縛られて生きています。国や民族も同じ事が言え、人々は伝統や文化に従った生き方になります。
これを日本の例にして話をしてみますと、日本は昔から狭い国土に四方を海に囲まれた海洋国家です。米作りに精を出した日本人は、周囲に枠を設け、枠社会、絆文化を形成して生き抜いてきました。
周囲を海で囲まれた狭い国土で生き抜いた日本人は、その分自国の文化や歴史、そして領土に敏感になり、他国に対抗した生き方になります。
ロシアは、昔から広い国土を持っていた事から地政学に沿った、守りの姿勢で生き抜いてきました。国土の広いロシア、逆に国土を海で囲まれた狭い海洋国・日本。双方は国土が広い、狭いの違いがありますが、領土に関してロシアと日本は、地政学で敏感な処があります。
自国の領土は、基本的には親から受け継いだ土地や建物の延長線のような処があります。だが、領土は個人的なものでなくその国の文化や歴史等の要因が絡む事から土地や建物より収拾が困難な代物となります。それを反映してどの国も領土には敏感になる処があります。
日本の領土である北方二島は、ロシアから見るとほんの僅かな面積の島です。日本はその返還を求めてロシアと地道に交渉を行っていましたが、交渉の進展が上手くゆかないのは、ロシアが固有の地政学に固守する事が原因になっています。
ロシアは寒冷地乍ら広い国土を有していた事から、昔から周辺国へ色々と気配りをしつつ一方で領土拡張を行うロシア独得の「二面作戦」で生き抜いていました。
だが、最近のロシアは技術革新により自国が世界一の穀物産出国になり、加えて豊富な資源が埋蔵されている事が分かり、ロシアはいま迄の守りの地政学を脇に置いてウクライナ侵攻のような強気の外交に転じています。
プーチンロシアは、新しい環境を背にして強気の外交を行っていますが、ウクライナ侵攻の成果が思わしくなく、自らを厄介な状況に追いやっている感があります。
次稿でプーチン大統領の率いるロシアの実体は、新しい考えや理念でなく、相も変わらず旧来の二面作戦の地政学でウクライナ侵攻を行っている様を、経済を絡めて説明してみたいと思います。