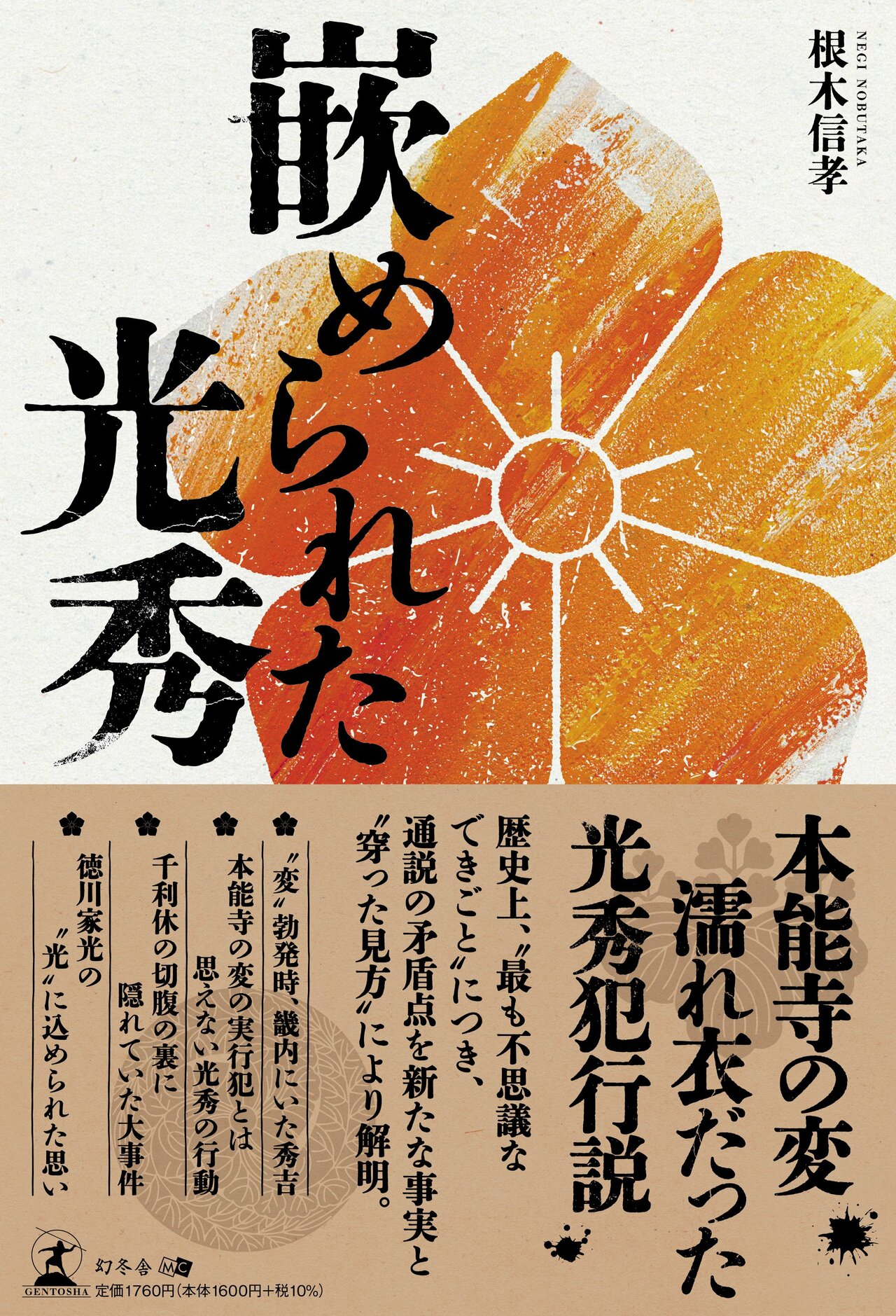2 本能寺の変以降の千宗易(利休)の異常な台頭
本能寺の変の4年後の天正14年(1586年)、島津から圧迫を受けた大友宗麟は上京して秀吉の弟の秀長に会って救援を求めた。その際に秀長から、「内々は宗易に、公儀は秀長に」と言われている。
秀吉には信長に仕えて間もない頃から秀吉に命を預け、秀吉の手足になって一緒に戦って来た家臣や、知恵袋といわれる黒田官兵衛など、有能な家臣が大勢いる。
それなのに、いかに信長の茶堂を務め、茶の道では名が通っているとはいえ、あるいは、ひょっとしたら秀吉と物凄く馬が合ったとしても、たかだか茶人の宗易が弟の秀長と並んで扱われたり、天下人である秀吉に対して発言力があるなど、通常ではあり得ない。
このことから、秀吉は千宗易に物凄く恩に着るようなことをしてもらったか、弱みを握られていたに違いない。
信長は備中の高松城に向けて出発する直前に急遽(きゅうきょ)本能寺で茶会を開いた。その目的は楢柴肩衝(かたつき)の入手だが、『信長の誤算』(井上慶雪氏著)は次のように書かれている。
信長はその名物狩りですでに『初花(はつはな)肩衝』と『新田(にった)肩衝』という大名物茶入れを所持していたのだが、この『楢柴肩衝』を入手すると天下の三大・大名物茶入れが揃うことになり、まさに信長の垂涎(すいぜん)の的(まと)の茶入れだった。
【イチオシ記事】添い寝とハグで充分だったのに…イケメンセラピストは突然身体に覆い被さり、そのまま…
【注目記事】一カ月で十キロもやせ、外見がガリガリになった夫。ただ事ではないと感じ、一番先に癌を疑った。病院へ行くよう強く言った結果…