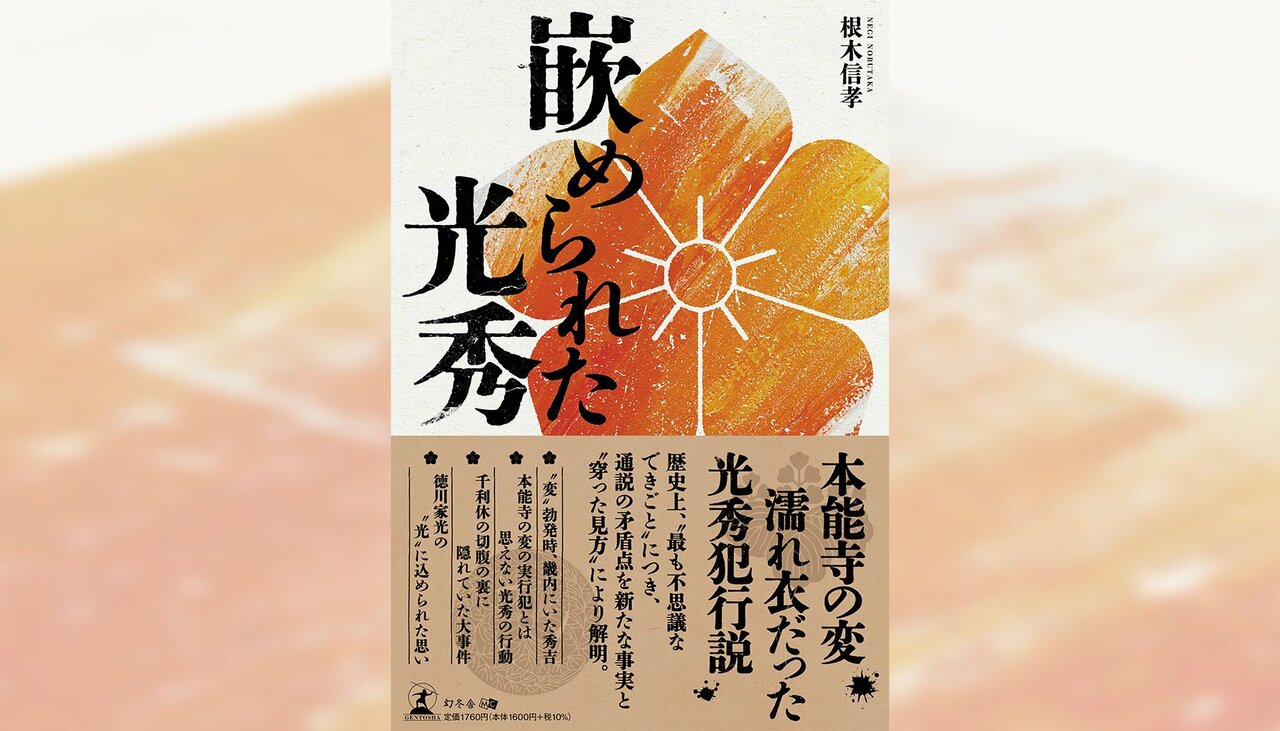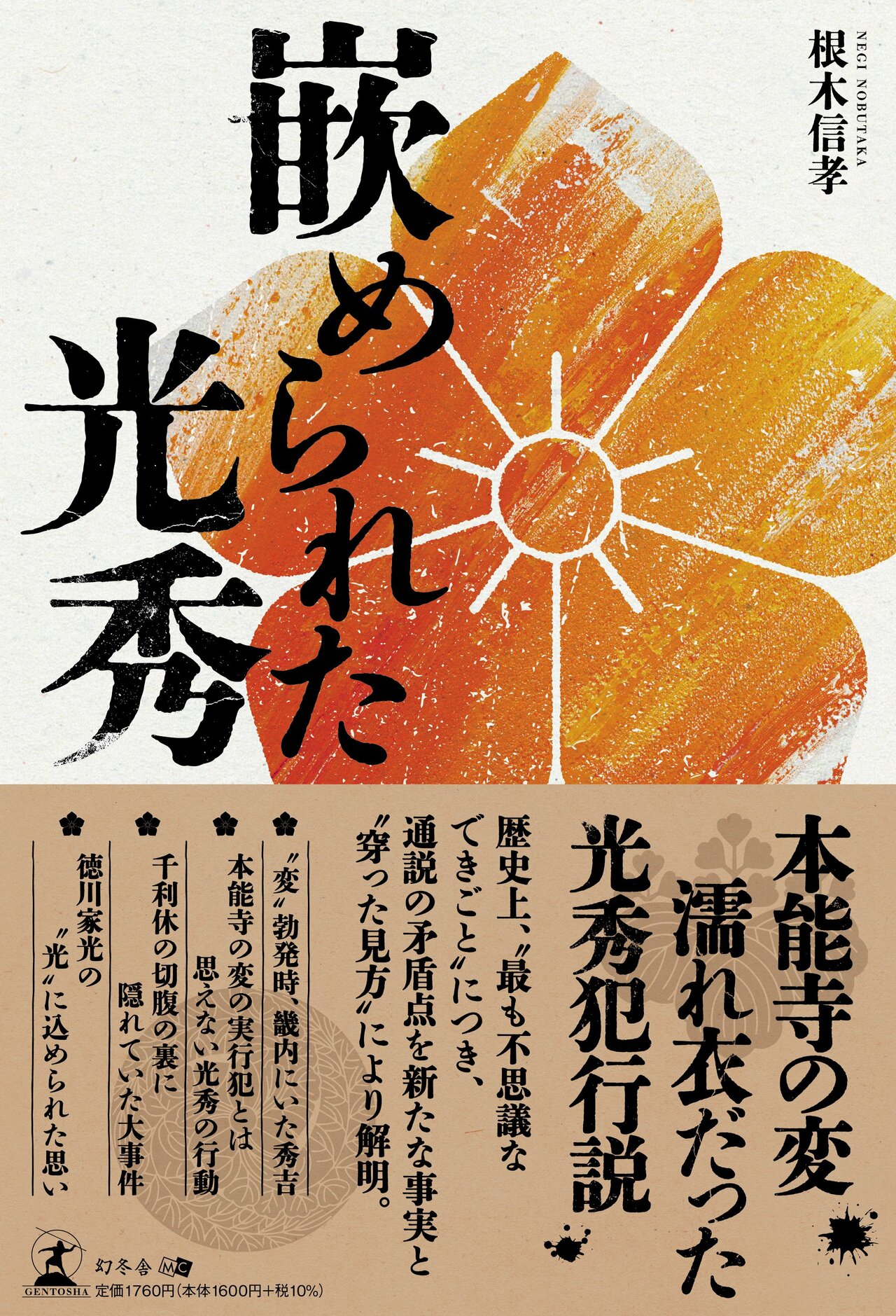【前回の記事を読む】本能寺の変に千宗易(利休)の影? ただの茶人が異例の出世を遂げた理由
第一部
4 本能寺の変が光秀の犯行だとするには不可解な秀吉に関する事象
2 本能寺の変以降の千宗易(利休)の異常な台頭
この「本能寺茶会」は元々、松井友閑が記すように、「天正十年正月二十八日に上様、名物茶器を持たれて上洛され、博多の宗叱(宗室)に見せさせられるべき茶会」だったが、俄(にわ)かに持ち上がった極秘の武田家攻略策戦のために中止になった茶会の、あくまでも再燃に過ぎなかった。
島井宗室が五月中旬から京都に滞在しており、六月初旬には博多に向けて京を立つ旨の情報が、千宗易(利休)から信長の許にもたらされた。
宗室在京のこの機を逸したら当分の間「楢柴肩衝(かたつき)」入手の機会が遠のく、という焦りがあり、何としてでも宗室に会いたい。
そのため、信長の御茶堂の一人、千宗易から島井宗室に連絡を入れさせ、「六月一日なれば、上様の御館に参上仕つる」との確約を得たのであろう。
この千宗易からの情報が基で信長が備中に向けて出発する直前に本能寺で茶会を開くことになり、安土城の外に宿泊したために賊に襲撃されたのだ。そのおかげで主君の信長がいなくなり、秀吉は織田家の中で台頭することができ、やがては天下を治めることになったのだ。ここまで千宗易が意図したかどうかは別にして、秀吉から見れば天下取りの最大功労者だ。
これが理由で秀吉は千宗易に頭が上がらなくなったとしても不思議ではない。そして、これが理由で、千宗易が自身の考えや嗜好(しこう)を主張したり、自身の像の股下を秀吉にくぐらせるようなことをしたのではないだろうか。
3 本能寺の変前後の早すぎる毛利との和睦
秀吉は6月2日早暁(そうぎょう)に起きた本能寺の変を3日に聞き、その日のうちに高松城主清水宗治の切腹を含む案で毛利と和睦したと伝えられているが、この和睦がとんでもなく早過ぎるのだ。
もし、秀吉が本能寺の変を3日に知ったとしても、それは3日の夕刻のはずだ。そうであれば、秀吉が毛利方に和睦案を提示できるのは4日朝であろう。そうなると、輝元が吉川元春と小早川隆景をすぐに呼んだとしても彼らが輝元の元に到着するのは4日の夕刻。それから和睦案の協議が始まる。
毛利家は毛利元就(もとなり)の子の隆元が早世したため、孫の輝元が幼くして国主となり、これを元就の子であり輝元の叔父である吉川元春と小早川隆景が二人で補佐し、政治・軍事はこれらの面々が合議で進める体制だった。こういう体制だと何かをする時や決める時はこれらの面々が協議しなければならず、国主が単独で決めることができる場合に比べてはるかに時間がかかるのだ。
加えて、毛利輝元は毛利家に忠節を尽くそうとする清水宗治を惜しみ、切腹させることに猛反対していたし、輝元の2人の叔父の兄の方の吉川元春は秀吉との決戦を主張していた。そんな中で4日に出された清水宗治の切腹を含む秀吉の和睦案に、毛利方が受け取ったその日のうちに和睦に応じるなどあり得ないのだ。4日どころか5日になっても合意には至らないだろう。
つまり、秀吉と毛利方は本能寺の変以前から和睦の内容=妥協案について調整し、和睦が成立していたと考えなければ、5日に高松城主清水宗治が切腹する結論に達するのは無理なのだ。