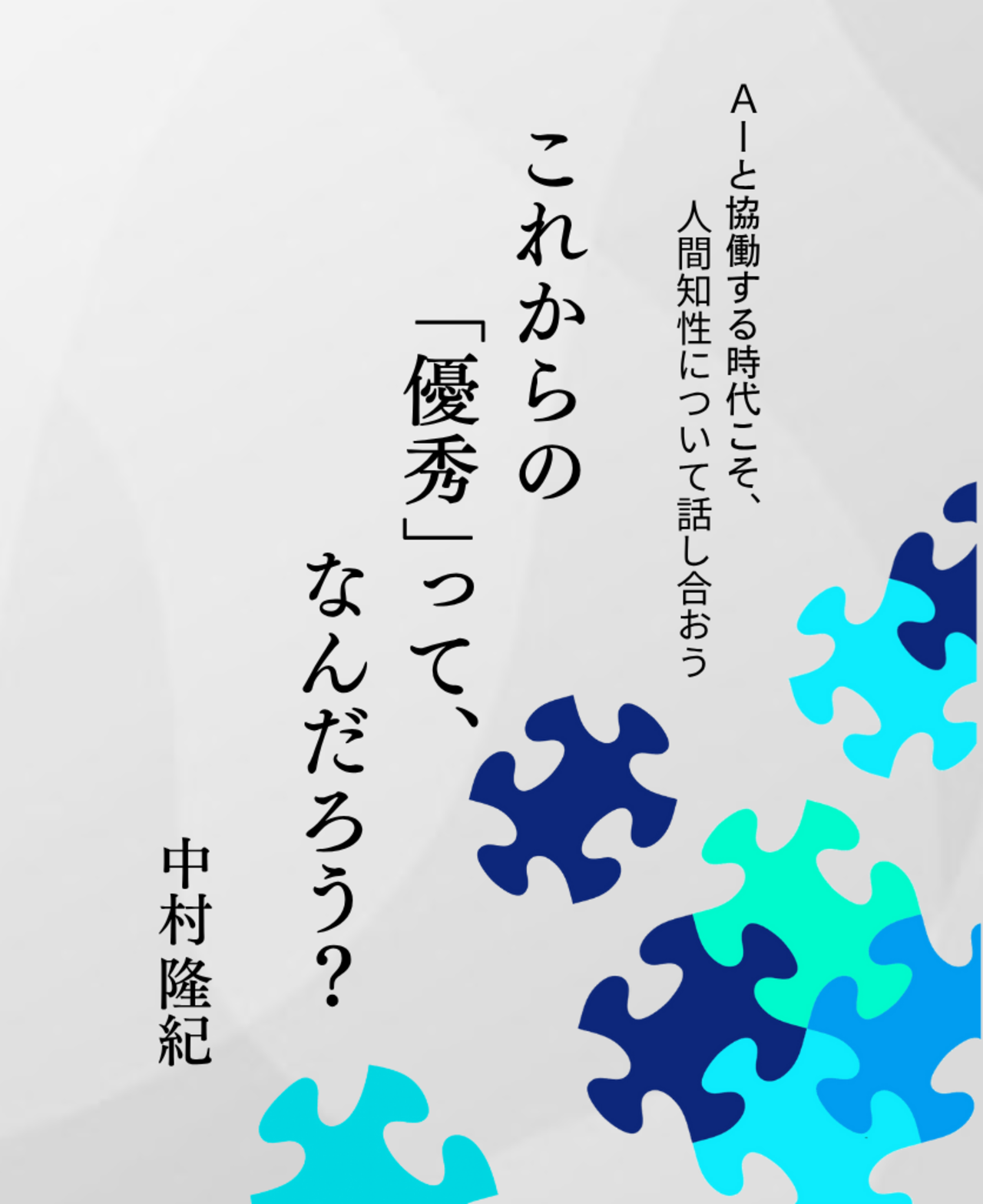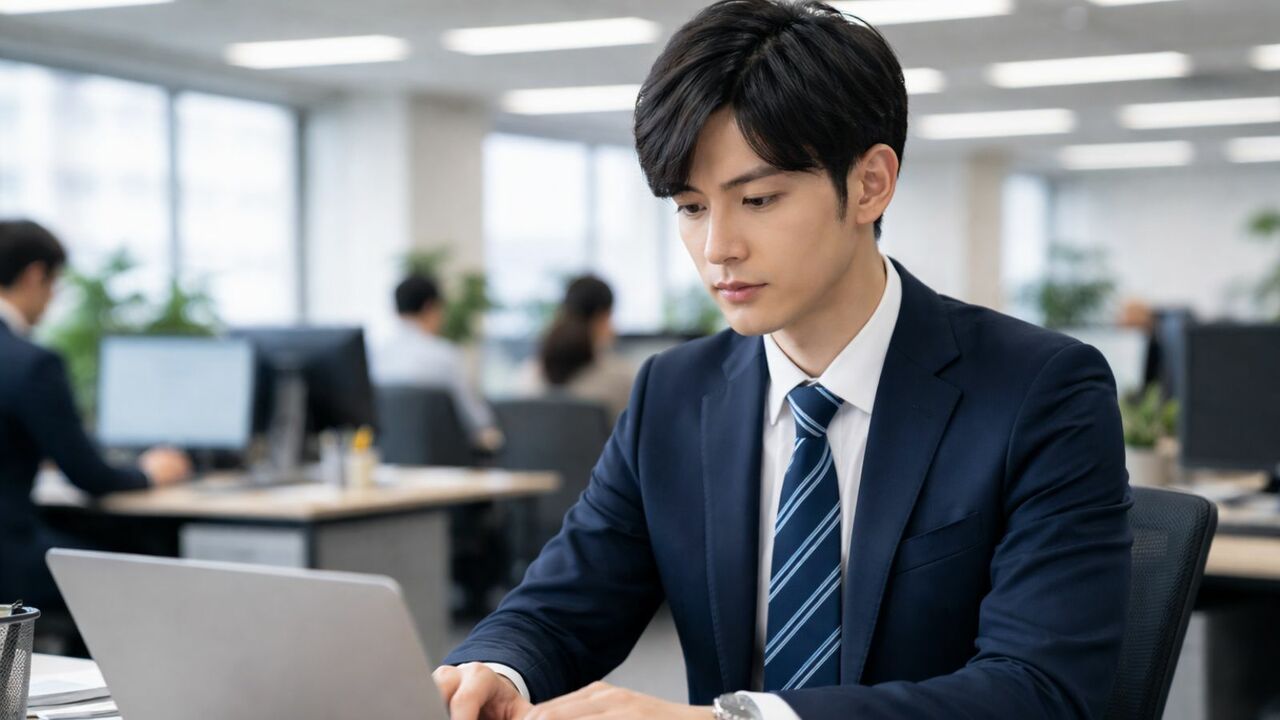[② 知覚をまるごと使う] モーリス・メルロ=ポンティ(1908~1961)
『知覚の現象学』モーリス・メルロ=ポンティ著
『メルロ=ポンティ読本』松葉祥一・本郷均・廣瀬浩司編
『現代思想~総特集メルロ=ポンティ』2008年12月臨時増刊号 より引用編集
■私たちの身体は物体であり意識であり、両義的に知覚する存在であり、身体が環境と関わりながら、世界と、そこに生きる自分の意味を探し続けている。
■私たちは、見る・聴く・触れるといった多様な感覚器官で知覚するが、中には「目の端でとらえる」「なんとなく聞く」といった意識的でない知覚も伴い、また、人の表情やしぐさなども感知し、その総体で時間や空間、まわりの人との関係などを認識している。
■知覚世界は、すべての知識や認識・科学や学問が生まれる源泉であるはずだが、私たちは効率を求めるあまり、つい忘れがちになる。たとえば森や草原や山河という風景を地理学の叙述や記号に抽象化した場合、もともとあった豊かな風景から感じた知覚も捨てられてしまう場合がある。
(顧客調査からデータを分析する場合、調査しなかった事柄への顧客の想いは集計上にないのだが、データを「顧客の心理全体」と思ってしまいがちなことと、似ているだろうか)
■「わたしは自分を、世界の一部として、生物学、心理学、ならびに社会学の単なる対象として考えることはできないし、一般に科学の考える世界のなかに私を閉じ込めることはできない」
*世界大戦が二度も起きるような20世紀前半の激動期において、科学の進歩が加速するにつれ、それによって不都合にさらされた「人間」への懸念が、さまざま思索されていたことに気づいた。しかし、それらの懸念は、その後の経済発展とともに、隅に追いやられてしまったのだろうか?
*21世紀前半の私たちにも同じように、「科学のもたらす進展についていけば、もっと自由に豊かに人生を育めるのか?」という不安が再浮上しているように思える。
*人間は言う。「私を機械にする会社は、うんざりだ。私たちは、もっと面白く成長したい」
組織は言う。「機械的業務は、機械に任せよう……ところで、あなたの面白味はどこなの?」
*人工知能の発達が進むほど、〈私〉の人間知性をどう育むのか、より問われる。ただしそれは、「○○職のスキルがあります」というほど単純な技能ではないような気がする。
*シュッツやメルロ=ポンティは、科学を否定したわけではない。よりメタな領域を捉えるためには、人間ポテンシャルを封じ込めることなく、もっとまるごと活用しようと提起しているのではないか。
次回更新は9月10日(水)、11時の予定です。
👉『これからの「優秀」って、なんだろう?』連載記事一覧はこちら
【イチオシ記事】添い寝とハグで充分だったのに…イケメンセラピストは突然身体に覆い被さり、そのまま…
【注目記事】一カ月で十キロもやせ、外見がガリガリになった夫。ただ事ではないと感じ、一番先に癌を疑った。病院へ行くよう強く言った結果…