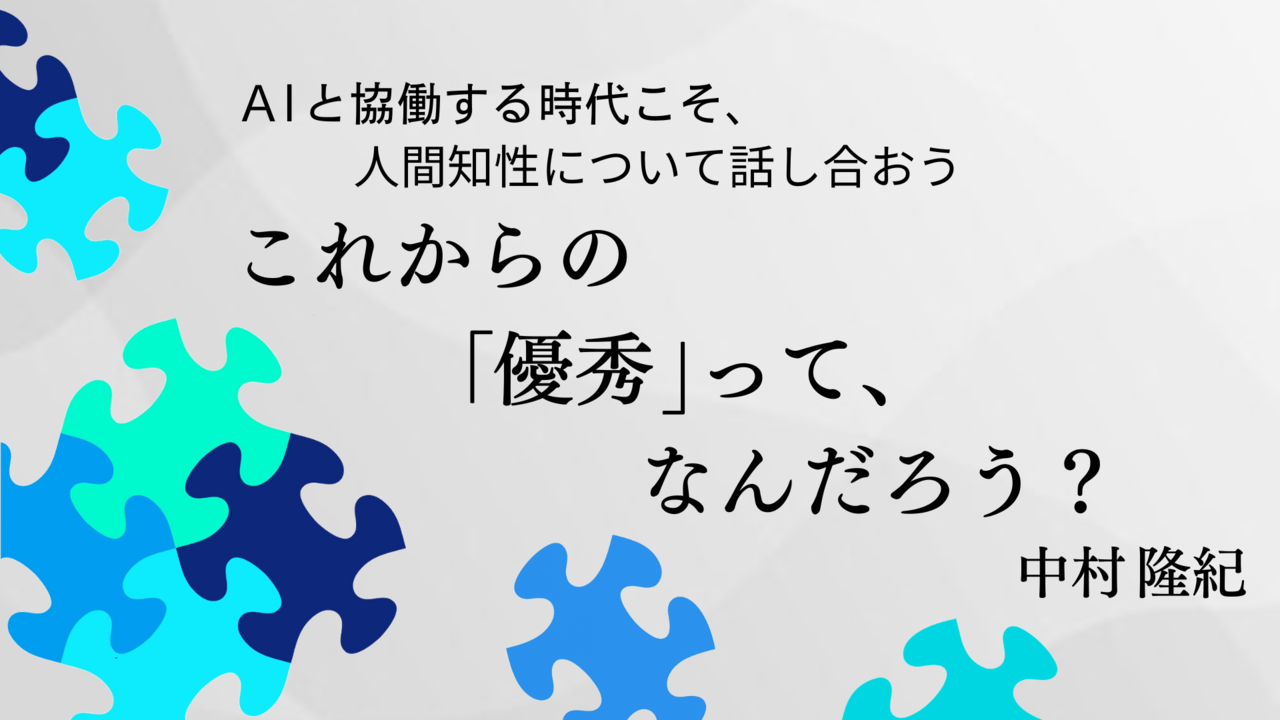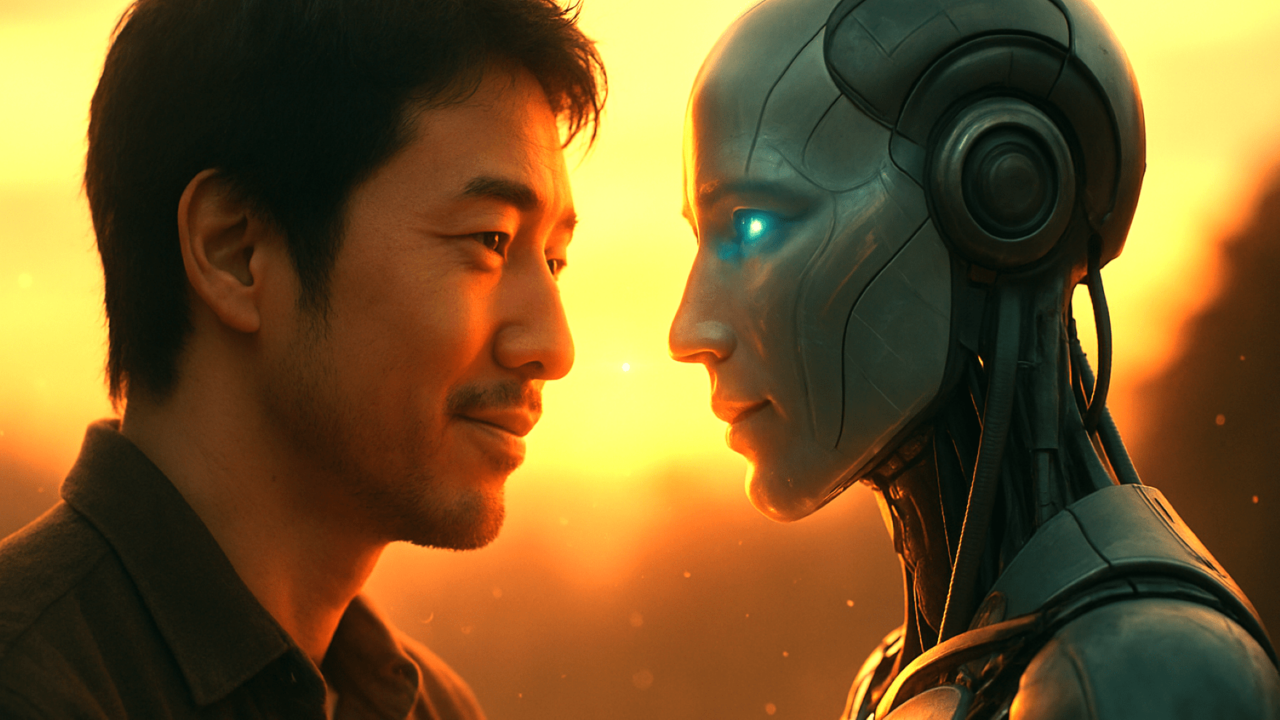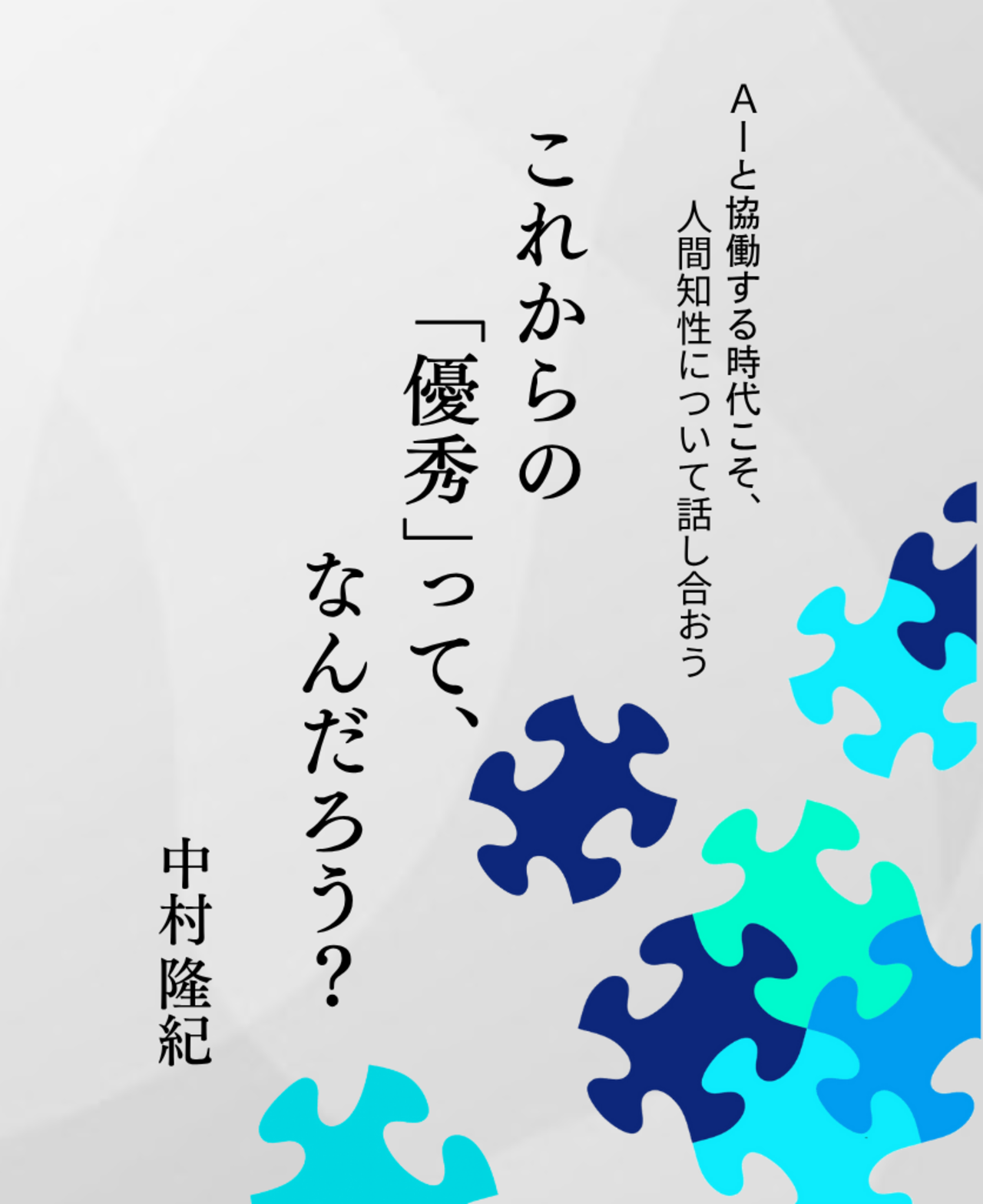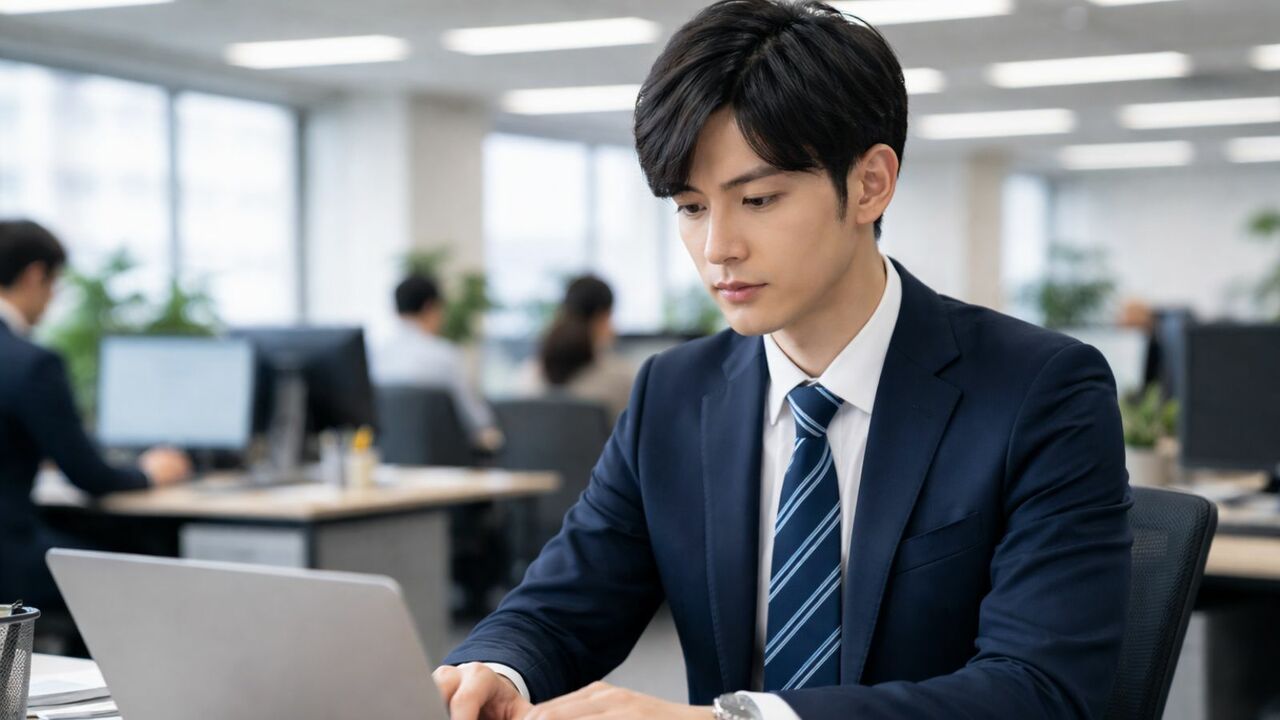【前回記事を読む】笑うZ世代、困る大人……おじさん構文とパーパスが示す分断の正体とは
第二章 すぐそばにある、知の分断
ネイビーにも、思い当たることがあった。〈イノベーション〉だ。
経営陣は、事業ドメインをトランスフォームするほどの破壊的なイノベーションを期待する。ところが管理セクターでは、持続的に事業効率を上げる改善を志向する。現場においては、たとえ短期でも新規の利益機会獲得を、イノベーションと読み替えてしまう。
了解し合っているようにみえる言葉の中で、自己都合的な解釈……そして分断が起こる。そのうちイノベーション推進活動は実態を失い、イノベーションという言葉そのものが組織から消え、いつもの対前年比/成長論に戻る。
リョウコさんのバズワード不信感が、さらにふくらむ。
「わたし、ダイバーシティっていう言葉も……もちろん、多様な価値観が共生することには賛成よ。でもね。わたしはこうだから、あなたはこうだからで、あら、価値観が違いましたね、それじゃあ、またね!って、ぶつけ合いも混ざり合いもなく隔たってしまったら、結局、分断したままじゃない?」
シュウトくんも、ふと、思い出す。
「YOさん、1on1って、知ってました?」
「もちろん。スラムダンクだろ?」
Keiさんがフォローする。
「いま企業では、1対1、なるべくパーソナルに上司と部下がコミュニケーションを取って成長の機会を後押ししよう、という場づくりがすすめられているんだ」
「僕、それを聞いて、びっくりしたんですよ。大きな組織は、そんなルールまでつくらなければ対話もないほど、ひとが離ればなれになっていたのかと思って」
僕の毎日は、パーソナルな対話ばっかり。そこから新しい発想や仕事が生まれてくるのに。大きな組織のひとたちは、なにに触発されて、ピンときたり、ジャンプしたりするんだろう?
「Kei、会社の現場は、相当に傷んでいるのかなぁ……」
おれたち小さな工務店だって、とっちゃんの職人と中東から来た若い衆が、しょっちゅう現場でしゃがんで話をしているよ。そのうえ、カミさんが頻繁に声をかけちゃあ、お節介を焼いている。そうしないと、仲間になれないじゃん。ウチは、その、1on1まみれだぜ。
Keiさんは仲間の指摘が効いて、しんみりと聞いている。そう、分断しているのはアメリカと中国どころじゃなくて、おれたち組織の日常なんだ。