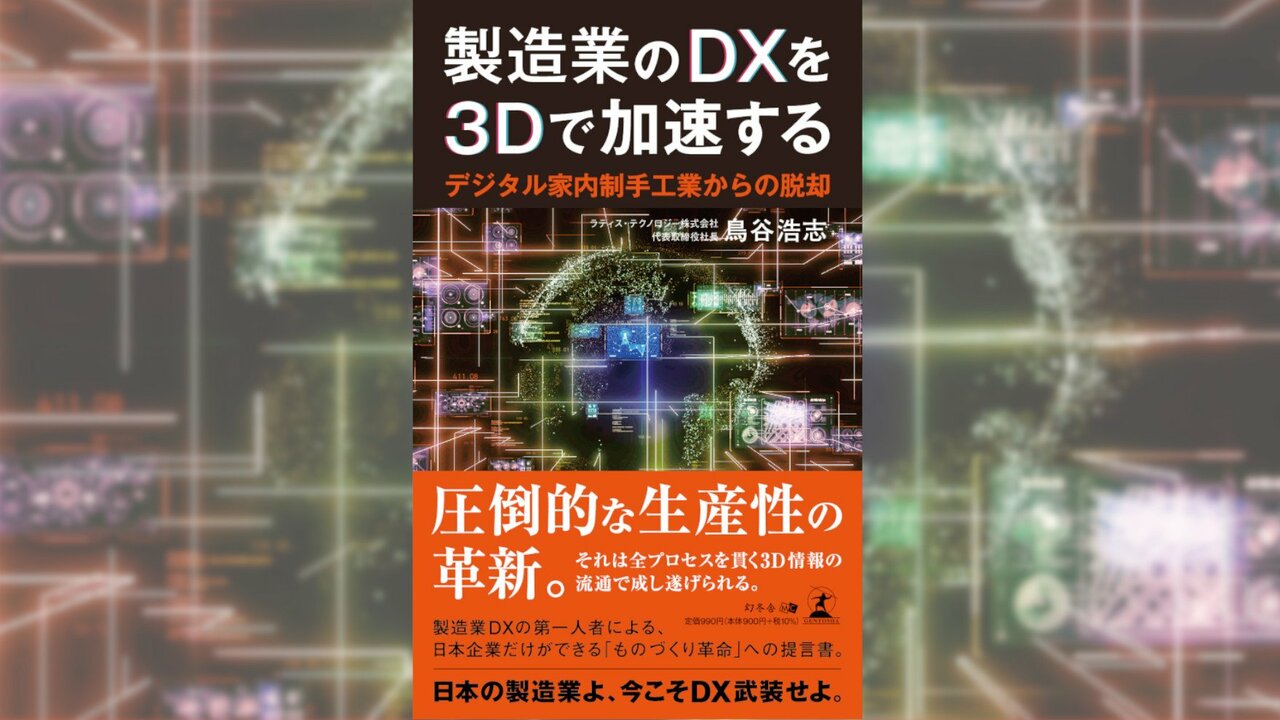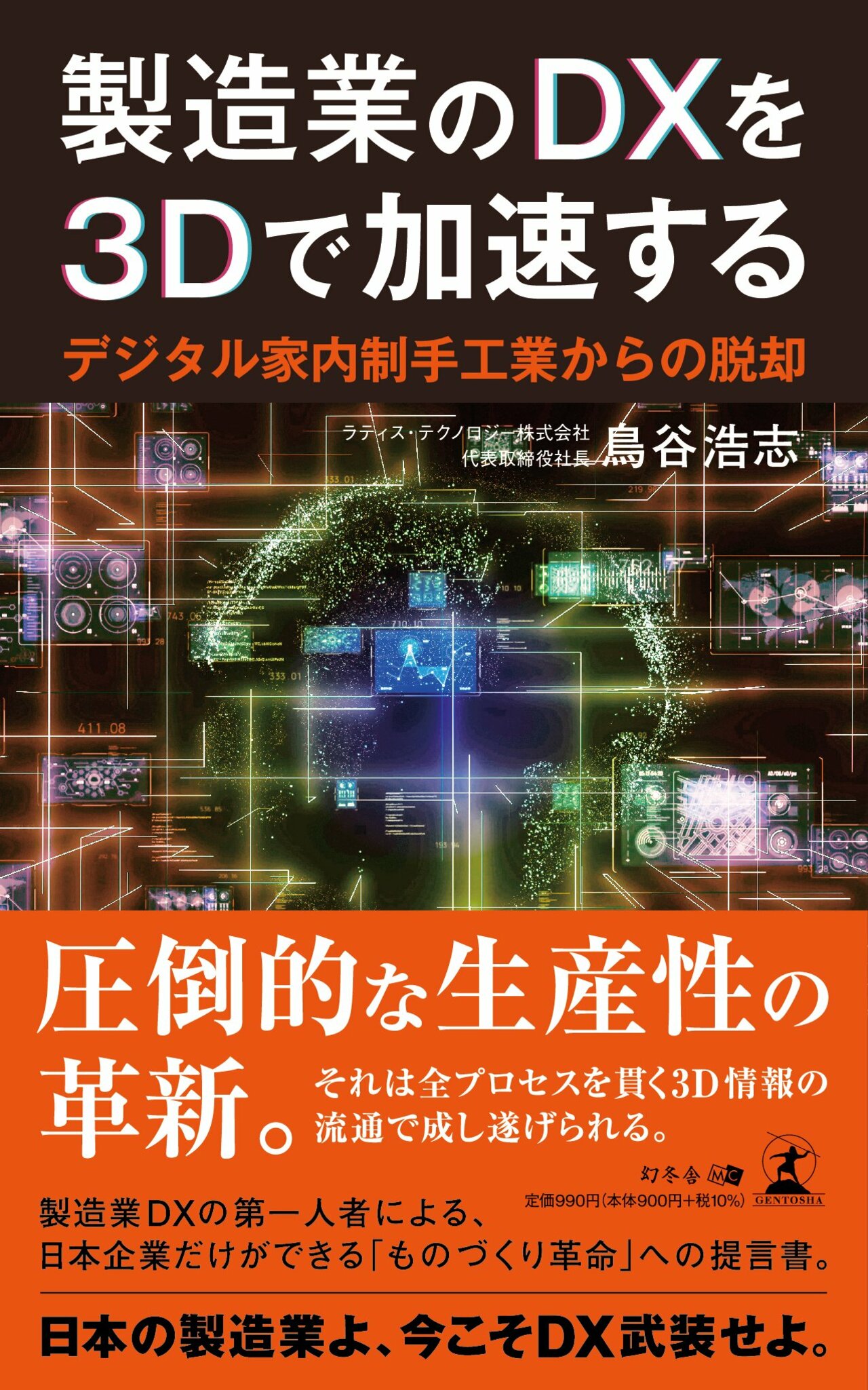【前回の記事を読む】日本より労働時間が年間300時間短く生産性が1・4倍のドイツ。「働きすぎ」と言われる日本人が学ぶべきマインドとは―。
第3章 ドイツ発Industrie4.0に学ぶ 製造業DX×3D
いったい何が日本と異なるのか?
日本と比較して、国をあげての標準化はドイツの得意とするところである。そのあたりの違いを農耕民族と狩猟民族の違いだとお二人は喝破(かっぱ)する。
農耕民族の日本は自分の田畑に自分で種を蒔いて時間をかけて丹精込めて育てる。
つまり、日本の製造業は自前主義に陥りやすい。各社各様で最適になるようライブラリ化を進めてしまうため、企業をまたいだ全体最適が進みにくくなる。たとえば、PLCにおいても主要メーカーである三菱電機、オムロン、キーエンスとそれぞれの規格が存在する。
一方、狩猟民族のドイツはお腹がすけば、他者と連携して狩りに出かけ獲物を仕留める。Industrie4.0でいえば、FA機器・配制機器・ケーブルなどの電機品データの標準化を進め、標準データベースにある電機品であれば、設計支援から受発注まで可能な仕組みを各社が連携して構築してしまう。
日本のFA業界でも、多くのメーカーのデバイス間で交信できるCC-Link(QR06)の規格をオープン化したり、エッジコンピューティング領域のオープンなソフトウェアプラットフォームを実現するEdgecross(QR07)を設立したり、といった動きもあるが、標準化では欧州がさらにその先を行く。
実は、このデータの標準化ができないことがDXを進める上でのボトルネックになる。汎用パッケージがあるにもかかわらず、自社に適したシステム構築をするユーザーが多いのも日本の特徴である。
では、なぜ日本では標準化が進まないのだろうか。尼崎氏は、国のリーダーシップと企業のスタンスの違いと指摘する。海外では政治家に理系出身も多く、技術的な事柄への知見・理解がある。一方、日本の官僚は文系出身が多く、技術への知見・理解が薄いのではないかという。
また、このためには、企業はITリテラシーを高め、発想を変えていく必要があるだろう。
たとえば欧州では、プログラム容量が大きいPLCを当たり前に購入し、それに関わる人件費を抑えようと発想する。一方、日本ではコスト低減のために容量の小さなPLCを購入し、設計者はいかにプログラムサイズを小さくするかに明け暮れる。この間に、欧州の設計者はソフトウェアの標準化に知恵を絞ることができるというわけである。