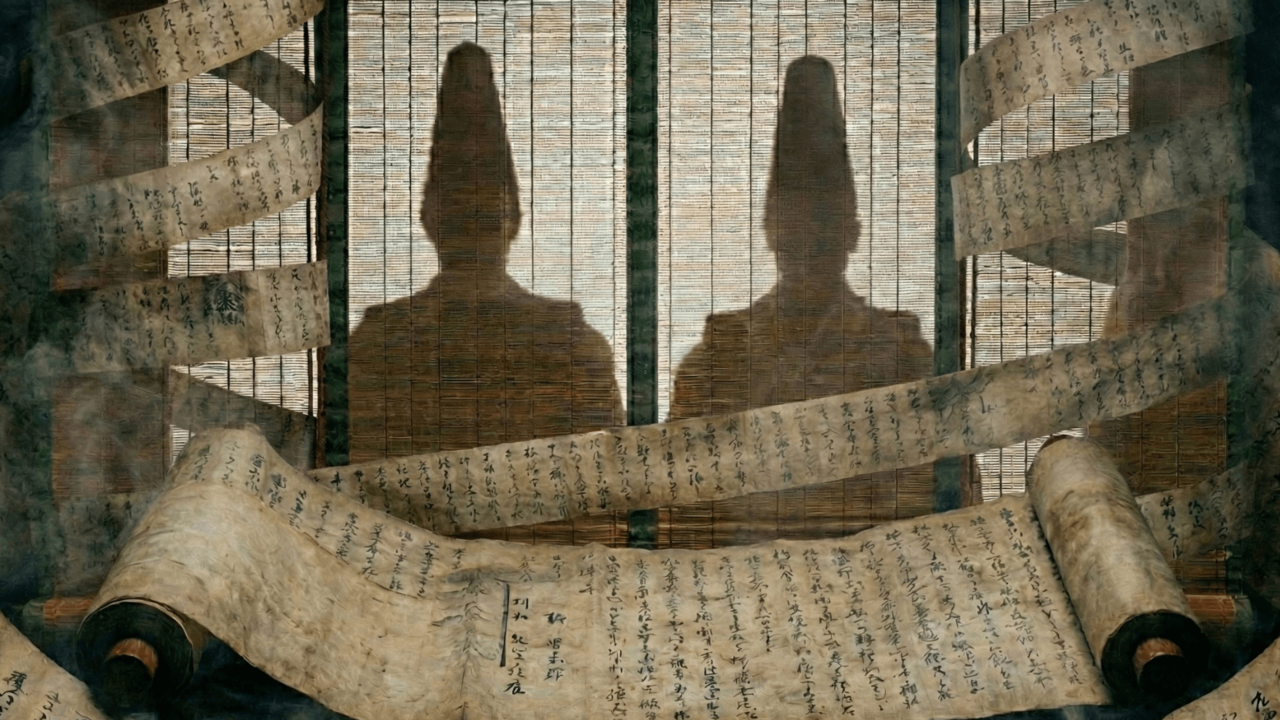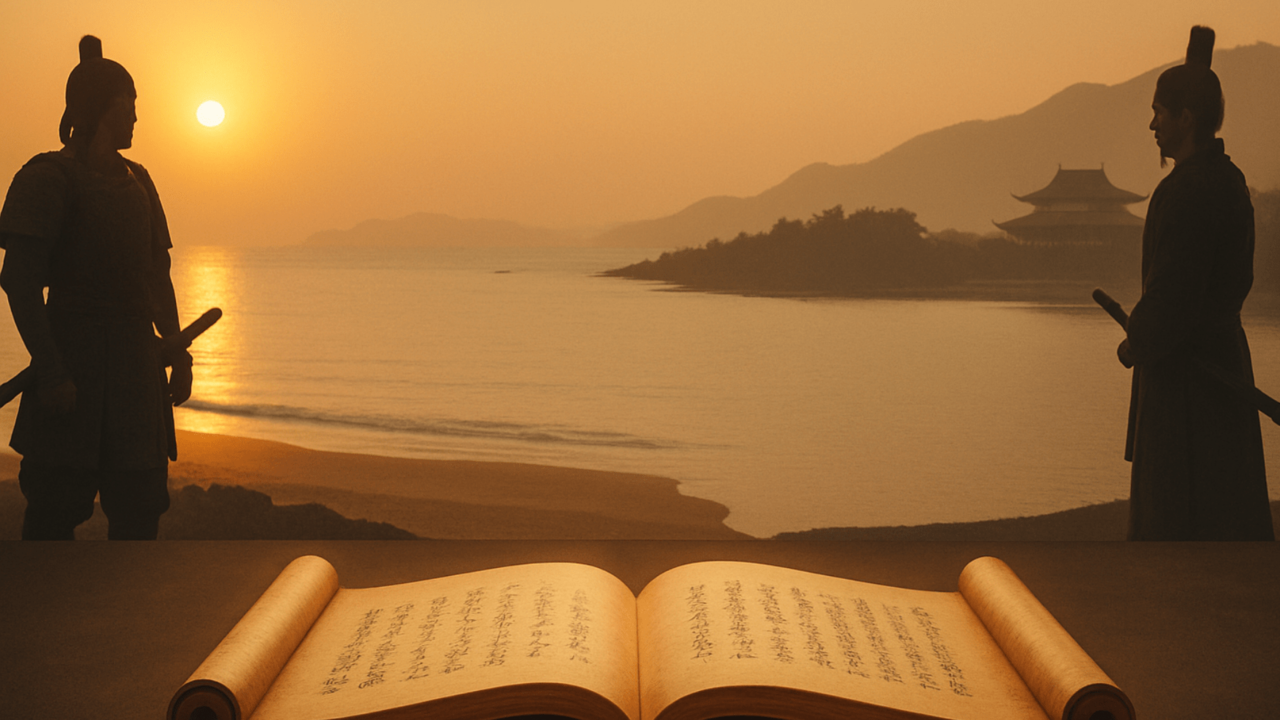この謎解きの情報を与えるのが、『魏志倭人伝裴松之注(魏略逸文岩波文庫)』である。そこには「其俗不知正歳四時但記春耕秋収為年紀」(倭国の風俗では正しい年の数え方や四季を知らない。ただ春の農耕期と秋の収穫期をもって一年と記す。)とある。つまり春と秋に一年の始まりがあり、現在の一年(正歳)の二倍年暦となることを伝えている。
前述の『晋書』に「秋の収穫期をもって一年とする」の解釈で「秋から次の秋まで」とする考えに違和感を示した。中華民は古代から現在に至るまで「春節」を一年の始まりとしていた。したがって『晋書』の記述は春からの一年は当然だが、秋からも一年(現代的に言えば半年)が始まるとの意味ではないだろうか。
このように理解すれば裴松の注釈と同様、春と秋に始まる半年を一年とする数え方を採っていたと考えられる。
古代の天皇が長寿であるが二百才を超えない理由はこの二倍年暦で合理的に説明がつく。最長寿の「崇神天皇」の百六八才が実際は八四才とすれば、単に長生きしたのだと言える。
『記紀』の中でいつまで二倍年暦の情報を用いていたのだろうか。『古事記』では「雄略天皇」(二一代)が百二四才、「顕宗天皇」(二三代)が四三才となっており、「雄略天皇」の時代が二倍年暦の最後かもしれない。中国史書『隋書』には「正月一日には矢を射て戯れ 酒を飲む」とあり、隋代の倭国では中国式の「正歳」の暦を用いていたと考えてよい。
二‐一「神功皇后紀」巻第九『魏志』引用の記事
是年(ことし)、太歳己未(つちのとひつじ)。魏志(ぎし)に云(い)はく、明帝(めいてい)の景初(けいしょ)の三年の六月、倭(わ)の女王(じょわう)、大夫(たいふ)難斗米等(ら)を遣(つかは)して、郡(こほり)に詣(いた)りて、天子に詣(いた)らむことを求(もと)めて朝献(てうけん)す。太守(たいしゅ)鄧夏、吏(り)を遣(つかは)して将(ゐ)て送(おく)りて、京都(けいと)に詣(いた)らしむ。
四〇年。魏志に云はく、正始(せいし)の元年に、建忠校尉梯携等(けんちうこういていけいら)を遣(つかは)して、詔書印綬(せうしょいんじゅ)を奉(たてまつ)りて、倭国(わのくに)に詣(いた)らしむ。
四三年。魏志(ぎし)に云(い)はく、正始(せいし)の四年、倭王、復使大夫(またつかひたいふ)伊声者掖耶約等八人(らやたり)を遣(つかは)して上献(しょうけん)す。
四六年の春三月(はるやよひ)の乙亥(きのとのい)の朔(ついたちのひ)に、斯摩宿禰(しまのすくね)を卓淳国(とくじゅんのくに)に遣す。
【イチオシ記事】添い寝とハグで充分だったのに…イケメンセラピストは突然身体に覆い被さり、そのまま…
【注目記事】一カ月で十キロもやせ、外見がガリガリになった夫。ただ事ではないと感じ、一番先に癌を疑った。病院へ行くよう強く言った結果…