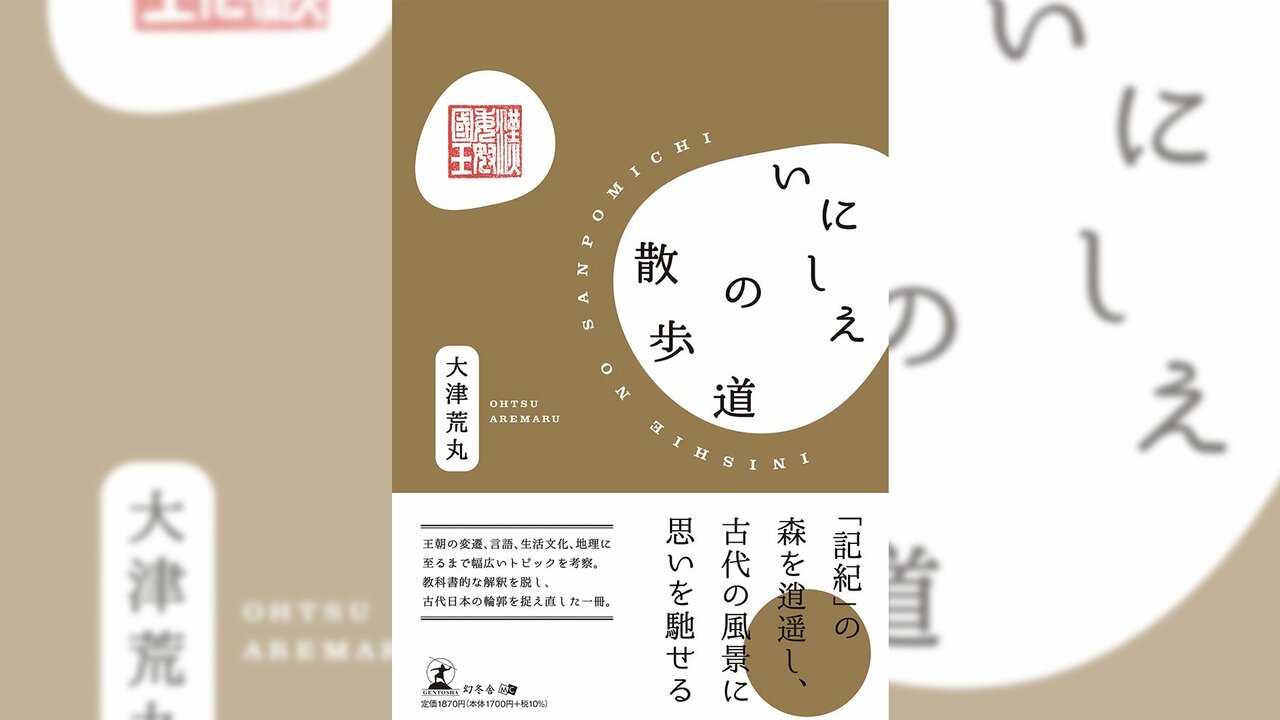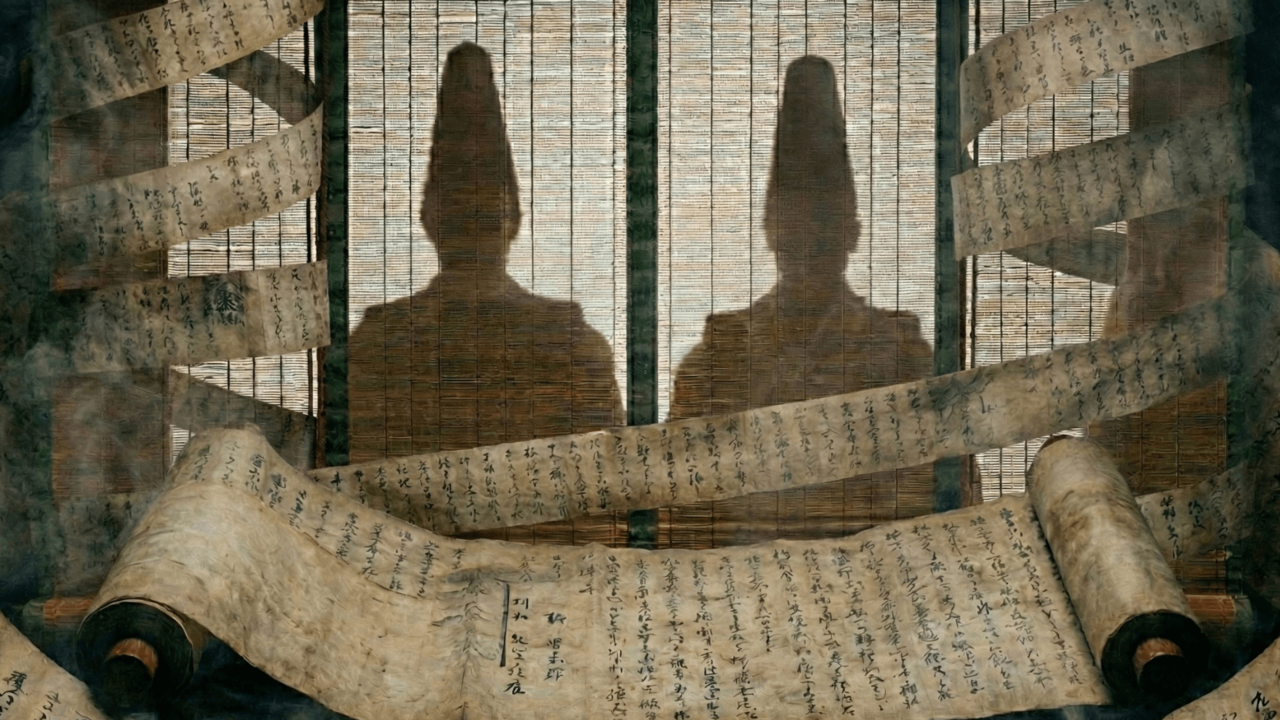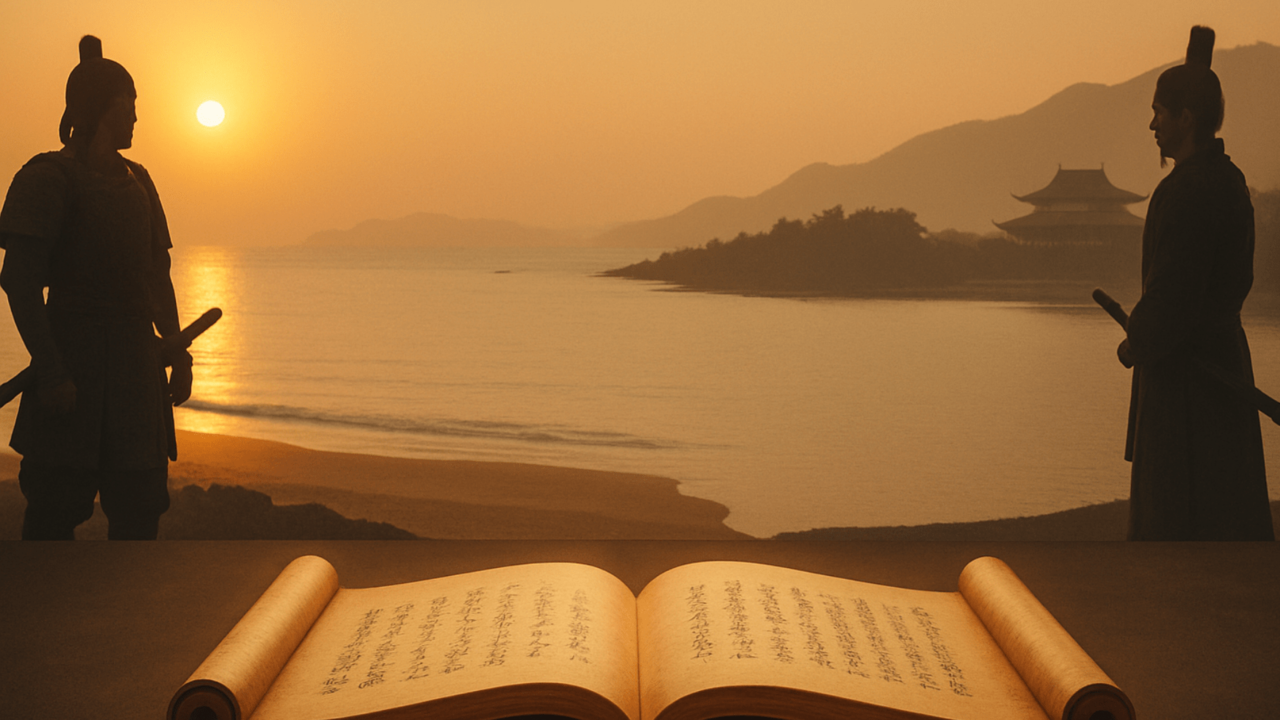【前回の記事を読む】日本古代史を再考する『記紀』の読み方―。「倭王武=雄略天皇」説が広く流布されているが、これが成立しないとなると...
文献・金文の章
第三話 数値情報から見る二倍年暦と皇統譜
一般的には時代を遡るほど情報が曖昧になると考えられるが、逆になっている。『日本書紀』では、立太子年とその時の年齢や享年は主に古い天皇に記載されている。
さらに表を見て誰もがおかしいと思う点は天皇の寿命である。『古事記』では八〇才を超える天皇が一一名、そのうち百才以上の天皇が八名いる。『日本書紀』では天皇在位期間が六〇年以上の天皇が一一名で、「孝安天皇」(六代)の一〇二年が最長である。
これらの疑問点をどう考えるべきなのか。
最も安易な解決法は「捏造があった」とすることだろう。あり得ないことが記載されているのだから、編纂者の手によって適当に創作されたとする。
しかしこれを是認すれば『記紀』は歴史的文献として全く無価値の物となる。捏造部分とそれ以外との区別をつけることはできない。多分歴史学者は考古学、文献学による状況証拠を突き合わせれば、その区別は可能だと言うかもしれない。
しかしこの手法は、自分の都合の良い部分を「つまみ食い」し、不利なことは捏造だとする恣意的な取捨選択を横行させる温床となっている。典型的な例が「倭の五王」の分析だろう(第二話)。