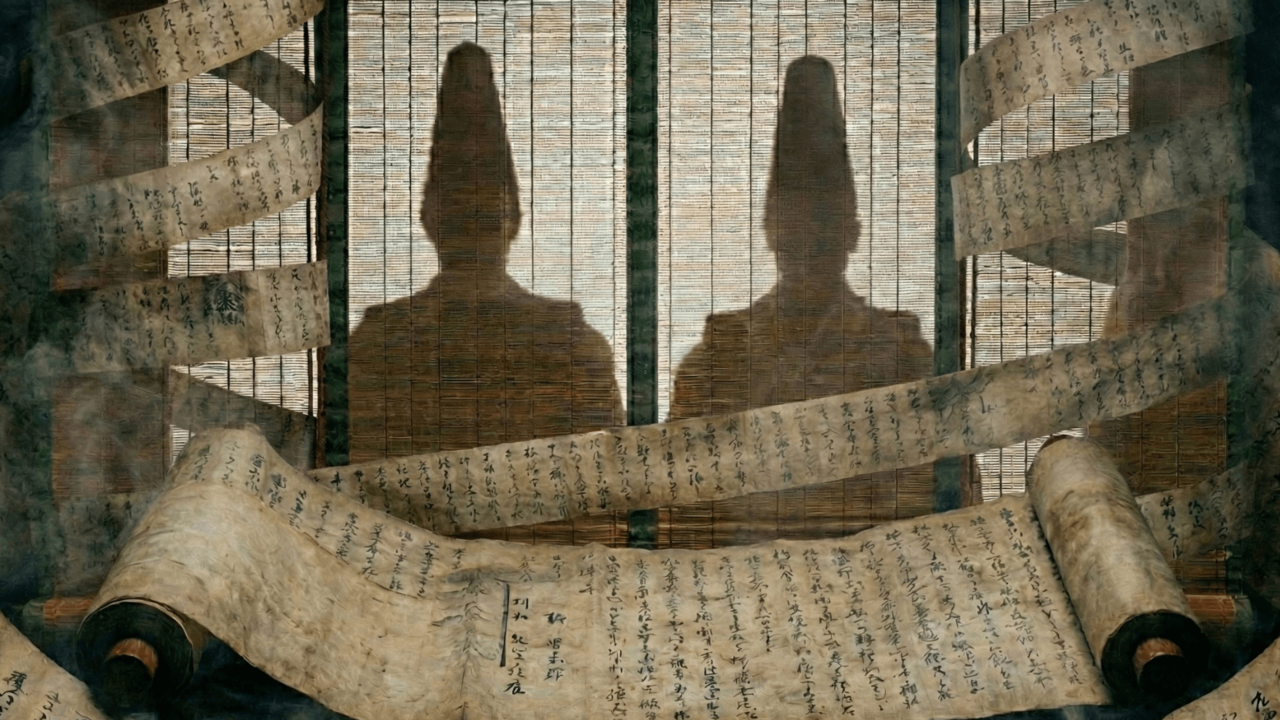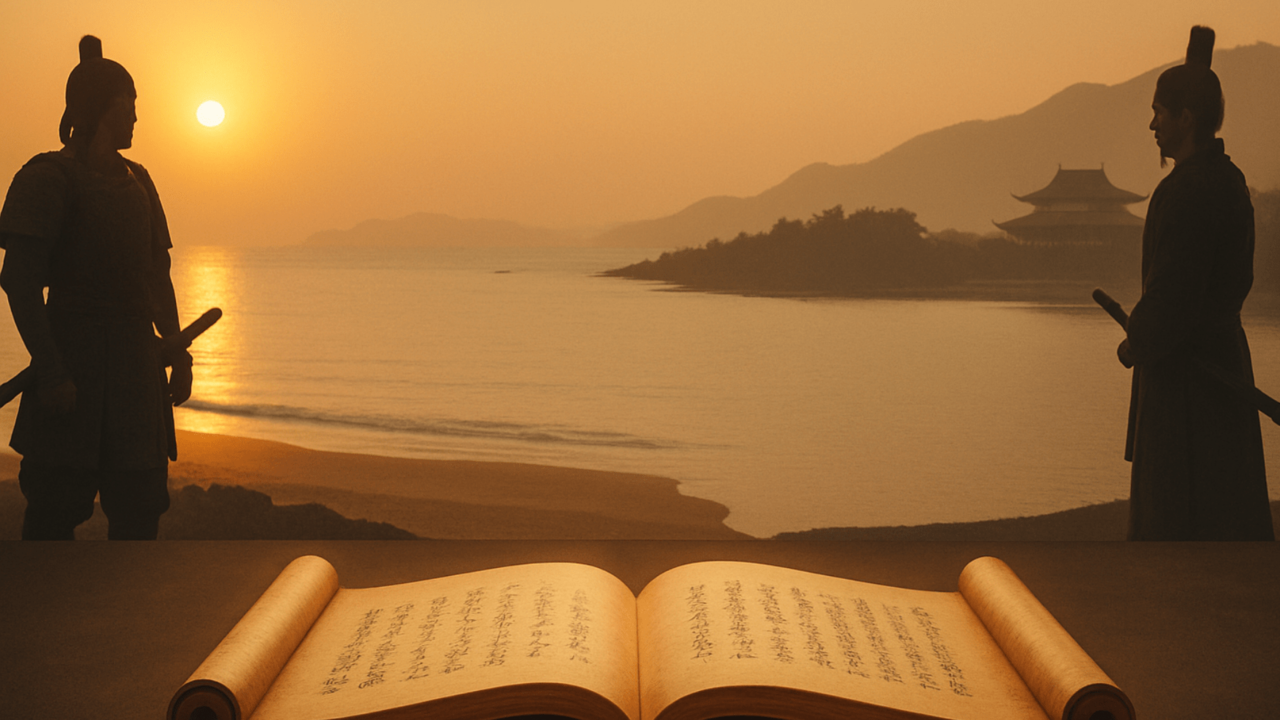この著述では創作による捏造はなかったことを前提に議論している。
すでに述べたように「継体天皇」(二六代)を傍流とする姿勢は、『記紀』編纂者に捏造する意志があることを感じさせない。また「神功皇后紀」において『魏志』を引用して、皇后が邪馬台国の卑弥呼に対応させようとする意図はありそうだが、皇后が「親魏倭王」の金印を授与されたとか、使大夫伊聲耆を遣わせたとの捏造は一切していない(引用資料二‐一)。
根本の歴史の流れを捏造する意図を感じさせない編纂者の編集態度を考えるなら、瑣末の数値を操作するとは思えない。
繰り返すが、この著述では『記紀』編纂時に集められた膨大なデータバンクにない、創作行為による捏造は行われなかったとの立場を採っている。これに沿って前述した数値情報の不可解な点を考察したい。
最初に天皇の長寿に関して取り上げるが、すでに多くの在野の歴史研究者が合理的な解釈を述べている。
ここでは「二倍年暦」という常識化しつつある知見の復習をすることになる。中国の史書を見ると面白い共通点がある。『魏志』から南北朝の『梁書』による倭国の記述に「其人(倭人)寿考(長寿)、或百年或八九十年」とある。
隋以前の中国では「倭人は長命で八十~百才の者が多くいる」とされていた。つまり百才を越える人がいてもおかしくないとの認識である。あたかも弥生、古墳時代にすでに高齢、長寿社会が実現していたかのようである。実際には食料や衛生事情から考えてあり得ない。
数字をよく眺めると意外にとんでもない数字がないことに気づく。「齢三百才、五百才」と捏造しても良いところだが、すべてが二百才以下になっている。最も長寿の「崇神(すじん)天皇」(一〇代)で一六八才である。
これらの数値の意味を理解する上で中国史書の記載が重要だと考えられる。『晋書』には「不知正歳、四節」とあり、倭人の風習には「正しい年紀や四季を知らない」と見なされていた。その後に「但計秋収之時、以為年紀」(但し秋の収穫の時を計り、もって一年とする)と続く。
この文を見ると秋から次の秋までを一年とするように読みとれるが、丸一年の中には四季があり、「不知正歳四節」とは相いれないように思える。