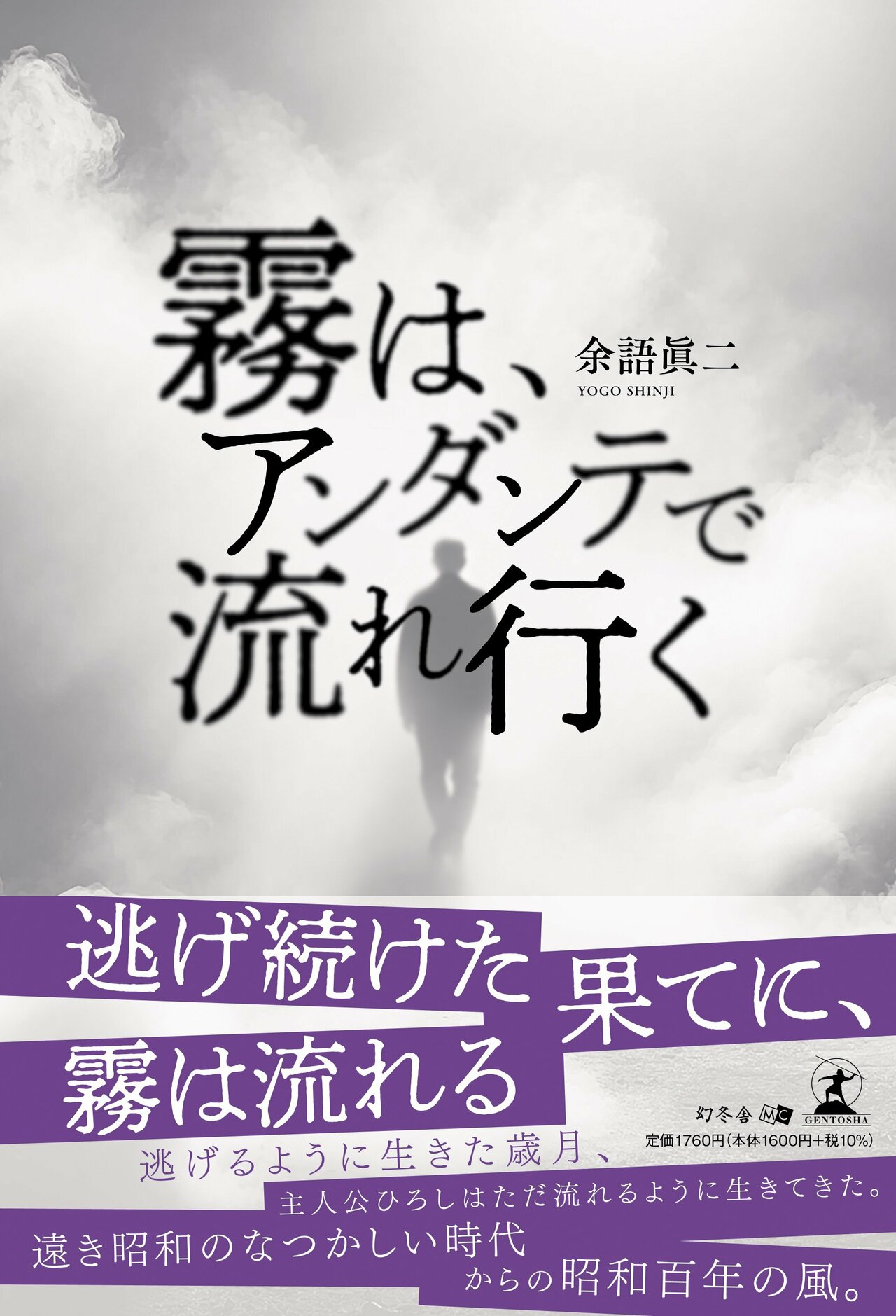ずいぶん以前、土だけで造った藁屋根の小屋がありそこで馬を飼っていた。農耕馬だが、お祭りの日だけは祭りの飾りを付けられて駆り出されていた。
その小屋の横からは、サトウキビの畑が続いていた。ひろしの背丈より高く伸びたサトウキビのことを「サトノキ」と村では呼んでいる。
サトウキビから黒砂糖を作っていたのだろう。ひろしのお爺ちゃんは、サトノキを引き抜くように倒して、細い竹のような一本をナタで切り、短くなったサトノキのカワを裂いて、ひろしに手渡してくれる。その一切れを口に入れて噛むと甘い汁が出る。
チューインガムがなかった頃の噛む菓子だった。この頃の甘いものといえば、これくらいだった。
稲作の田植えの前、稲田の代掻(しろか)きは馬で行っていた。
お爺ちゃんは朝早くから暗くなるまで田植えをして、全身が鉛のように重くなった。家に帰ってくると馬屋の横の五右衛門風呂に入り、出ると待ちきれないように土間で茶碗酒をひっかける。
そして、夕食の後もお爺ちゃんは茶碗酒を飲みながらお寺の和尚から聞いた話をするのだ。孔子の話もよくしていた。