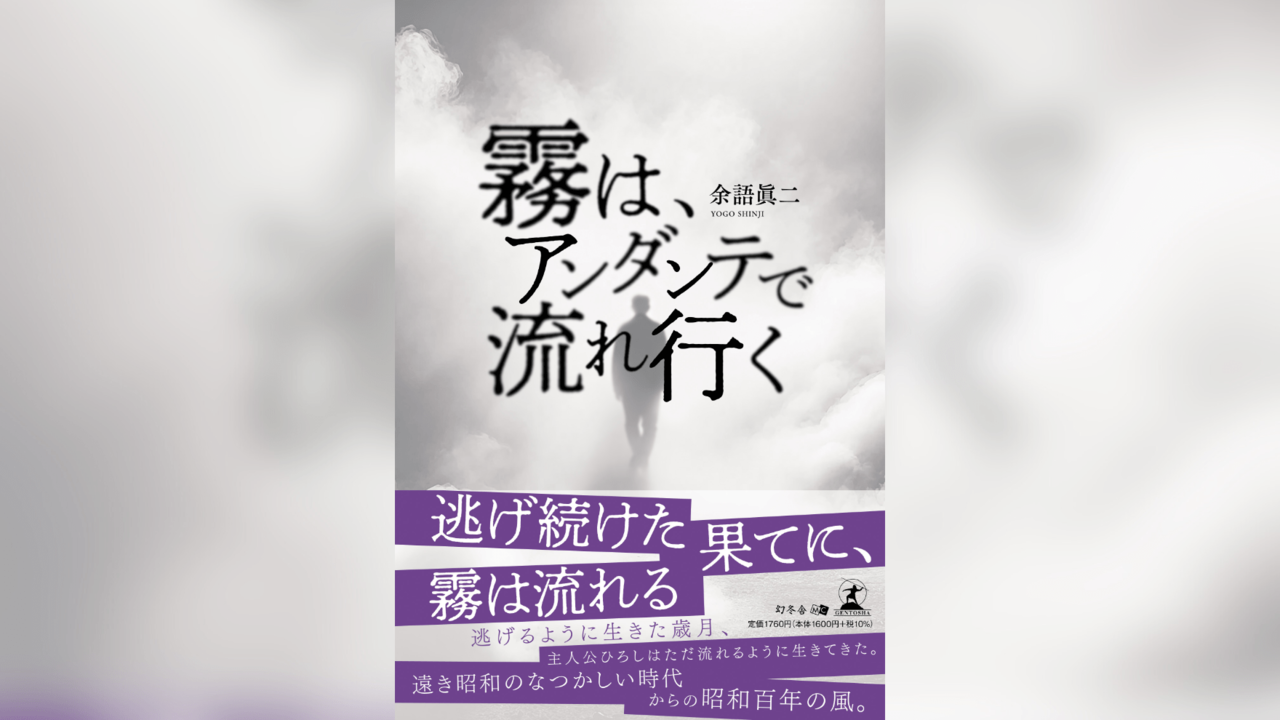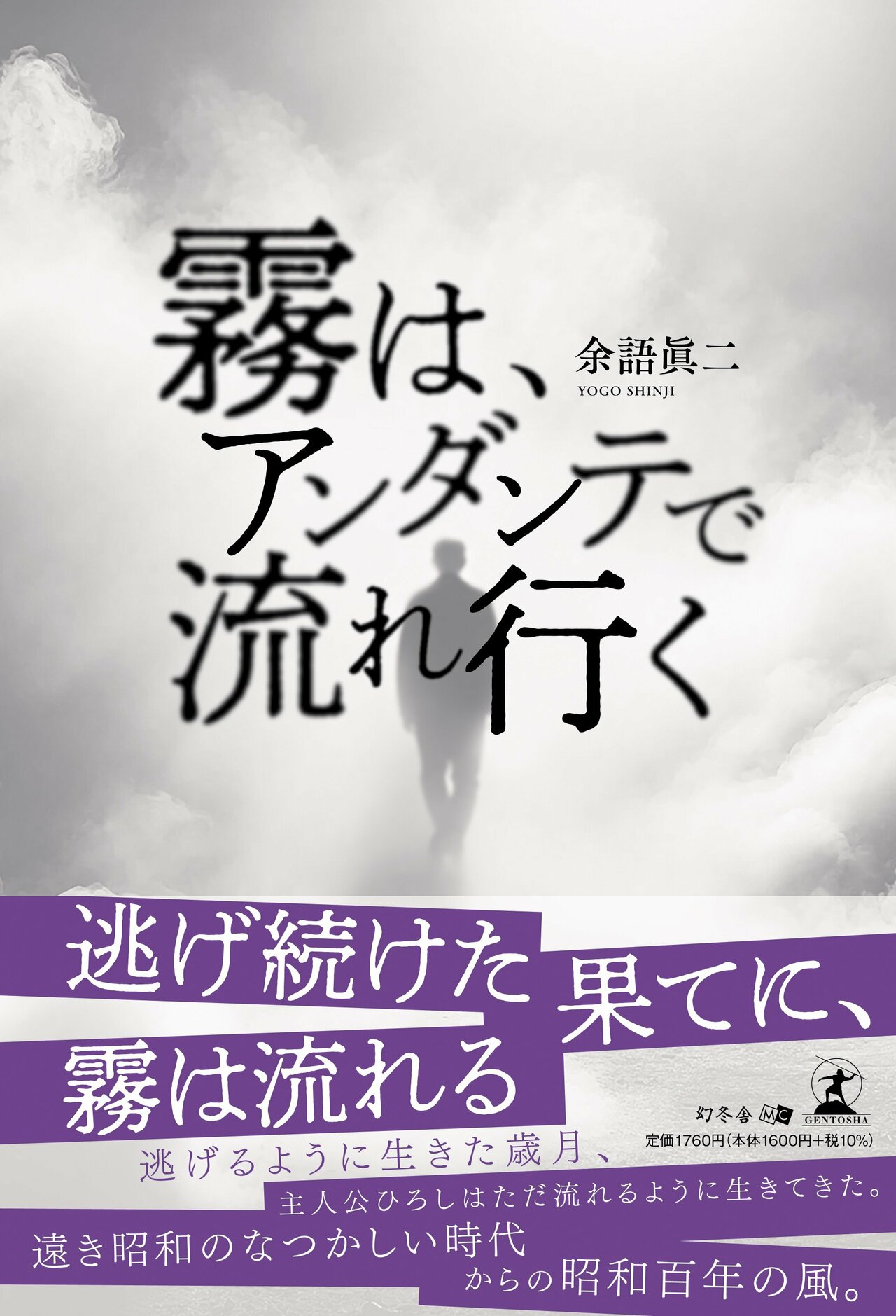【前回記事を読む】社長の一言で、気づいたら結婚することになっていた――高卒で工務店に就職した父と、その工務店で事務をしていた母は…
風の部 霧は、アンダンテで流れ行く
第一章
孔子の弟子、子路(しろ)が「いかにして死者の霊魂に仕えるか」と孔子に問うと「生きている人間にさえ満足に仕えることができないのに、どうして死者の霊に仕えられよう」と言われた。
すると子路が「では一体、死とはどういうものであろうか?」と問うと、それに孔子は「未だ生を知らず、焉(いずく)んぞ死を知らん」と答えられたという。
お寺の説法が落語の起源という話だが、この話はお爺ちゃんにも良くわからなかった。だからこそ、何故かよく思い出していた。
ひろしの妹である孫娘の圭子が生まれた時、お爺ちゃんはものすごく喜んで、馬に米一俵を積んで町に出て、立派な雛飾りを買ってきた。
毎年桃の節句には、ひろしの家の座敷に飾られていた。お爺ちゃんは、ある秋の稲刈りの最中、草刈り鎌を手にしたまま亡くなった。
刈り取られた稲穂が途中まできれいに並べられていた。刈り残され、首を垂れた穂はお爺ちゃんに刈り取られるのを待っていた。
横の畦道には、一升徳利(どっくり)が茶碗とともに残っていた。
小学生のある夜、とてつもない嵐になった。伊勢湾台風だった。翌朝、ひろしの近所の家の何軒かは、屋根瓦が風に飛ばされ木造の塀は倒されていた。
何日か経って、ずっと10円だった近くのパン屋のアンバンが5円値上がりした。これがこの街の高度経済成長の始まりだつた。
小学5年生になると、毎年夏休みに海の家へ行く2泊の行事が行われていた。
しかし、ひろしが5年になった年は、なぜか南アルプス麓のキャンプ村でのキャンプに変わり、費用を負担することができたクラスの2割ぐらいが参加した。ひろしの家も、なんとか参加させてくれた。「小さい頃の思い出は、大切な財産になると思って行かせたんだよ」と、母からのちに聞いた。
バスで汽車の駅まで行き、当時はもう少なくなった煙を吐く蒸気機関車に乗った。汽笛を鳴らし、トンネルに入ると窓を閉めなくてはいけない。閉め忘れていると煤(すす)が入り、顔を拭くと煤で黒くなる。ひろしたちは案の定、窓を閉め忘れて、友達と真っ黒になった顔を笑い合った。